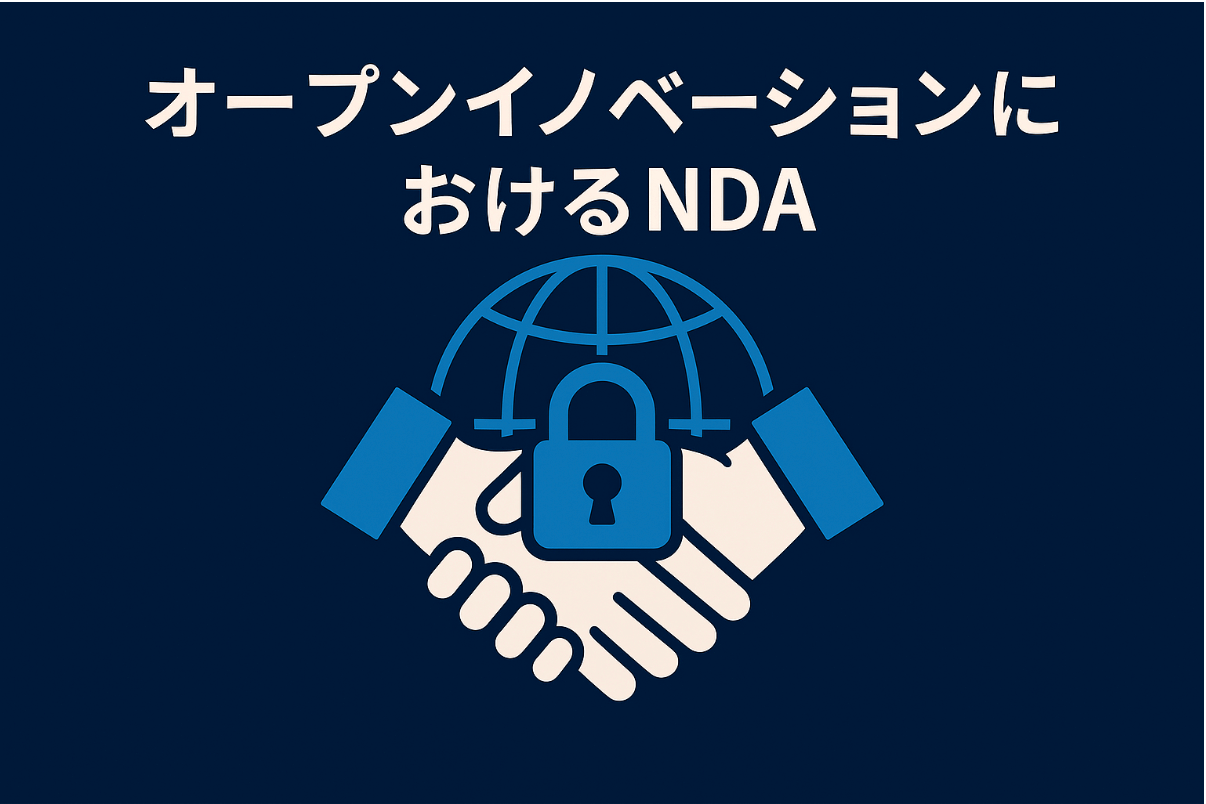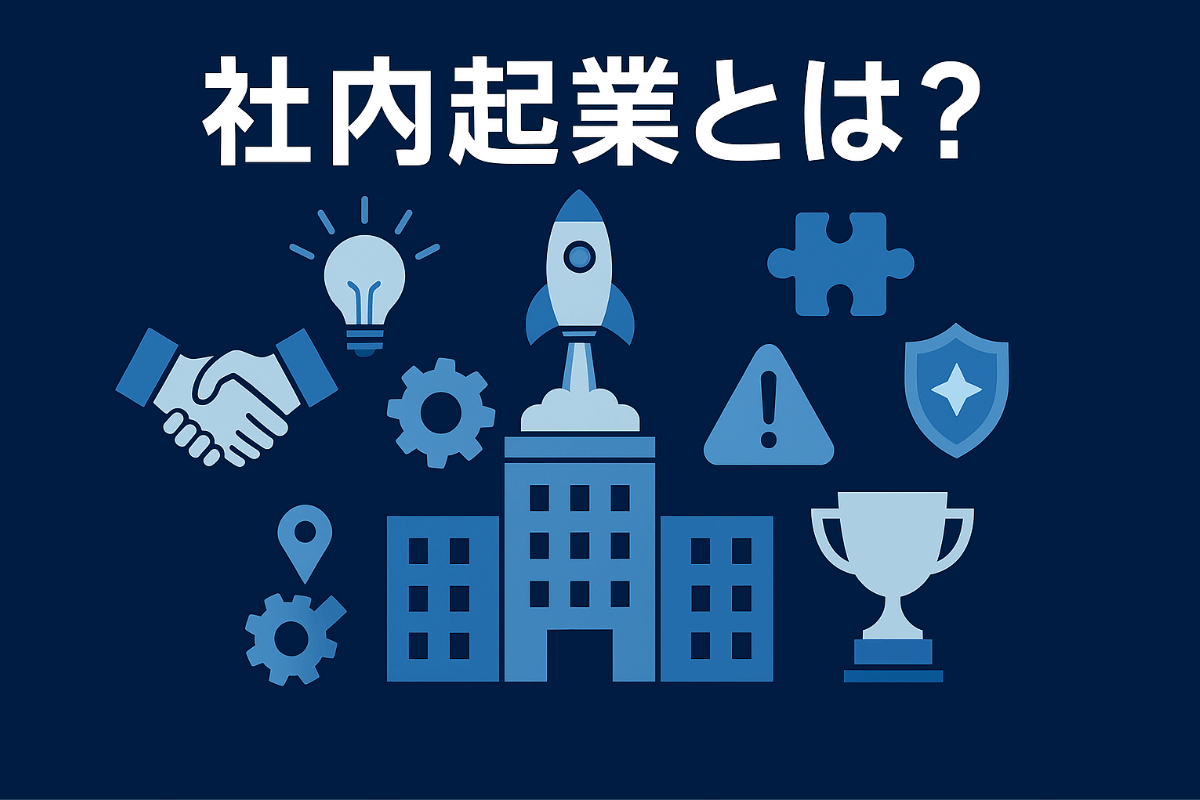「協業」とは、2社以上の会社が協力して事業を成功させることを指します。
これまで研究開発から製品開発、販売までを自社で一貫して行う「クローズドイノベーション」が主流であった日本では、他社との協業は考えにくかったかもしれません。
しかし、近年大企業×スタートアップ企業の協業が増えており、成功事例も多数存在します。
そこで今回は大企業とスタートアップ企業が協業するメリットや成功事例、成功のポイントを深掘りしていきます。他社との協業に興味がある方はぜひ、今回の記事をご覧ください。
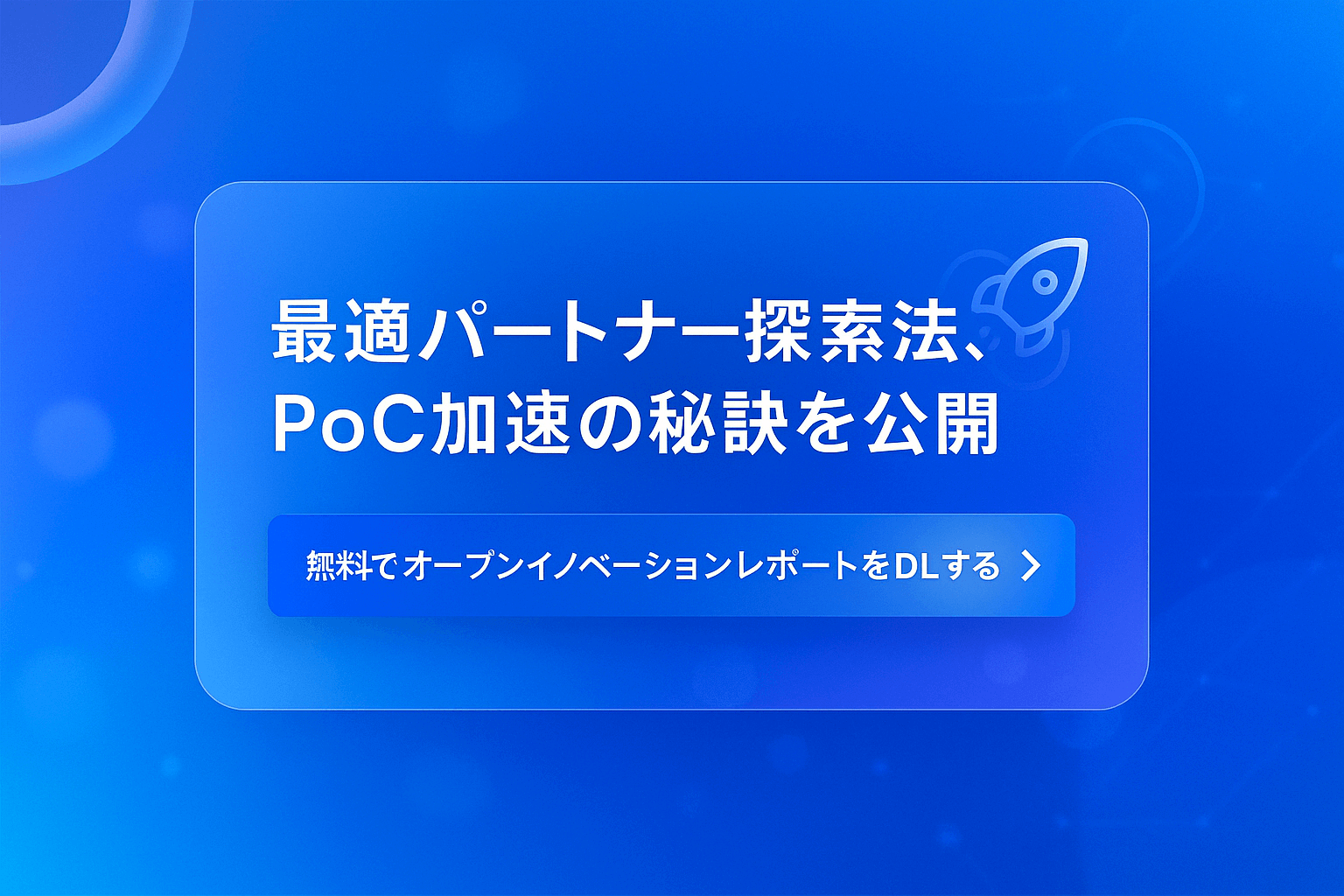
実際のスタートアップ×大企業の協業現場で何が起きているのか生の事例をご覧ください
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
協業を成功に導く具体的なマッチング手法やコミュニケーションのポイント、契約締結までのプロセスを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の協業推進にご活用ください。
近年大企業とスタートアップ企業の協業が増加している背景
これまで企業では、自社の重要な技術やアイデアを他社に模倣されないように研究開発から販売までを一貫して自社で管理する「クローズドイノベーション」が主流でした。
しかし、海外の研究開発が発表したレポートによると、世界的な景気減速により企業の予算が圧迫されることで、自社内だけですべての業務を完結させるのではなく、より専門性が高いスタートアップ企業への事業のアウトソーシング化が急増しているという研究結果が出ています。
特にイノベーション大国であるアメリカでは、企業の72%がスタートアップ企業とのプロジェクトを実施し、そのうち67%が「スタートアップとの協業が必要不可欠である」と回答しています。
(出典:The Open Innovation Report 2023)
大企業がスタートアップ企業と協業するメリット

大企業がスタートアップ企業と協業するメリットは大きくわけて以下2点です。
- イノベーション創出と新技術の獲得
- 新市場開拓と革新的なアイデアの創出
それぞれ詳しく解説していきます。
(引用:日本の大企業とスタートアップとの協業関係に関する実証分析)
イノベーション創出と新技術の獲得
自社にはないスキルや知見をローコストかつ短時間で習得できることはスタートアップ企業と協業する大きなメリットです。
企業の大きな成長を求めて新規事業やDC(デジタルトランスフォーメーション)に乗り出すためには、その分野の知見やスキルが必要となります。しかし、新たな技術を社内でゼロから構築しようと思うと膨大なコストと時間がかかってしまうでしょう。
そこで、スタートアップ企業と協業することで、すでに成熟した知識やスキル、ノウハウなどのリソースを外部から習得できます。
新市場開拓と革新的なアイデアの創出
スタートアップ企業と協業することで自社内の技術やアイデアだけでは生み出せなかった革新的な製品やサービスを生み出せることは大きなメリットの1つです。
大企業は長年親しまれてきた定番の商品やサービスがもたらす顧客の定着によって経営の基盤が安定しています。しかし、流行の移り変わりや消費者の意識の変化が激しい現代の市場では、時代にマッチした商品開発や競合他社とは異なる斬新なアイディアを求められることも多くあります。
このような現代のニーズを過敏にキャッチするスキルや新たなアイデアを創造する発想力をアウトソーシングしたい時には、スタートアップ企業との協業が効果的と言えるでしょう。
スタートアップ企業が大企業と協業するメリット
スタートアップ企業が大企業と協業するメリットは以下の3つが挙げられます。
- 資金調達と経営安定化
- 販路拡大と市場アクセス
- 信頼性とブランド力の向上
それぞれ詳しく見ていきましょう。
(引用:日本の大企業とスタートアップとの協業関係に関する実証分析)
資金調達と経営安定化
スタートアップ企業が協業する最大のメリットは、大企業からの資金調達による経営基盤の安定化です。
企業としての実績や信頼性が低いスタートアップ企業は金融機関からの融資や投資家からの出資が十分に受けられず、経営が不安定になるケースも少なくありません。しかし、大企業との協業を成功させれば大企業からの安定した資金調達ができるため、さらなる自社への投資によって事業を拡大させることができます。
販路拡大と市場アクセス
スタートアップ企業が大企業と協業することで、さらなる販路拡大や市場開拓に繋がることも協業のメリットです。
大企業の場合、自社内だけでなく、さまざまな外部企業との繋がりを持っています。そのため、協業によって大企業からの信頼を得れば、企業の太いパイプを通してさまざまな企業と取引できる可能性があります。
スタートアップ企業を始めたものの、企業との繋がりや人脈がない場合には大企業とタックを組むことでより高い視野で市場にアクセスすることが可能となります。
信頼性とブランド力の向上
大企業と協業することで、自社の信頼性やブランド力を向上させられることも1つのメリットです。
スタートアップ企業の場合、企業に対するブランド価値や信頼性が低く、なかなか他社との契約に結び付かないことも多いでしょう。しかし、大企業と協業した経験を持っていると、その企業に関する信頼性は大きく高まります。
そのため、大企業と協業し、自社のブランド価値を底上げすることで、その後の他社との契約もスムーズに決まるケースが多くなります。
スタートアップ企業と大企業が協業して成功した事例
日本の誰もが知るような大企業とスタートアップ企業が協業して成功を収めた事例を4つ紹介します。
- 株式会社エニキャリ x 株式会社明治
- 株式会社ヘルスケアシステムズ x 花王株式会社
- 株式会社アジラ x セコム株式会社
- メディア ブレスト × ANA
それぞれ詳しく見ていきましょう。
株式会社エニキャリ x 株式会社明治
株式会社明治は、食品事業を展開している日本最大手の企業で、国内だけでなく海外でも高いシェアを誇ります。そんな株式会社明治では、新規事業として「できたての乳製品」のおいしさを近隣の消費者に届ける事業を模索していました。
実際に試作品のテスト販売を通してPMFの検証はできたものの、「少量生産・随時配送」の仕組みを新たに構築しなければならないという課題に直面していたのです。
そこで、スタートアップ企業である「株式会社エニキャリ」が管理画面でドライバーや荷物の位置や状況、着荷予測時間がリアルタイムで分かる配送管理システム「ADMS(アダムス)」を提供しました。
この協業によってフレッシュな乳製品を正確な時間に消費者に届ける配送システムを構築することができるようになりました。
(出典:できたて乳製品の「少量生産・随時配送」のバリューチェーン構築を提携で実現)
株式会社ヘルスケアシステムズ x 花王株式会社
花王株式会社は、日用品からケミカル製品まで幅広い事業を展開する日本の大手化学メーカーです。そんな花王株式会社は、2021年6月にスタートアップ企業であるヘルスケアシステムズとの協業により、⽣活者が⾃宅に居ながら健康状態の把握ができる郵送検査サービスの開発を始めました。
当時、花王株式会社では、ヘルスケア領域における社会課題の解決を目的に「皮膚疾患や脱毛症など我々の近傍領域についても、新たな取り組みを進めていきたい」と新たなアイデアを模索していました。
そこで、郵送検査キットの開発・販売を手掛けるヘルスケアシステムズと協業し、本人さえも気が付かないまま忍び寄る疾患を自宅で見える化できる検査キットの開発を進めています。
株式会社アジラ x セコム株式会社
セコム株式会社は、日本最大手のセキュリティ事業を展開する企業です。そんなセコム株式会社は2022年9月にAI警備システム「アジラ」を開発・販売するスタートアップ企業であるアジラと資本業務提携を結びました。
セコム株式会社とアジラは、定期的に技術部門で情報交換や技術交流を行いながら、ユーザーごとの状況に合わせて、最適なソリューションの提案などを模索しています。
近年、急速に進化を遂げるAIを自社に取り入れるための協業事例と言えるでしょう。
(出典:行動認識AI開発で資本業務提携、セキュリティ分野のAI化など社会実装を目指す)
メディア ブレスト × ANA
ANA(全日本空輸株式会社)は、日本を代表する航空会社であり、国内外の航空事業が主力です。そんなANAは2015年2月にメディアブレストと業務提携し、ANA国際線の機内放映番組を共同で制作・提供しています。
年間700万人を超える旅行客が長時間のフライトを快適に過ごすことができるよう、オリジナルコンテンツを約350種類放映しています。
これまではオリジナル・コンテンツの提供などは難しかったANAが専門分野のスタートアップ企業と協業することで、自社内で運営できるメディアビジネスを展開できた1つの成功事例と言えるでしょう。
(出典:ANA国際線の機内放送番組を共同で制作・提供、オリジナルコンテンツを強化)
スタートアップ企業×大企業の協業を成功させるポイント

スタートアップ企業と大企業の協業を成功させるためのポイントは大きくわけて以下の4つです。
- 自分に合った協業先を慎重に選ぶ
- 明確な目的と戦略を設定し、社内で理解を得る
- 知財戦略と契約内容を事前にすり合わせる
- 経営層のコミットメントを行い、協業の推進体制を整える
それぞれ詳しく解説していきます。
引用:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「我が国のオープンイノベーションの課題・阻害要因・成功要因」
自分に合った協業先を慎重に選ぶ
他社との協業を成功させるためには、自社の社風や技術、目的などにマッチした提携企業を選定することが必要不可欠です。
この協業先選びを誤ってしまうと、どんなに入念にコミュニケーションを取っていても、どんなに高い技術力を持っていても、企業同士がイノベーションを起こしにくくなってしまいます。
もし、協業先選びに不安がある方は以下3つのチェック項目を必ず確認しておきましょう。
- 他社との協業経験があるか?
- 社内全体が他社との協業に積極的か?
- 協業の目的に合った明確な技術力を持っているか?
- 企業の経営状況は安定しているか?
また、実際に企業へ訪問し、お互いの技術力や目的を確認することはもちろん、IR情報や企業ホームページで社風や財務状況などを徹底リサーチしておくことも重要です。
明確な目的と戦略を設定し、社内で理解を得る
他社との協業を行う目的や戦略を定量的に示したうえで社内で理解を得ることも協業を成功させるために重要です。特にクローズドイノベーションが主流だった日本ではスタートアップ企業との協業に後ろ向きな社員も少なくありません。
このように社内の理解を得られないまま他社との協業をスタートさせてしまうと、内部の反発や不安によって協業が失敗に終わるケースも多くあります。
そのため「なぜ他社と組む必要があるのか?」「協業することでどのような利益をもたらすのか?」を具体的な例や数値を使って説明し、社内の理解と協力を得ることが重要です。
知財戦略と契約内容を事前にすり合わせる
他社との協業を行う際には、共同で開発した製品やサービスに関する権利や知財について事前にすり合わせることが重要です。実際に日本の大手企業である「ファーストリテイリング社」は、ITスタートアップ企業と共同開発したセルフレジの特許権を巡る訴訟問題が起きました。
こちらの事例では両者が納得する形で和解したものの、なかには賠償問題にまで発展してしまうケースも存在します。
そのため、かならず他社との協業を行う際には知財や利権に関する細かい契約を両者が納得のいく形で額面に示しておきましょう。
経営層のコミットメントを行い、協業の推進体制を整える
スタートアップ企業と大企業の協業を成功させるためには経営層の協力が必要不可欠です。経営者は、企業の安全や安定を求める傾向が高く、他社との協業に否定的な場合が少なくありません。
経営層とコミットメントができていないまま協業をスタートさせると、少しのトラブルでも共同開発が打ち切りにされてしまうこともあるでしょう。
そのため、必ず現場だけでなく経営層ともコミュニケーションを取り、慎重に協業を進めていくことが重要です。
スタートアップ企業と大企業の協業は革新的なアイデアに繋がる!
今回はスタートアップ企業と大企業の協業についてそれぞれのメリットや成功事例、成功の秘訣を解説してきました。協業は、自社内では生み出せない革新的な製品やサービスを生み出せる可能性を秘めています。
特に流行の移り変わりや消費者の意識の変化が激しい現代の市場では、複数企業による協業によって大きな利益を上げた成功事例も数多く存在します。ぜひ、今回ご紹介した過去の成功事例や協業のポイントをチェックした上で他社との協業を検討してみてください。
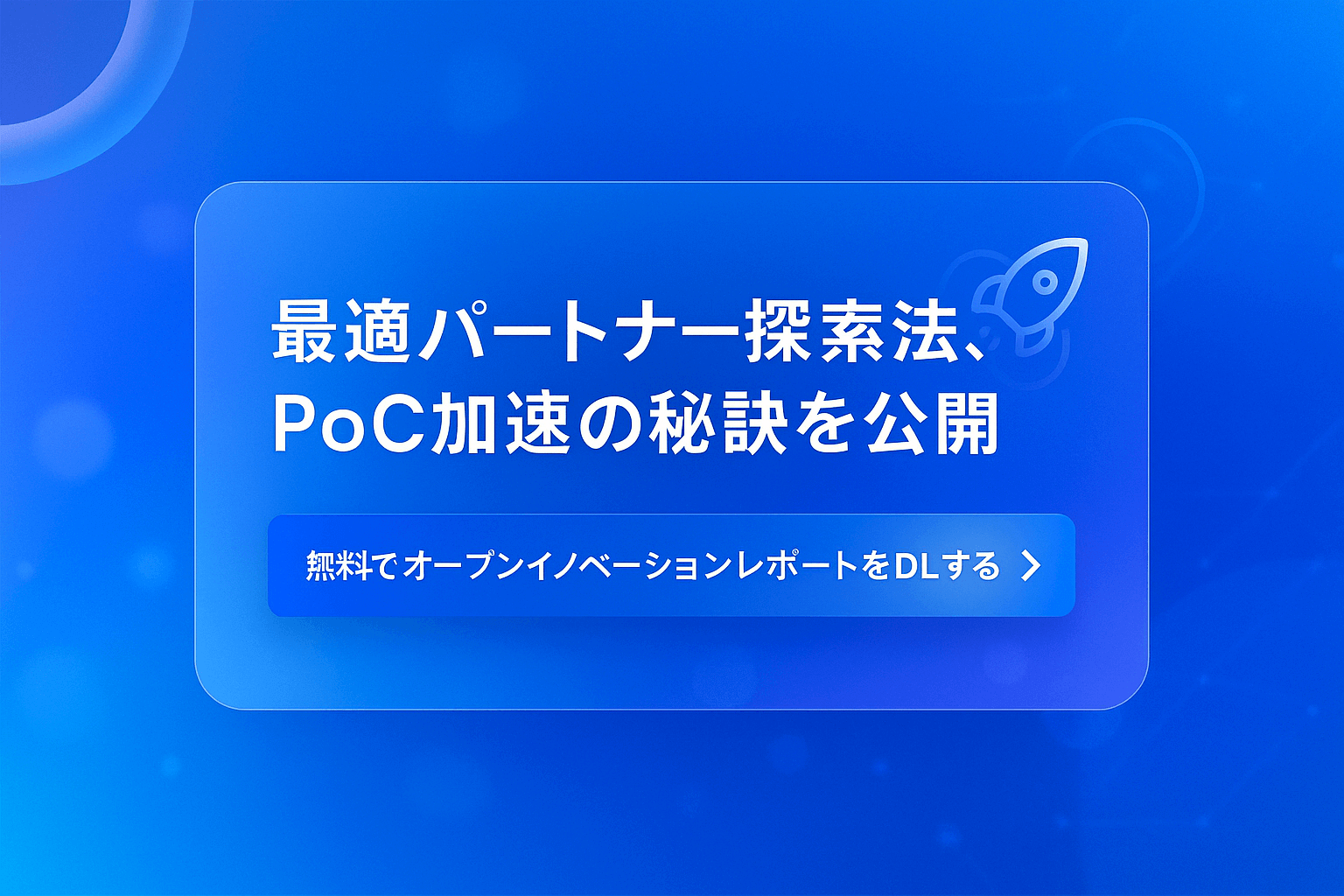
実際のスタートアップ×大企業の協業現場で何が起きているのか生の事例をご覧ください
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
協業を成功に導く具体的なマッチング手法やコミュニケーションのポイント、契約締結までのプロセスを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の協業推進にご活用ください。