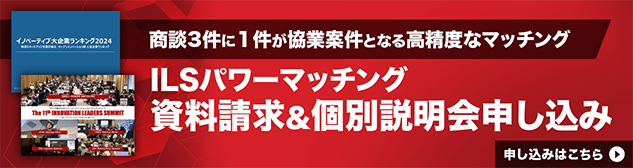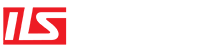ILSが提供してくれるスタートアップのデータベースは、質量とも充実しています。他社のデータだと必ずしもアクティブな情報ばかりではなく、問い合わせると現在はもう稼動していないスタートアップが含まれていたりすることもありました。今後もILSによるスタートアップの「生きた情報」をもとに、当社のニーズにマッチした、相性の合うスタートアップと出会っていきたいと思います。




公開日:2025年6月 / 執筆:ILS事務局
株式会社ダイキアクシスは、2023年12月のILS2023における交流会を機に、子会社のCVCを通して株式会社LIGHTzに出資を決め、2024年3月に資本業務提携を締結。合わせて、ダイキアクシスの総合水処理事業において属人的に暗黙知となっている熟達者の知見・技術を、LIGHTz独自のパーソナルAI化技術を使って形式知化し、次世代への技術継承を進めるプロジェクトを推進している。

1958年創業のダイキアクシスグループでは、総合水処理メーカー、住宅設備製品卸売、再生可能エネルギー関連、家庭用ウォーターサーバーの4つの事業を柱として展開している。さらに「環境を守る。未来を変える。」というミッションのもと、スタートアップとの戦略的シナジーの創出を目指して、2023年5月にCVCの子会社、株式会社Daiki Axis Venture Partnersを設立。そうして実際に、互いのリソースを掛け合わせて事業課題や社会課題の解決に取り組めるスタートアップとの出会いを求めて、2023年12月のILSに初参加した。「当CVCは、親会社のCFOを含めた経営陣が直接運営に当たっているため、投資判断などの意思決定が非常に迅速です。現在までに、LIGHTzを含めた12先に出資していますが、一般的にデューデリジェンスを経て出資決定、着金まで半年程度かかるところ、LIGHTzの場合は2ヵ月で実行しました。出資先には、協業や連携により新たな価値を創出できることを期待しています(井上氏)」

キヤノン出身で、製造業向けコンサルティングのキャリアを持つ乙部氏が2016年に創業した株式会社LIGHTzでは、地方での雇用創出につなげたい思いから、ものづくりの技術・技能の継承をAI化。属人的になりやすい熟達者の複雑な知識・経験・思考を整理したうえで、その言葉からAIを造っていく「BrainModel(ブレインモデル)」を開発しており、若手にも継承しやすいよう「汎知化(はんちか)」するプロジェクトを個社ごとに推進している。ILSにはそのような技術継承の課題を持つ製造業大手が多く参加しているため、2018年より参加。研究開発や製品企画、生産工程などに広く有効なのもあって、多くの大手企業とのマッチングを果たしてきた。2023年12月のILS開催時には、同社はシリーズBラウンドにあり、戦略的に事業会社との資本業務提携を求めていたなか、交流会を機にダイキアクシスより技術継承の現状や課題感などをヒアリング。投資・連携意欲の高かったダイキアクシスと、出資前提でプロジェクトを進めていくことがとんとん拍子に決まった。

2024年1月の投資委員会を受けて出資が決定(着金は3月末)し、資本業務提携を締結。5~6月にはダイキアクシスの本社がある愛媛県で事業部門や工場を視察して、8月にはまず調査フェーズのプロジェクトとして、現場の課題抽出と認識合わせを行った。その結果をふまえ、2025年2月より排水処理施設の設計部門にて本格的にプロジェクトを開始。パーソナルAIを作る前段階となる「汎知化(はんちか)」を行っている。これは要件定義のようなもので、熟達者にヒアリングして言語化されたものを整理してノウハウ記述書と呼ばれる約100枚の資料にまとめ上げる。いわば知識の構造化であり、6月末にこの成果物を納品予定。排水処理施設の設計における技術・技能の難しさは、生活排水や工業排水といった種類など、その領域ごとに細かな勘どころが存在する点にある、微生物を使った処理の計画は有機的なもので、状況に応じた熟達者の判断が重要になる。「非常に、暗黙知の温床にやりやすい業態だと思いました(乙部氏)」
このプロジェクトによるダイキアクシスの一番のメリットは、対応案件数の改善だという。これまでは熟達者でないと対応できなかったような難しい案件を、経験の少ない若手社員でも対応できるようにすることで、現場を停滞させることなく工期短縮に繋げ、売上も向上。さらに、若手が作業ではなく、上流工程を手がけられることで仕事が面白く、やりがいを持ってもらえることで離職対策にもなり、メンバーの士気が上がることが期待できるとのこと。「今後、さらに設計領域を深堀りしていくか、開発や製造・生産などの他部門に広げていくかは、LIGHTzを含めたプロジェクトメンバーと相談しながら進めたいです(井上氏)」

ILSが提供してくれるスタートアップのデータベースは、質量とも充実しています。他社のデータだと必ずしもアクティブな情報ばかりではなく、問い合わせると現在はもう稼動していないスタートアップが含まれていたりすることもありました。今後もILSによるスタートアップの「生きた情報」をもとに、当社のニーズにマッチした、相性の合うスタートアップと出会っていきたいと思います。

設計・製造などの展示会にも出展しますが、そこで名刺を1000枚獲得しても深くヒアリングができなければ良い出会いとはなりにくいもの。それがILSだと大手企業の決定権のある方と、時間をかけて話ができます。マッチング以外でも会期中に会場であいさつできたりしますので、興味を持ってもらえれば、今回のように場を変えてじっくり話したり、後日の動きをとることもしやすいと思います。
ILS 開催概要
第13回・ILS2025 (2025年12月) ・
第12回・ILS2024 (2024年12月) ・
第11回 (2023年12月) ・
第10回 (2022年11月) ・
第9回 (2022年2月) ・
第8回 (2021年) ・
第7回 (2019年) ・
第6回 (2018年) ・
第5回 (2017年) ・
第4回 (2016年) ・
第3回 (2015年)・
第2回 (2014年)
新事業創造カンファレンスレポート
第6回 (2018年)・
第5回 (2017年)・
第4回 (2016年) ・
第3回 (2015年) ・
第2回 (2014年) ・
第1回 (2014年)