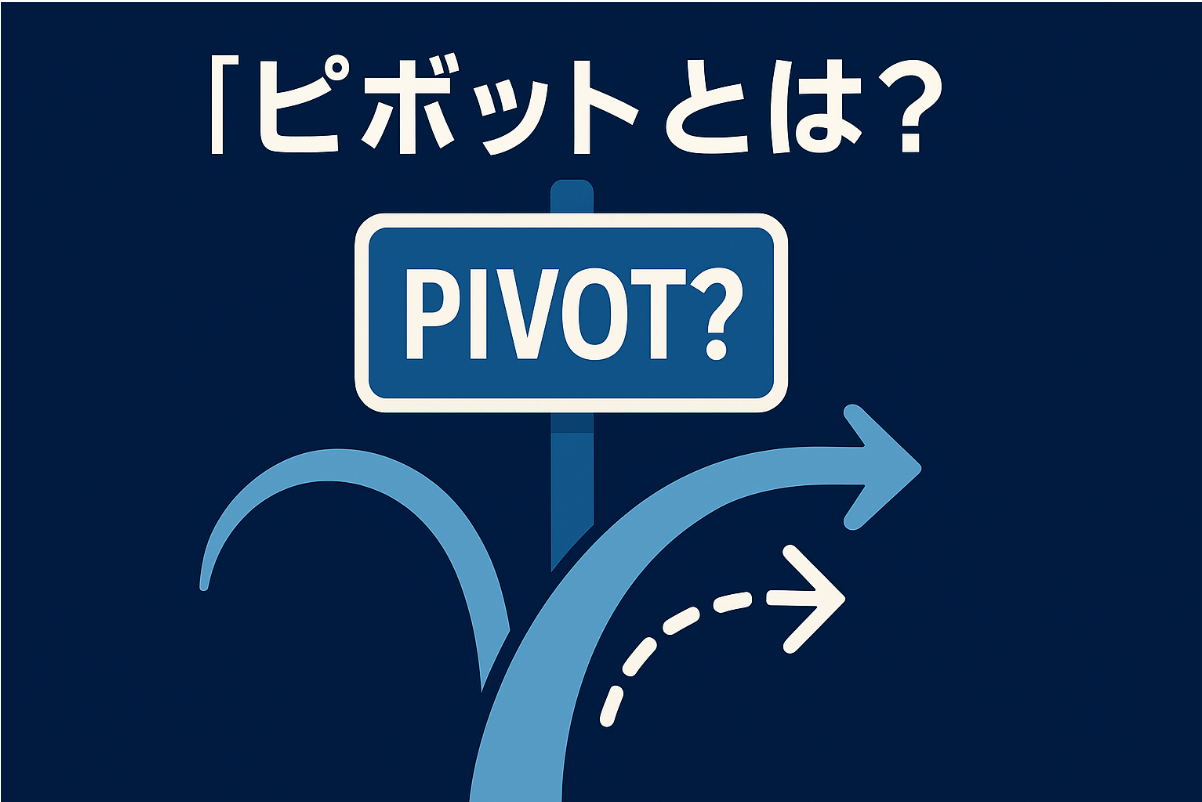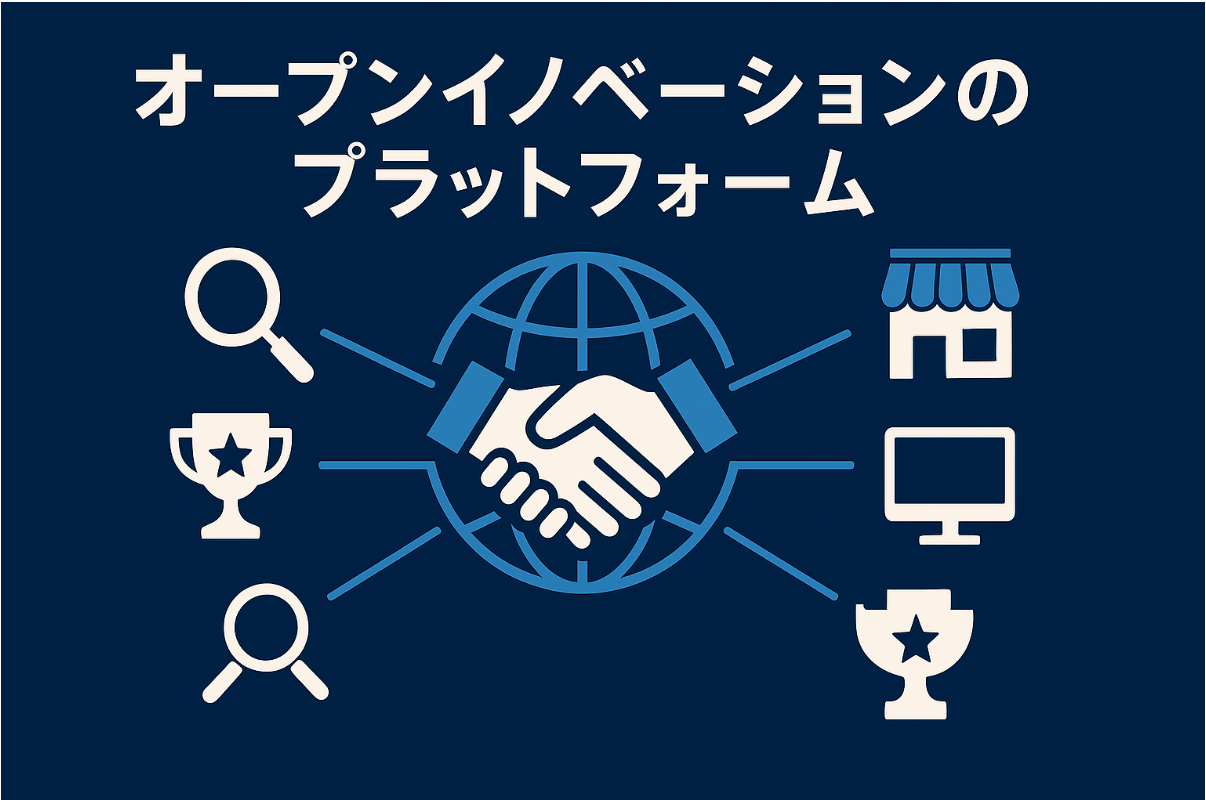新規事業に取り組むと、多くの悩みがでてきます。しかし、そうした迷いや行き詰まりは、前に進もうとしている証でもあります。
そこで今回は、新規事業において特に多くの人が直面する課題とその背景を掘り下げ、悩みを乗り越えるための視点や実践的なヒントを紹介していきます。また、実際に失敗を乗り越えて成長を遂げた企業の事例も取り上げており、自身の取り組みと重ねながら読み進められる内容です。「悩んでいる=止まるべき」ではなく、「悩んでいる=見直すタイミング」として活用することで、新たな突破口が見えてくるはずです。今まさに新規事業で壁にぶつかっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
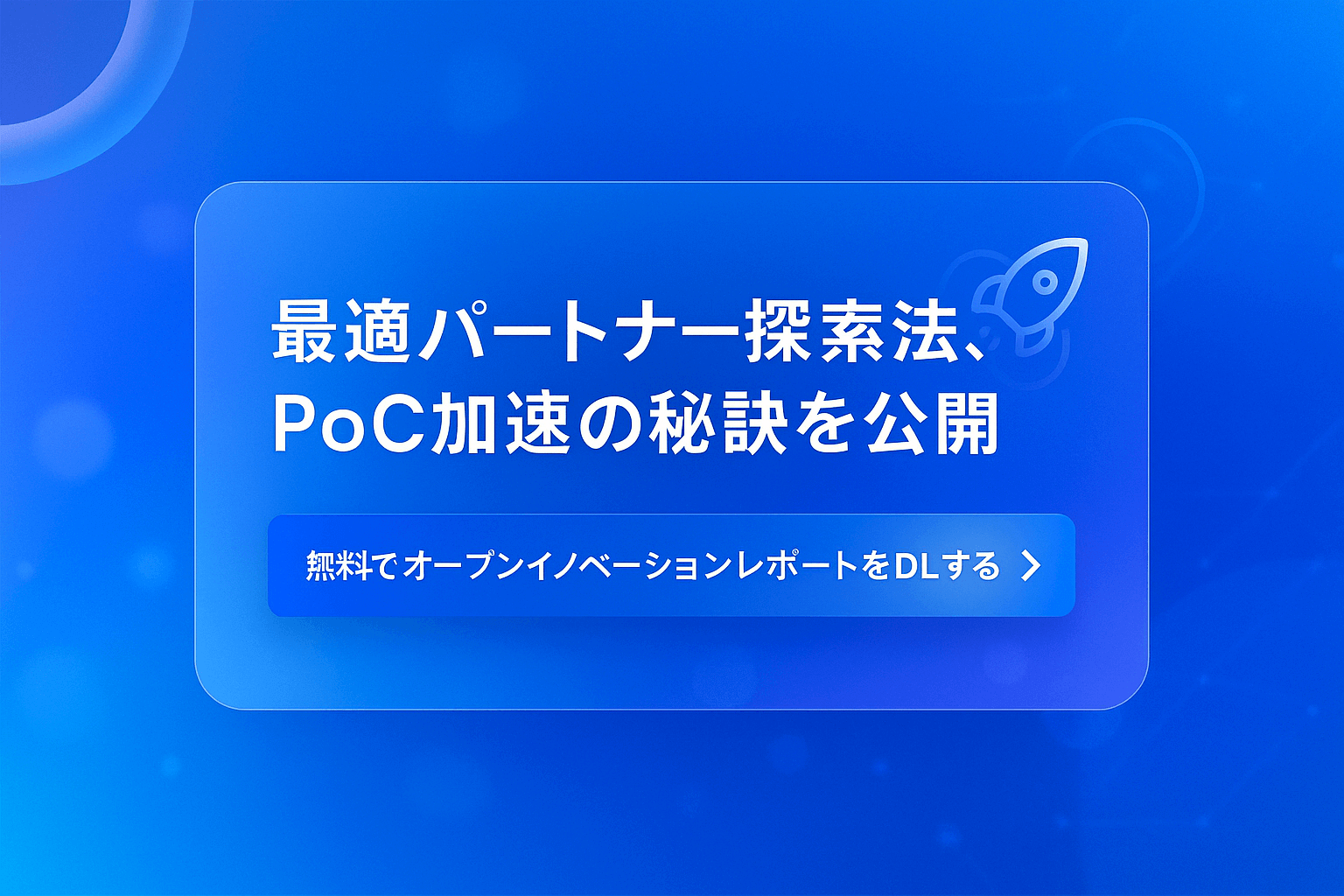
新規事業の悩みは一人で抱え込まず外部連携で解決する企業が増えています
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
新規事業でつまずきがちな壁を外部連携で乗り越える具体的な手法や成功事例を豊富に扱っているので、ぜひ貴社の新規事業推進にご活用ください。
新規事業で多くの人が感じる悩みとは?
新規事業に挑むとき、多くの人が最初にぶつかるのは「正解のない世界」に対する戸惑いです。どこから着手すべきか、誰に協力を仰げばよいか、市場に受け入れられるのか、不安の種は尽きません。責任の重圧や判断の迷いも重なり、足が止まってしまうこともあるでしょう。ここでは、そうした悩みの具体例とその背景をひも解きながら、突破口を見つけるヒントを紹介します。
新規事業の課題と解決方法については詳細を以下で解説しておりますので合わせてご覧ください。
フェーズ別にわかる新規事業の課題と解決フレームワークを解説
何から手をつければいいかわからない
新規事業を任されたものの、何から手をつければよいのかわからず、足が止まってしまう。これは多くの担当者が最初に直面する悩みです。
新規事業には決まった正解や手順が存在せず、会社の方針や置かれた状況によって、取るべきアプローチも変わってきます。とはいえ、最初の一歩としては「下地づくり」から始めるのが一般的です。
具体的には、リサーチや情報収集、ビジョンの整理といった準備工程にしっかり時間をかけることが重要です。焦ってアイデアをひねり出そうとする前に、自社の強み、市場の動向、顧客の課題などを多角的に把握しましょう。
プロジェクトの土台が整えば、進むべき方向性は自然と見えてくるはずです。
社内の理解や協力が得られない
新規事業を進める際、「社内の理解や協力が得られない」と感じる場面は少なくありません。特に既存事業を重視する組織では、新規事業の優先度が相対的に低く、周囲との温度差が発生しがちです。
さらに、前例のない取り組みに対しては「失敗を避けたい」という心理が働き、積極的な支援を得ることが難しくなる傾向もあります。こうした状況を打開するには、自身のアイデアがもたらす価値を丁寧に伝えることが大切です。
相手の課題や立場を理解したうえで、粘り強く対話を重ねる姿勢が信頼関係の構築につながります。熱意と当事者意識を持ち続けることで、少しずつでも協力者を増やしていくことができるはずです。
市場ニーズとのズレが怖い
新規事業でよくある不安の1つが、「市場ニーズとズレているのではないか」という懸念です。どれだけアイデアを形にしても、顧客の求めるものと一致していなければ支持は得られず、やがて失敗につながります。
特に、自社の技術や発想を起点とした企画では、「売りたいもの」を優先してしまう傾向があります。けれども、本当に重視すべきなのは、「顧客が必要としているかどうか」という視点です。
ズレを防ぐには、徹底した市場調査と明確なペルソナ設定が求められます。さらに、テストマーケティングによる仮説検証を重ねることで、アイデアの実効性を確かめることが可能です。
まずは小さく始め、顧客の反応を見ながら柔軟に軌道修正していく。この積み重ねが、確かな手応えを得る近道となります。
ピボットすべきか撤退すべきか判断できない
新規事業を進めるなかで、ピボット(方向転換)を繰り返しても成果が見えず、「続けるべきか、撤退すべきか」と判断に迷う場面は珍しくありません。仮説検証が思うような結果につながらなくても、打ち手を変えれば再挑戦できるため、明確な線引きが難しくなりがちです。
こうした局面では、あらかじめピボットの回数の上限やKPIを設定しておくことに加え、起案者自身の熱量も重要な判断材料になります。ピボットを重ねる中で「前に進めていない」と感じたなら、撤退は決して後ろ向きな選択ではありません。
感情に左右されず、冷静にリソース配分と成果のバランスを見直すこと。それが、健全な事業判断を下すための第一歩です。
新規事業のピボットについては以下で詳細を解説していますので合わせてご覧ください。
新規事業の「ピボット」とは?成功の分かれ道になる判断と実行のポイントを徹底解説!
責任の重さに押しつぶされそうになる
新規事業の担当者にとって、「すべての判断が自分にかかっている」という感覚は、想像以上に大きなプレッシャーになります。企画立案から検証、実行、社内調整まで広範な責任を負う立場では、心身が疲弊し、決断の重みに押しつぶされそうになることもあるでしょう。
特に初めての挑戦では、「失敗すれば信用を失うのでは」といった不安から、判断が鈍る場面も少なくありません。
このような状況を乗り越えるには、すべてを一人で抱え込まないことが大切です。タスクの優先順位を明確にし、信頼できるメンバーに役割を委ねることで、負担が分散され、精神的な余裕も生まれます。さらに、定期的な振り返りを行い、課題と成果を可視化することで、過剰な自己責任感を和らげる効果も期待できます。
重圧は責任感の裏返しです。正面から向き合いつつも、冷静に状況を整理することで、次の一歩を踏み出す力が備わっていきます。
新規事業の悩みが起こる主なタイミングと原因
新規事業の悩みは、思いついた瞬間から始まっているともいえます。立ち上げ初期の構想段階から、社内提案や検証フェーズ、さらにはローンチ後に至るまで、それぞれの局面で異なる課題が立ちはだかります。なぜそのタイミングで悩みが生じやすいのかについて、解説していきます。
立ち上げ初期(構想・企画)フェーズの壁
新規事業の立ち上げ初期では、「何を起点に発想すればよいのか」「どこまでの情報を揃えるべきか」といった手探りの状態に戸惑うことが少なくありません。アイデア創出の段階では正解が見えづらく、ゼロから一を生み出す負荷の大きさに不安を感じる担当者も多いものです。
特に、自分の仮説や着想に確信が持てないまま社内調整が進んでしまうと、「そもそも価値があるのか?」という迷いが膨らみ、手が止まってしまうこともあります。このような状況を打開するためには、自社の強みや市場環境を踏まえたうえで、仮説を言語化・可視化することが大切です。
さらに、ワークショップやオーディション形式の場で他者と意見を交わすことで、新たな視点を得ながらアイデアの精度を高めることができます。初期の構想段階こそ、焦らずに探索と検証を繰り返す姿勢が求められます。
検証・PoC(実験)フェーズのつまずき
新規事業におけるPoC(概念実証)フェーズは、「実現可能か」「顧客にとって価値があるか」「事業として成立し得るか」を見極める重要なステップです。
しかし、ここでつまずくケースも少なくありません。例えば、検証の目的が曖昧なまま進めてしまい、PoCの結果が判断材料として活かせず、いわゆる“PoC貧乏”に陥ることがあります。また、必要以上の完成度を求めて開発に時間やコストをかけすぎる「豪華客船型PoC」も、失敗の一因となりがちです。
この段階では、あくまで仮説の検証に徹することが重要です。簡易なプロトタイプやユーザーヒアリングを活用し、スモールスタートで実証を行うのが理想的です。
社内提案・意思決定の通し方に悩む
新規事業を社内で提案する際、多くの担当者が「どうすれば意思決定までたどり着けるのか」と悩みを抱きがちです。特に、経営陣や他部署を巻き込む必要がある場合は、資料の構成や提示のタイミング、根拠の示し方1つで可否が左右されるため、精神的な負荷も大きくなります。
さらに、既存事業との優先順位やリスクを懸念する声が先行し、斬新なアイデアほど「通りづらい(受け入れられない)」という現実に直面することも少なくありません。
こうした壁を乗り越えるには、提案内容に客観的なデータを添えて信頼性を高めると同時に、相手の関心や課題に寄り添ったストーリー設計が重要です。
加えて、提案前にキーパーソンへ事前説明を行う“根回し”も有効な手段です。社内の合意形成は一度きりのプレゼンで決まるものではなく、丁寧な準備と対話の積み重ねが成功へのカギとなります。
ローンチ後の手応えがない
新規事業をようやくリリースしたものの、期待していたような反響が得られず、「このままで本当にいいのか」と迷いが生じることもあります。こうした悩みは、ローンチを“ゴール”と捉えてしまったときに起こりやすく、リリース後も仮説の検証と改善を重ねていく姿勢が大切です。
特に顧客との対話を怠ると、ニーズとのズレに気づけず、市場からの無反応に戸惑うばかりになってしまいます。ローンチはあくまでスタート地点。実際のユーザーの声に耳を傾け、どこが響いていないのかを見極めることで、提供価値を再構築するチャンスと考えましょう。
また、「何をやったか」ではなく「何がわかったか」という視点で振り返りを行うことが重要です。社内外で共通の理解や信頼関係を育むことで、次に取るべき行動が見えてきます。手応えのなさは失敗ではなく、改善への出発点なのです。
悩みを乗り越えるために知っておきたい4つの視点
新規事業において直面する悩みや不安は、誰にとっても避けがたいものです。しかし、行き詰まりを感じたときこそ、視点を変えることが突破口になることがあります。ここでは、悩みを前進に変えるために知っておきたい4つの視点をご紹介します。
「正解を探す」より「仮説を動かす」マインドセット
「正解を探す」という姿勢は、新規事業においてはかえって足かせになることがあります。ビジネスの世界には、そもそも唯一の正解など存在しないからです。不確実な状況下では、完璧な答えを求めるよりも、「仮説を立てて試す」姿勢が求められます。
たとえ小さなアイデアでも、検証を繰り返すことで顧客の反応や市場の兆しが見えてきます。重要なのは、実験と学習のサイクルを止めないこと。失敗したとしても、それは「誤った正解」ではなく「次につながる学び」として蓄積されます。
まずは一歩踏み出し、仮説を行動に移すこと。その勇気こそが、新規事業を前進させる突破口となります。
「小さく始める」ことで見える世界がある
新規事業は「大きなビジョンを掲げて始めるべき」と考えるあまり、かえって動けなくなる人も少なくありません。しかし実際は、「小さく始める」ことこそが突破口になるケースが多く見られます。
重要なのは、完璧を目指すことよりも、まず動き出すこと。小さな実験から得られるフィードバックは想像以上に多く、次の一手を考える手がかりになります。たとえ失敗したとしても、その経験は次の挑戦に活きる貴重な糧になるでしょう。
大きく構えるよりも、できることから始めてみる。その一歩が、事業の可能性を切り開く起点となるのです。
「社外」の視点を取り入れるという選択肢

新規事業を進めるうえで「社外の視点」を取り入れることは、視野を広げるうえで効果的です。社内の枠組みにとどまっていると、アイデアが似通ったり、意思決定に偏りが生じたりすることもあります。
そうした状況では、外部の専門家や支援機関、あるいはスタートアップとの共創が、新たな知見や気づきをもたらしてくれることもあるでしょう。特に仮説検証や市場調査といった初期フェーズでは、リサーチ会社や外部パートナーの協力を得ることで、スピードと精度の両立が図れます。
さらに、社外からの客観的なフィードバックは、社内では見落としやすい課題の発見にもつながります。内と外のバランスを意識することで、柔軟かつ実行力のある事業開発が可能になるのです。
新規事業の悩みは一人で抱え込まず外部連携で解決する企業が増えています
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
新規事業でつまずきがちな壁を外部連携で乗り越える具体的な手法や成功事例を豊富に扱っているので、ぜひ貴社の新規事業推進にご活用ください。
「やめる勇気」も立派な選択肢
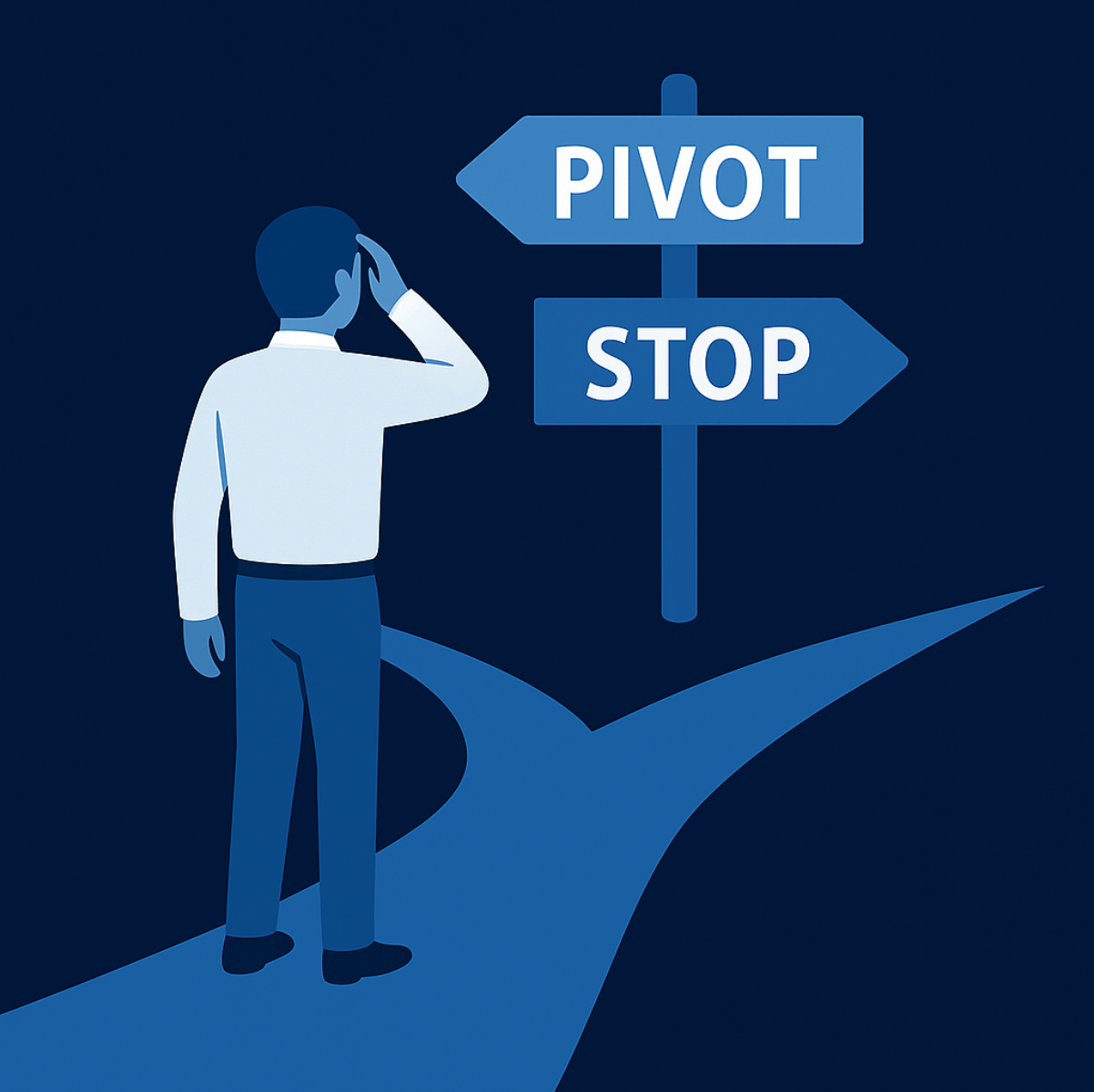
新規事業に取り組んでいると、「続けることこそが正解だ」と思い込んでしまうことがあります。しかし、成果が見えず、心身に負担がかかっている状況では、「やめる(撤退)」という選択も立派な判断です。
残り続けるには執着だけで足りますが、やめるには覚悟と勇気が求められます。そんなときは、一度立ち止まり、「今の自分なら、この事業をもう一度選ぶだろうか?」と自問してみるとよいでしょう。環境や自分の気持ちを見つめ直すことが、的確な判断につながります。
また、撤退は単なる終了ではなく、未来のためにリソースを再配分するという前向きな意味もあります。例えば、NetflixはDVDレンタル事業からの撤退を機にストリーミングへと大きく舵を切り、世界的な成功を収めました。カシオもスマートフォンの台頭を受け、デジタルカメラ事業からの撤退を決断し、電子楽器や時計といった成長分野へ集中したことで業績を立て直しました。このように、時代の変化に合わせて大胆に方向転換した企業は、新たな価値を創出し続けています。
撤退は失敗ではなく、新たな選択の始まり。自分自身とこれからの可能性を信じ、前向きな決断を下す勇気を持ちましょう。
新規事業の悩みを抱える人にこそおすすめしたいサポートと仕組み
新規事業を進める中で生じる悩みや不安は、決して個人の資質だけに起因するものではありません。むしろ、周囲の理解や支援の有無によって、大きく左右されるケースが多くあります。こうした状況を乗り越えるには、適切なサポート体制や外部の仕組みを上手に活用することが重要です。ここでは、孤立せずに前に進むために役立つ支援の形を紹介します。
社内でのメンターや伴走者を見つける
新規事業に取り組む中で、孤独や不安に押しつぶされそうになる瞬間は少なくありません。そんなとき、心強い存在となるのが社内のメンターや伴走者です。
メンターは単なる助言者ではなく、自身の経験や視点を共有しながら、担当者の自発的な行動を引き出してくれる存在です。一方、伴走者は「ともに考え、ともに動く」存在です。課題の壁に直面したときに冷静な視点で状況を整理し、精神的な支えにもなってくれます。特に初めての挑戦では、成功や失敗の基準が曖昧になりがちですが、こうした存在がいることで判断の軸が定まりやすくなります。
社内で信頼できる先輩や、異なる部署の仲間を巻き込み、定期的に対話する仕組みを整えること。それが、新規事業を健全に進め、着実に成長させる土台となるでしょう。新規事業は一人で進めるものではなく、信頼できる誰かと共に歩むことで、前に進む力が生まれます。
社外リソース(支援機関・VC・アクセラレーター)の活用
新規事業に取り組む中で、社内リソースだけでは限界を感じる場面もあるでしょう。そんなとき、有効な手段となるのが「社外リソース」の活用です。
例えば、ベンチャーキャピタル(VC)による資金支援に加え、アクセラレーター(※)や支援機関が提供する伴走型プログラムに参加することで、専門的なノウハウや人的ネットワークを得ることができます。実際に、京都アクセラレーションプログラム(KAP)では、起業経験者がバーチャルCEOとして支援に加わり、わずか3ヶ月で投資判断を受けられる水準まで事業案を磨き上げる取り組みが行われています。
このように、外部の知見を取り入れることで、スピード感のある仮説検証や市場適応が可能になり、社内だけでは得られない視点や判断軸にも触れられます。事業の成長に必要な要素を的確に補完するためにも、社外との積極的な連携も重要です。
(※)スタートアップや起業家に伴走し、事業成長を助けるパートナーのこと
相談しやすいコミュニティやイベントに参加する
新規事業に取り組む中で、孤独や不安を感じる瞬間は誰にでも訪れるものです。そんなときに心の支えとなるのが、起業家コミュニティやビジネス系イベントへの参加です。
こうした場では、メンターに相談できる機会が得られるほか、同じ志を持つ仲間と出会えるため、有益な情報や励ましを受けることができます。実際、起業後の成長を目指す人ほど積極的にコミュニティに参加する傾向があり、それが成長スピードの差にもつながっています。
さらに、イベントやワークショップでは、新たなアイデアや市場ニーズへの気づきを得られることもあります。無料かどうかにとらわれず、自分に合った風通しのよいコミュニティを選ぶことが、継続的な学びや人脈形成につながるポイントです。
悩みを抱え込まず、社外との交流からヒントを得る姿勢こそが、新規事業を前進させる大切な一歩となります。
新規事業の失敗や悩みを成長の糧にした事例紹介
新規事業の道のりは、必ずしも順風満帆とは限りません。むしろ、数々の失敗や迷いを経験しながら、その先に成長を掴んだ企業こそが持続的な進化を遂げています。ここでは、困難を乗り越えた企業の事例を紹介しながら、悩みや挫折を“学び”に変えるヒントを探っていきます。
Dropbox|3回のピボットを経てクラウドストレージの巨人に成長
Dropboxは、サービス本体が存在しない開発初期の段階で、1本の紹介動画を用いた“スモークテスト型MVP”によって市場の反応を検証しました。創業者のドリュー・ハウストン氏は、自らの課題とその解決策を描いたユーモアあふれる動画を投稿し、わずか一晩で、登録希望者は5,000人から75,000人へと急増しました。
この結果を手応えとし、プロダクトの開発を本格的にスタート。3度にわたるピボットを重ねながら、提供価値を徐々に磨き上げていきます。現在では、世界中で6億人を超えるユーザーに利用されるサービスへと成長を遂げました。
仮説をもとに素早く検証し、必要に応じて方向転換する柔軟な姿勢こそが、Dropbox成功の原動力といえるでしょう。
サイボウズ|社内ベンチャー制度を活用し新規事業を成長させた事例
サイボウズは、自社の社内ベンチャー制度を活用し、新規事業「Cybozu for Challengers(通称サイチャレ)」を立ち上げました。このプログラムでは、スタートアップや事業承継者を対象に、「kintone」を活用した業務改善支援をはじめ、チームビルディング研修やコミュニティ形成の機会などを、1年間にわたって提供します。
参加企業は、社内外からの支援を受けながら、トライアル形式で実践的にビジネス課題に取り組み、事業基盤の強化を図ります。背景には、「ツールを導入しても活用できない」「相談相手がいない」といった中小企業特有の課題を、ツールと人的サポートの両面から解決したいという想いがあります。
試行錯誤を重ねて形づくられたこの取り組みは、理念を軸に事業成長を目指す好例といえるでしょう。
メルカリ|ユーザーニーズに合わせてサービス方向を見直し急成長したフリマアプリ
フリマアプリ「メルカリ」は、サービス初期から市場ニーズとのズレに直面しながらも、柔軟に方向転換を重ね、急成長を遂げた代表的な事例です。当初は不要品の売買を中心に展開していましたが、利用者の声をもとに「匿名配送」や「簡単出品」「エスクロー決済」などを導入し、誰もが安心して簡単に取引できる環境を整えてきました。
その後も、「メルカリShops」や「メルカリ ハロ」など新たなサービスを次々に展開。直近では「時間やスキルの循環」をテーマにしたHR領域にも進出し、モノの売買にとどまらないプラットフォームへと進化しています。こうした柔軟な姿勢と、試行錯誤を恐れない企業文化こそが、メルカリの成長を支える原動力となっています。
新規事業の悩みを抱えたときに立ち止まって考えたいこと
新規事業に取り組む中で、行き詰まりや迷いを感じる瞬間は誰にでも訪れます。「このまま進んでよいのか」「やめるべきか」などの悩みが膨らんだときこそ、一度立ち止まって状況を見直すことが重要です。ここでは、そんな不安を抱えたときにこそ考えておきたい3つの視点を紹介します。
その悩み、本当に一人で抱える必要はある?
新規事業に取り組む中で、悩みを「自分だけの問題」として抱え込んでしまう人は少なくありません。しかし、その重圧をすべて一人で背負い続ける必要はあるのでしょうか。
立場上、責任感が先行しやすい場面ではありますが、周囲を頼ることで視野が広がり、冷静に判断できるようになります。例えば、社内の信頼できるメンターや他部署の仲間に相談するだけでも、精神的な負担はぐっと軽くなるはずです。
また、社外の起業家コミュニティやイベントに参加することで、共通の悩みを抱える仲間と出会えることもあります。孤独を感じたときこそ、誰かと話すことが重要です。悩みを共有できる相手の存在は、新規事業を続けるうえで大きな支えとなるでしょう。
「やる/やらない」以外の第三の選択肢を探す
新規事業に取り組む際、「やるか・やらないか」の二択にとらわれてしまうことは少なくありません。しかし、その間にある“第三の選択肢”に目を向けることで、見落としていた可能性が開けることもあります。
例えば、「一部だけ小規模に試す」「他社と連携してリスクを分散する」「副業的に始めて反応を見る」など、多様な中間的アプローチが考えられます。
「やるか・やらないか」といった極端な判断にすぐ結びつけるのではなく、自分の想いや会社の現実に即した“緩やかな踏み出し方”を探ることも1つの手です。焦らず、今の状況に合った柔軟な進め方を見つけることで、より納得のいく意思決定につながるはずです。
「原点に立ち返る」ことで見えてくるもの
新規事業で行き詰まりを感じたときこそ、一度立ち止まり、自社の「原点」に立ち返ってみることが大きなヒントになります。なぜこの事業を始めようと考えたのか。誰の、どのような課題を解決したかったのか。こうした問いをあらためて自分に投げかけることで、忘れていた使命感や価値観が浮かび上がってくることがあります。
特に、短期的な成果を追うあまり、施策の方向性がぶれやすくなっている場面では、「存在意義」という土台に立ち戻ることが、判断の軸を取り戻す助けになります。
また、原点に立ち返る姿勢は、社員の意識を1つにまとめ、顧客との信頼関係を強化するうえでも効果的です。過去の理念を再確認し、それを今の現場にどう活かすかを考えることで、軸のぶれない持続的な成長につながっていきます。
変化の激しい時代だからこそ、足元を見つめ直すことが、次の一歩を確かなものにしてくれるのです。
悩みは前に進むためのサイン。新規事業を止める前にできることを考えよう!
新規事業には悩みがつきものです。立ち上げ初期の不安や、社内調整の壁、市場ニーズとのズレへの懸念など、乗り越えるべき課題は多岐にわたります。しかし、それらの悩みは、むしろ前進のサインともいえます。「正解探し」から「仮説検証」への転換や、小さく始める勇気、社外との連携活用など、多角的なアプローチが新たな突破口を開きます。事業を止める前にこそ、一度立ち止まり、今できることを冷静に見つめ直してみてください。
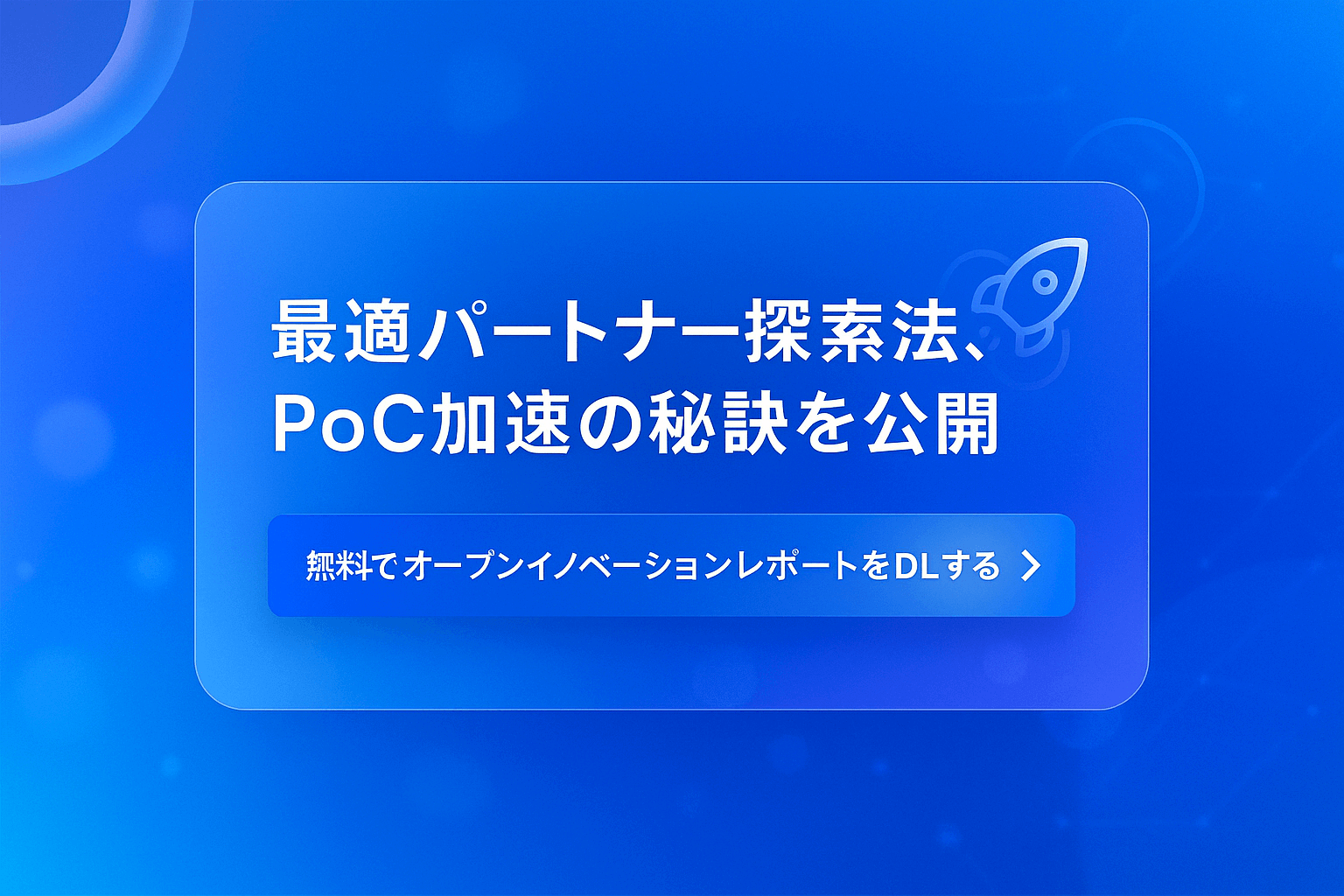
新規事業の悩みは一人で抱え込まず外部連携で解決する企業が増えています
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
新規事業でつまずきがちな壁を外部連携で乗り越える具体的な手法や成功事例を豊富に扱っているので、ぜひ貴社の新規事業推進にご活用ください。