スタートアップの成長に欠かせない存在、それがベンチャーキャピタル(VC)です。
資金調達によってスタートアップなどの事業の成長を加速させるだけでなく、その成長を支えるネットワークやノウハウの提供も大きな魅力といえます。
しかし、VCの仕組みや活用方法は専門的で分かりにくく、「そもそもVCとは何か?」「どんな種類があるのか?」「出資を受けるメリット・デメリットは?」と疑問を抱く方も多いでしょう。
本記事では、VCの基本構造から種類、資金調達の流れ、国内外の代表的なVC、成功事例までを網羅的に解説します。
初めての資金調達に挑む方も、自社に最適なVC活用法を見つけられるはずですので、ぜひ参考にしてみてください。
成長フェーズのスタートアップとの協業チャンスを見つけませんか?
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
VCから投資を受けて成長段階にあるスタートアップとの具体的な連携方法や協業のポイントを豊富に扱っているので、ぜひ貴社のオープンイノベーション推進にご活用ください。
VC(ベンチャーキャピタル)とは?仕組みと基本構造を理解しよう
スタートアップの成長には、大きな資金と専門的な支援が必要不可欠です。
VCは、そうした企業を資金面・経営面から後押しする存在として注目されています。
しかし、VCがどのような仕組みで投資を行い、他の投資家とどう異なるのかは、初めて資金調達を検討する方には分かりづらい部分も多いでしょう。
ここでは、VCの基本的な仕組みと他の投資家との違いを整理して解説します。
VCの定義
VCとは、成長が期待されるスタートアップやベンチャー企業に対し、株式などの形で資金を投資し、企業の成長後に株式の売却(エグジット)を通じて利益を得る投資家や投資機関のことを指します。
単に資金を出すだけでなく、経営の助言やネットワークの提供など、非財務面での支援も行うのが特徴です。
VCにおける投資の仕組み
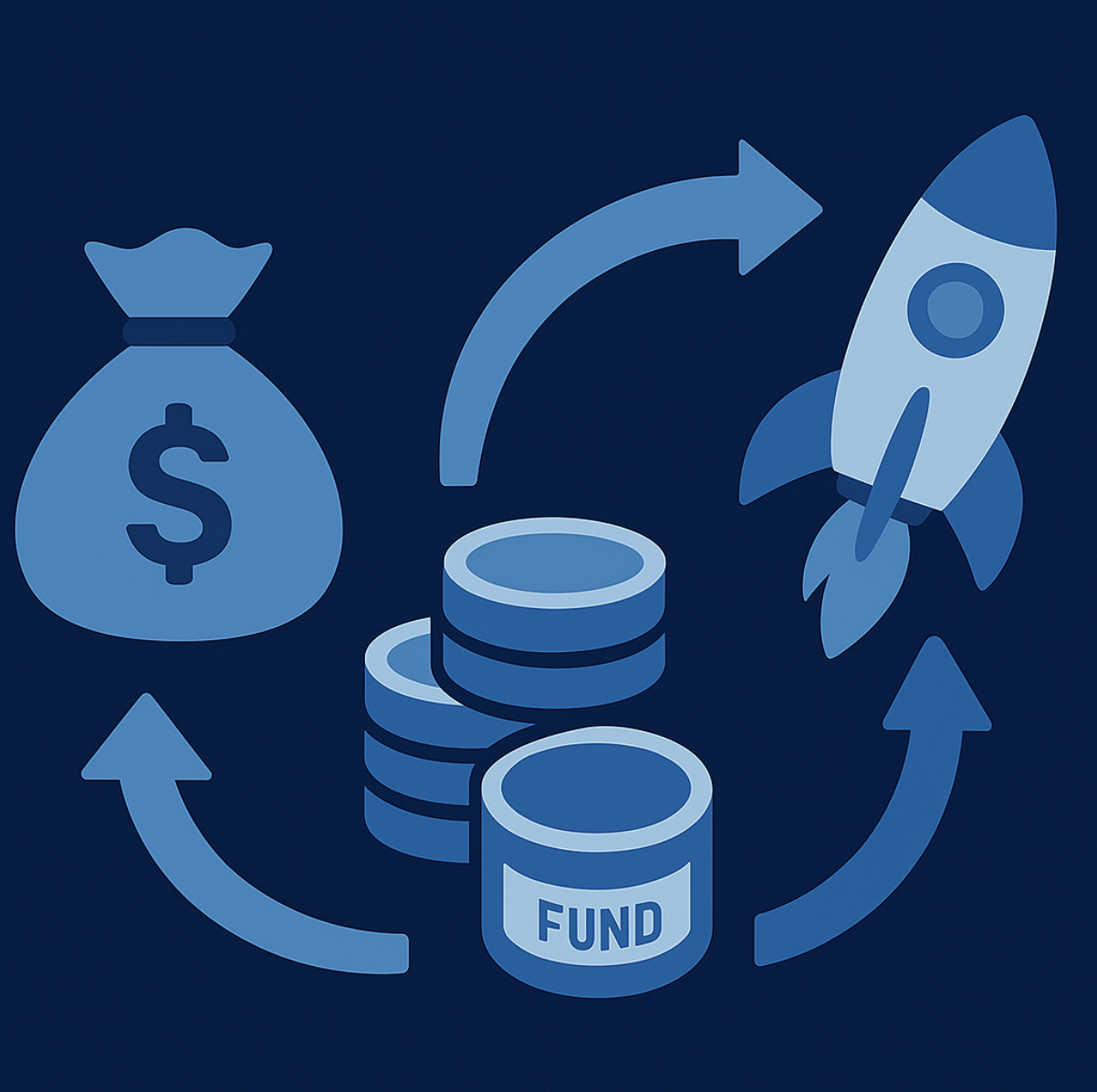
VCの投資は「ファンド」を通じて行われます。ファンドには、年金基金や金融機関、大企業などの機関投資家が出資し、VCがその資金を集めて運用します。
投資先のスタートアップがIPO(新規株式公開)やM&A(企業・事業の合併や買収)で成功すれば、株式の売却益を投資家に分配し、VC自身も運用報酬を得る仕組みです。
これによりハイリスク・ハイリターンの投資を可能にしているのが、VCの大きな特徴でもあります。
「エンジェル投資家」「PE」との違い
VCと混同されやすいものとして、「エンジェル投資家」や「PE(プライベート・エクイティ)」が挙げられます。
エンジェル投資家は、個人が自己資金を投資するケースが多く、投資額はVCより小規模で、創業初期の支援に特化することが一般的です。
また、PEは、主に成熟企業を対象に買収や再生を手掛け、大規模な資金を投入する点がVCとは大きく異なります。
いずれも、スタートアップ期から成長期の企業にリスクマネーを供給する存在であるVCとは似て非なるものであり、その違いをよく理解しておくことはVC活用の準備として必要です。
VCの主な種類
VCとひとくちに言っても、その出資元や運営方針によってさまざまな種類があります。
出資の目的や得られる支援内容はVCの性格によって異なるため、自社に合うVCを見極めることが資金調達の成功につながります。
ここでは、代表的なVCの種類を整理して紹介します。
金融機関系VC
金融機関系VCは、銀行や証券会社などの金融機関が母体となるVCです。
財務面での信用力が高く、豊富なネットワークを活かした資金調達支援が期待できますが、投資基準が比較的厳しめな傾向があります。
大学系VC
大学系VCは、大学や研究機関が出資するVCです。
技術系スタートアップや大学発ベンチャーの支援を得意とし、アカデミックな知見や研究者とのネットワークを活かせる点が強みです。
政府系VC
政府系VCは、国や自治体が出資する公的VCです。
経済活性化や地域振興など政策目的が背景にあり、リスクが高い分野への投資も積極的です。
また、補助金や助成金との併用も視野に入れられることも大きなメリットです。
事業会社系VC
事業会社系VCは、大手企業が本業とのシナジーを狙って運営するVCです。
出資だけでなく、事業提携や販路拡大の支援が期待できますが、出資先に自社との関係性を強く求めるケースもあります。
独立系VC
独立系VCは、特定の親会社を持たず、投資のみを専門とするVCです。
投資判断のスピードや柔軟性が高く、幅広い分野のスタートアップへの投資を行います。複数のファンドを並行して運用する場合もあります。
地域特化型VC
地域特化型VCは、地域経済の活性化を目的に、特定エリアのスタートアップへ投資するVCです。
地域金融機関や地元企業が出資者となっていることが多く、地方発のベンチャーにとって心強い存在です。
海外系VC
海外系VCは、海外の投資家が運営するVCです。
世界展開を視野に入れたスタートアップにとって有力な資金調達先といえます。
海外市場への進出支援やグローバルネットワークの活用が大きな魅力ですが、英語対応や国際的な契約条件に注意が必要です。
VCから出資を受けるメリット

VCからの出資には、単なる資金調達手段ではなく、スタートアップの成長を後押しする多くの利点があります。
ただし、その恩恵を最大限活かすためには、自社のステージや課題に合ったVCを選び、関係を築いていくことが重要です。
ここでは、VC出資を受けることで得られる主なメリットを解説しますので、VCの魅力を理解するとともに、自社に合ったVC選びに役立ててみましょう。
担保や返済という概念がない
VCが提供する資金は、融資ではなく株式出資という形で供給されるため、銀行融資のように返済義務や担保設定が発生しません。
そのため、スタートアップにとっては、資金繰りの負担を大きく軽減できる点が大きな魅力です。
また、事業が軌道に乗る前の赤字フェーズでも、将来の成長可能性を評価して資金を投入してもらえるため、資金調達のハードルが下がるという側面もあります。
ネットワークの拡大と成長速度の向上
VCは、出資先企業同士のネットワークや、提携先となる大企業、業界のキーパーソンなどとのつながりを持っています。
これらの繋がりを活かすことで、スタートアップ単独では難しい販路開拓や大手企業との協業、海外進出などが現実味を帯びてきます。
また、VCがハンズオン型で事業開発を支援するケースも多く、経営資源が限られたスタートアップにとっては、成長スピードを大幅に上げる大きな武器となります。
資金提供以外の支援(ネットワーク・知見)
多くのVCは、資金の提供だけにとどまらず、経営や事業戦略へのアドバイス、人材採用支援、PR戦略の立案など、多角的な支援を行います。
VC自身が多くの投資案件を見てきた経験や、失敗と成功のパターンを知っているため、スタートアップにとっては経営上の貴重なナレッジを享受できる点が大きなメリットです。
特に、スタートアップが成長フェーズに入った時には、経営で生じる課題や壁を乗り越えるために外部の視点がますます重要になってきます。
VCから出資を受けるデメリット
VCからの出資を受けることには多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
資金や支援を受ける代わりに、経営の自由度や将来の利益配分などに影響が及ぶ可能性があるため、VCとの関係構築には慎重さが必要です。
ここでは、VCから出資を受ける際に懸念となる代表的なデメリットを解説します。
株式の希薄化
VCからの出資は、自社株式の一部を渡すことで資金を調達する仕組みです。
これにより、創業者や既存株主の持株比率が低下し、将来的な経営支配権にも影響を及ぼす可能性があります。
特に、複数のラウンドで資金調達を行うスタートアップは、結果的に創業者の持ち株比率が大幅に下がり、意思決定権が弱まるケースも少なくありません。
経営への関与・干渉リスクが生じる
VCは出資した資金を回収する責任を負っており、投資先の経営に対して一定の言及をする権利があり、それを行使することが一般的です。
経営会議への出席やレポート提出を求められるなど、経営の透明性が高まる反面、創業者が思い描くスピード感や戦略とズレが生じる場面もあります。
特に、投資先の経営に深く関与するハンズオン型VCの場合、経営方針に対する意見が強く出ることもあるため、どこまで関与を許容するかが重要なポイントとなります。
第一に結果を求められる
VCの最大の目的は投資リターンの獲得です。
したがって、スタートアップにはエグジット(上場や売却)への強いプレッシャーがかかることがあります。
場合によっては、創業者が考える長期的なビジョンや社会的意義よりも、早期の売上成長や利益確保が優先されることもあります。
そのため、VCから投資を受ける場合は、このようなプレッシャーに耐えうる経営体制や心構えが必要です。
VCが出資先を選ぶ際に重視するポイント
VCは、投資した資金を数倍以上にして回収することを目的としているため、出資先を選ぶ際には非常に厳しく多角的に評価を行います。
単に事業アイデアが新しいだけではなく、市場の大きさや成長性、事業モデルの収益性、経営陣の実行力や信頼性など、さまざまな観点からリスクとリターンを見極めます。
この章では、VCが出資を検討する際に特に注目するポイントを4つに分けて解説します。
市場性・実現性
最も基本的かつ重要な視点が「市場性」と「実現性」です。
市場性とは、対象としているマーケットの規模、成長性、そして競争環境などを指します。
VCは、一定の投資回収を見込むために、最終的に数十億円以上の市場規模があることを一つの目安としています。
一方、実現性は、その市場で実際にプロダクトやサービスが成立するか、スケールできるかという点です。構想が壮大でも、実行体制が未成熟であれば投資判断は見送られることが多くあり、すでにMVP(Minimum Viable Product)をリリースしていたり、PoC(Proof of Concept)が成功していたりすると、実現可能性が高いと見なされ、投資を受けやすくなります。
ビジネスモデル
ビジネスモデルは、事業がどのように収益を上げ、持続的に成長していくかを示す重要な要素です。
VCは単なるアイデアではなく、それが収益につながる構造になっているか、スケーラビリティ(利用者や仕事の増大に適応できる能力・度合い)があるかを重視します。
たとえば、SaaSモデルのようにLTV(顧客生涯価値)を高めつつ、CAC(顧客獲得コスト)を抑える仕組みが明確な場合、収益性と拡張性の両立が見込めるため、VCから好まれる傾向があります。
また、収益化のタイミングが明確かどうか、初期から黒字化を狙うのか、先行投資型でシェア獲得を狙うのかといった戦略も評価対象となります。
経営陣の経歴や実績
どんな事業も、最終的にそれを成功に導くのは「人」です。
VCが出資判断で重視するのが、創業メンバーや経営陣の実績、スキル、人柄、そしてチームとしての信頼性です。
たとえば、過去に起業経験がある、業界に深いネットワークがある、大企業で事業開発を主導してきた、などの経歴は大きなプラスになります。
一方で、たとえ実績が乏しくても、熱意や柔軟性、データに基づいた判断力などが評価される場合もあります。
また、創業チームの関係性や価値観の共有度、意思決定プロセスなど、長期にわたって一丸となって経営できる体制かどうかも、VCは細かくチェックしています。
イベント参加企業・VC同士の情報網
VCは、業界イベントやピッチコンテスト、アクセラレータープログラムなどを通じて有望なスタートアップを発掘しています。
これらの場に積極的に参加し、高評価を得ている企業は、それだけで一定の信頼性を得ることができます。
また、VC同士の情報共有ネットワークも強力な判断材料となります。たとえば、すでに信頼しているVCが出資している、あるいは注目している企業であれば、安心感を持って後続投資に踏み切れるケースも少なくありません。こうしたネットワークは、数値には現れない信用力として作用します。
そのため、スタートアップ側としてもイベントやネットワーキングを活用し、業界内での認知度を高めておくことが、間接的に資金調達の成功率を高める戦略につながります。
スタートアップに適したVCへのアプローチ手段
資金調達を目指すスタートアップにとって、どのVCに、どのようにアプローチするかはとても重要です。単に資金を得るだけでなく、VCが持つ知見やネットワークを活用できるかどうかが、その後の事業成長に大きな影響を与えます。
しかし、VCは日々膨大な数の投資案件を見ており、ただ問い合わせただけでは埋もれてしまうケースも少なくありません。
スタートアップ側としては、自社に合ったVCに効率よくリーチするための手段を複数用意し、接点を増やすことが重要です。
ここでは、スタートアップがVCとつながるための主なアプローチ方法を3つ紹介します。
取引先からの紹介
VCにアプローチする際、最も信頼度が高く効果的なのが「紹介」です。
VCは人脈を重視するため、信頼するネットワーク経由での推薦や紹介は、それだけで一定の安心材料となります。特に、自社のビジネスをよく理解している取引先からの紹介であれば、自社の強みや魅力を適切に伝えてもらえるため、VCへの印象も良くなりやすいでしょう。
紹介をもらうためには、まずは既存の取引先や周囲のネットワークに、自社が資金調達を検討していることをオープンに伝え、支援をお願いすることが重要です。
イベントやコンテストへの参加
スタートアップ向けのピッチイベントやビジネスコンテストは、VCに自社を知ってもらう絶好の機会です。
こうした場は、VCが新しい投資先を探すために積極的に参加しており、登壇するだけで多くのVCの目に留まる可能性があります。
また、イベントで高評価を得ることで、第三者からの推薦やメディア露出につながることも少なくありません。さらに、ピッチの過程で事業計画をブラッシュアップできる点も大きなメリットです。
イベントやコンテストを選ぶ際は、参加するVCの顔ぶれや、そのイベントがどのフェーズのスタートアップをターゲットにしているかをしっかり確認し、自社に合ったものに絞ることがポイントです。
支援事業の活用
各自治体や国の公的機関、あるいは民間のインキュベーションプログラムなどが実施する支援事業を活用するのも有効な手段です。
支援事業の多くは、スタートアップに対してVCとのマッチング機会を提供しており、普段なら接点を持ちにくいVCともつながるきっかけになります。
また、支援事業に採択された実績は一種の「お墨付き」としてVCから評価されることもあります。特に国や自治体が運営するプログラムは審査も厳しく、その過程で事業計画の精度が上がるため、投資家への説明力向上にもつながります。
日本国内の代表的なVC
日本には、幅広いステージ・領域で活躍する代表的なベンチャーキャピタルが複数存在します。
ここでは、資金調達を目指すスタートアップが出会う可能性の高い、5つの主要VCについて紹介します。
グロービス・キャピタル・パートナーズ
| 設立年 | 1996年 |
| 事業内容 | アーリー~レイターステージへのハンズオン型支援 |
| 投資企業数 | 200社以上 |
| 主な投資先 | メルカリ、スマートニュースなど |
グロービス・キャピタル・パートナーズは、日本を代表する独立系VCの一つで、特に「ヒト・カネ・チエ」の総合支援体制が大きな特徴です。
単なる資金提供にとどまらず、経営戦略の立案や組織づくり、事業成長の支援など、ハンズオン型の支援に強みを持っています。
また、グロービス経営大学院を母体とする豊富なネットワークと人材プールを活かし、経営陣の強化や経営人材の紹介など、企業成長を多角的に支援できる点も他社とは一線を画します。
投資先としては、メルカリやスマートニュース、グリーといった著名企業を多数輩出しており、日本のスタートアップエコシステムの発展に大きく貢献しているVCです。
インキュベイトファンド
| 設立年 | 2010年 |
| 事業内容 | プレシード~グロースまでの一貫支援 |
| 投資企業数 | 800社以上 |
| 主な投資先 | AGRIST、アルダグラム、アスエネなど |
インキュベイトファンドは、シード・アーリーステージ投資のパイオニアとして知られ、創業初期のスタートアップに積極的に投資することで高い存在感を誇ります。
「起業家第一主義」を掲げ、投資後も経営や戦略の立案をきめ細かく支援する姿勢が強みです。
2021年には、シード投資で支援した企業が成長した後も継続的に支援するためのグロースファンドを立ち上げるなど、事業フェーズを問わない投資体制を構築しています。
スタートアップにとって、初期段階から信頼できるパートナーを求める場合、非常に心強い存在といえるでしょう。
サイバーエージェント・キャピタル
| 設立年 | 2006年 |
| 事業内容 | シード~アーリー期のインターネット領域支援 |
| 投資企業数 | 200社以上 |
| 主な投資先 | クラウドワークス、スペースマーケットなど |
サイバーエージェント・キャピタルは、親会社のサイバーエージェントグループの豊富なインターネットビジネスの知見とネットワークを活かし、主にインターネット領域に特化して投資を行っています。
国内外に展開する10拠点を通じ、東南アジアなど海外スタートアップへの投資も積極的で、クロスボーダー展開を視野に入れる企業にとっては非常に心強いパートナーです。
また、投資先へのマーケティング支援や事業開発のノウハウ提供など、資金面だけでなく事業成長を強力に後押しするサポートが充実しています。クラウドワークスやスペースマーケットなど、IPOや急成長を遂げた企業を数多く輩出しており、スタートアップ業界では「インターネット系スタートアップの登竜門」として認知度が高いVCです。
GMOベンチャーパートナーズ
| 設立年 | 2005年 |
| 事業内容 | IT系領域への投資・価値向上支援 |
| 投資企業数 | 50社以上 |
| 主な投資先 | ラクスル、マネーフォワード、Chatworkなど |
GMOベンチャーパートナーズは、GMOインターネットグループのCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)として設立され、IT・インターネット領域を中心に投資を展開しています。
特にSaaSやFinTech、EC領域への投資に強みを持ち、投資後の支援もグループのリソースを活かしてきめ細かく行うのが特徴です。
累計で6本のファンドを組成し、IPO実績を多数誇るなど、確かな実績を積み重ねています。投資スタンスとしては、スタートアップの成長フェーズに応じて柔軟に対応し、グループ内のエンジニアやマーケティング部門とも連携できる点が大きなメリットです。スタートアップにとって、成長だけでなく実務面の支援も求める場合に心強いパートナーとなるVCです。
実例で学ぶ!VC出資で成長した事例3選
ここでは、実際にVCの支援を受けて急成長を遂げた国内外の代表的なスタートアップ3社を取り上げ、それぞれの資金調達の特徴やピッチ方法、成長のポイントを分析します。
彼らの成功には共通する要素があり、資料の構成、数字の示し方、戦略の伝え方など、資金調達を目指す起業家が学べる貴重なヒントが満載です。
これらの実例を踏まえ、より実践的な資金調達準備やプレゼンテーションのコツを掴んでいきましょう。
メルカリ|たった8枚のスライドで資金調達に成功
メルカリは、日本発のC2Cフリマアプリとして急成長し、VCからの資金調達でも話題となりました。初期のプレIPOやシリーズAラウンドなどで、投資先に選ばれた背景には、シンプルかつ戦略的な資料構成がありました。
実際、メルカリのスライドはわずか8枚程度であり、市場背景、プロダクトの特徴、ユーザー獲得戦略、ビジネスモデル、トラクション、チーム、資金用途、ビジョンなどを短くまとめるスタイルが高く評価されたとされています。
資料の質の高さと熱意が、説得力を持って投資家の注目を集めた例と言えるでしょう。
Airbnb|洗練されたピッチブックで多額の資金調達
Airbnbは、2009年に3分ほどのピッチスライドを活用して約6,000万円の資金調達に成功しました。
ピッチ資料には、「問題提示 → 具体的ソリューション → 市場規模 → ビジネスモデル → 実績 → チーム → 資金使途」までが、短く明確にまとめられています。
この資料の成功要因は、伝えるべき要素を絞り込み、視認性に優れた構成と数値で投資家に訴求できた点です。結果としてシード調達後も急成長し、さらなる大型の資金調達につながりました。
SmartHR|シリーズBラウンドでの加速
株式会社SmartHRは、クラウド型の人事労務管理システムを提供するベンチャー企業であり、2013年に設立されてから急速に成長を遂げてきました。
SmartHRの資金調達は成功事例として有名で、特にシリーズBラウンドでの調達が注目されています。ラウンドBでは、約15億円を調達し、評価額を大幅にアップさせました。
これにより、さらなるサービスの拡充やマーケティング活動に資金を投じることが可能となり、顧客基盤の拡大を実現しました。
SmartHRの強みは、資料における「人事業務クラウド市場の高成長性」を示すデータを充実させたことと、具体的な収益モデルおよびARR実績を明確に提示した点にあります。これにより、投資家に市場の規模感と収益性、拡張性の両方を強く訴求できました。
まとめ|自社の状況と必要性を整理してVCを活用しよう
VCからの出資は、スタートアップの成長に大きな力を与える一方で、投資先としての魅力を示すためには自社の状況や成長段階、資金ニーズを明確に理解し整理することが不可欠です。
まずは、自社のビジネスモデルや市場性、チームの強みを客観的に把握し、どのフェーズの資金調達が必要か、VCに期待する支援内容は何かを整理しましょう。そうすることで、自社に適したVCを選定し、効果的にアプローチが可能になります。
また、VCは単なる資金提供者ではなく、経営のパートナーとして多角的な支援を提供する存在です。資金調達の成功は、資料の質やピッチの内容だけでなく、その後のコミュニケーションや信頼関係の構築にも大きく依存します。
本記事で紹介した代表的なVCの特徴や、実際に資金調達で成功した事例を参考に、自社の成長戦略に最適なVC活用を進めていきましょう。
成長フェーズのスタートアップとの協業チャンスを見つけませんか?
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
VCから投資を受けて成長段階にあるスタートアップとの具体的な連携方法や協業のポイントを豊富に扱っているので、ぜひ貴社のオープンイノベーション推進にご活用ください。


