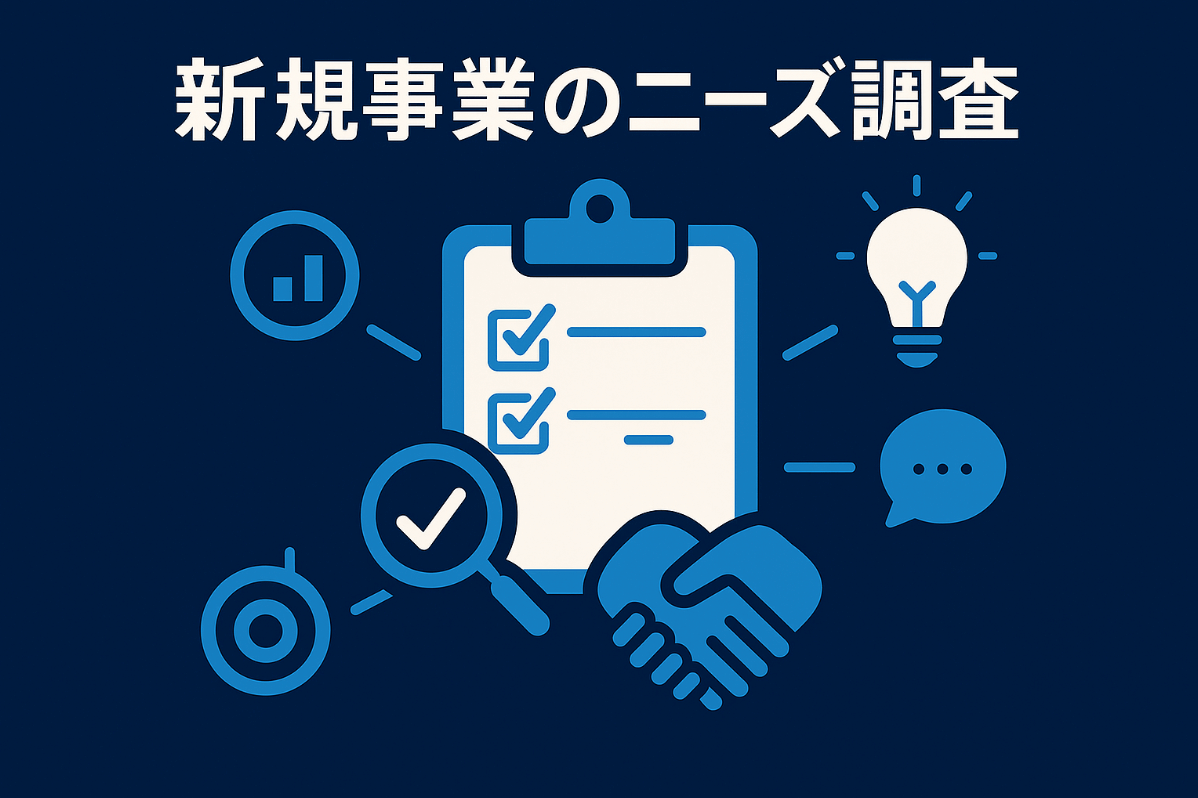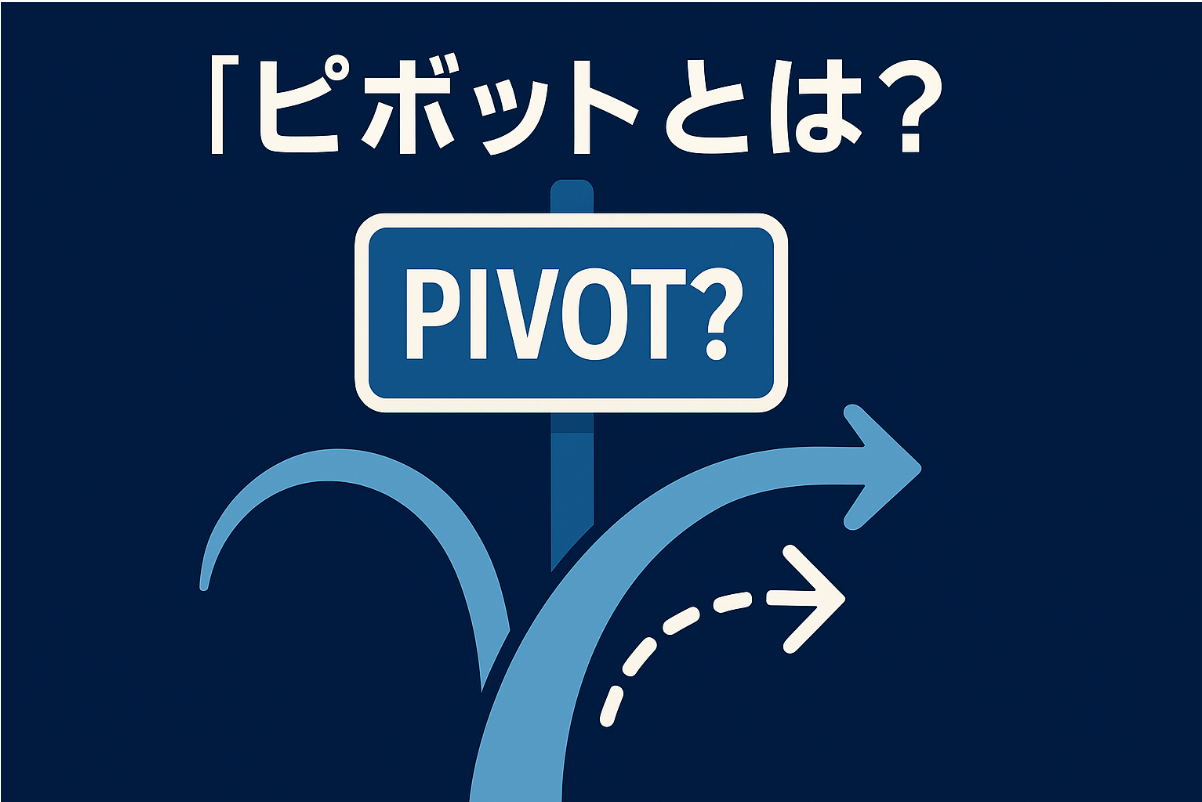新規事業を立ち上げる際、どれほど魅力的なアイデアを持っていても、それが顧客のニーズと噛み合っていなければ、市場で成果を上げるのは容易ではありません。特に、顧客自身も気づいていない「潜在ニーズ」を的確に捉えることができれば、他社との差別化や将来的な成長につながる大きな武器になります。
実際、多くの成功している企業は、定量調査と定性調査を組み合わせた丁寧なリサーチを通じて、ニーズに根ざした商品やサービスを展開しています。
そこで今回は、新規事業におけるニーズ調査の基本的な考え方に加え、調査手法の選び方や実際の成功事例、さらに調査結果を事業へどう活かすかといった具体的なステップまでを網羅的に解説しています。
新たな市場を切り開きたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
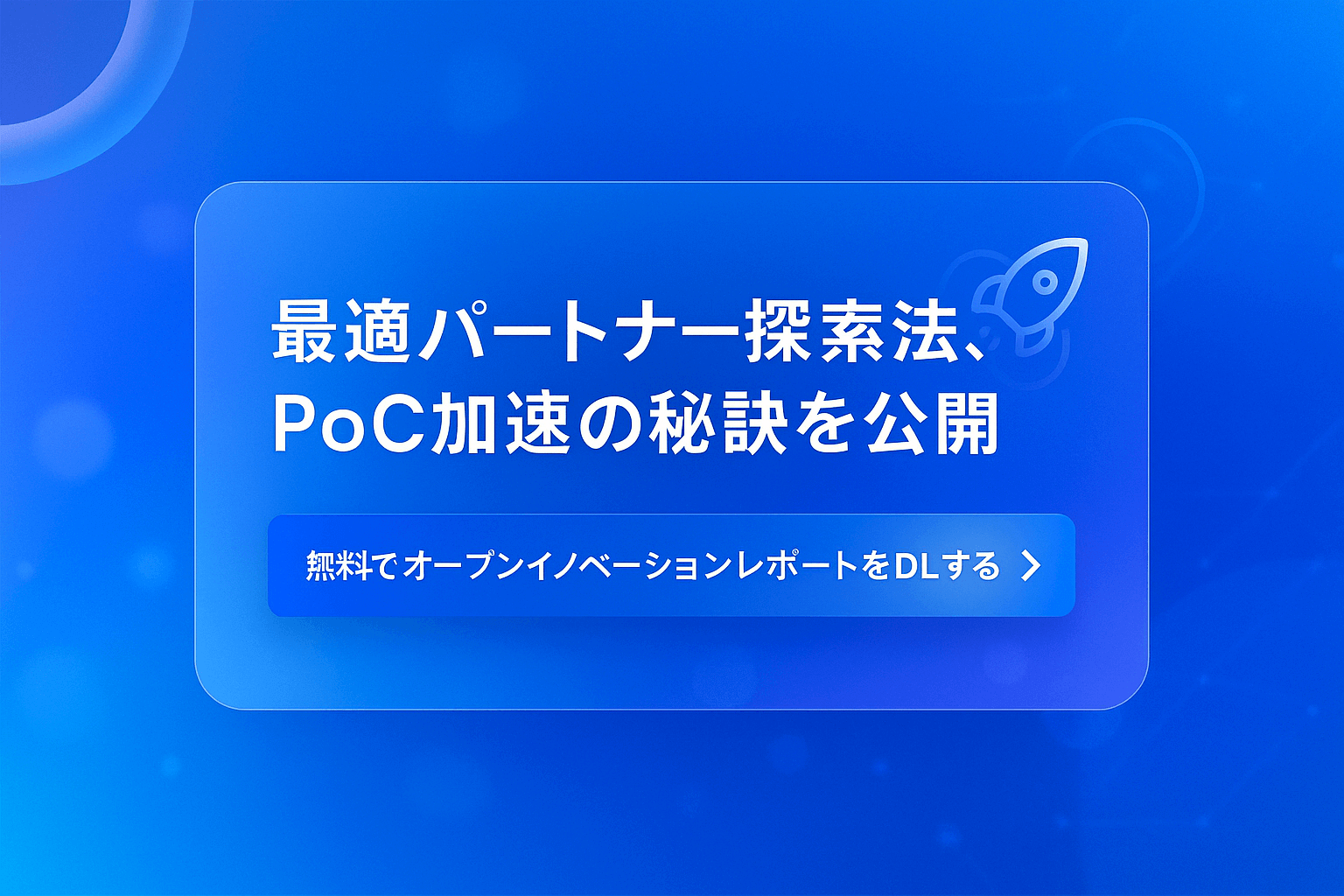
ニーズ調査で見つけた課題は外部連携で解決する企業が増えています
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
ニーズ調査で発見した市場機会を外部連携で事業化する具体的な手法や、スタートアップの市場知見を活用したニーズ発見の成功事例を豊富に扱っているので、ぜひ貴社の新規事業推進にご活用ください。
なぜ新規事業にニーズ調査が欠かせないのか?
新規事業を成功させるには、優れたアイデアだけでは不十分です。顧客が抱える課題や欲求を的確に把握し、その解決につながる価値を提供する必要があります。ここでは、なぜニーズ調査が不可欠なのかを具体的に解説します。
顧客ニーズとビジネスアイデアの関係
新規事業において、顧客ニーズとビジネスアイデアの関係が極めて密接です。なかでも注目すべきなのが、顧客自身も気づいていない「潜在ニーズ」や「インサイト」です。これらを的確に捉えることで、他社と差別化された新しい価値を提供できます。
例えば、ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」や、日清食品の「0秒チキンラーメン」は、いずれも顧客の無意識の願望を起点に企画され、支持を集めた成功事例です。
顧客への理解を深めることによって、未来の需要を先取りするアイデアが生まれる可能性が高まります。
ニーズ調査を怠ったときに起きる失敗例
新規事業においてニーズ調査を怠ると、事業の土台そのものが揺らぐ恐れがあります。ターゲット設定の誤りや表面的なリサーチは、むしろ失敗を早める要因になります。新規事業では「とにかくやってみる」という姿勢だけでは不十分です。重要なのは、仮説を丁寧に検証し、顧客の顕在ニーズや潜在ニーズを的確に捉えることです。
リソースが限られる立ち上げ期だからこそ、慎重な検証を重ねることが、リスクを最小限に抑え、成功の確率を高めるカギとなります。
新規事業のニーズ調査のメリットとデメリットを理解しよう
ニーズ調査は、新規事業の成功確率を高められる手法である一方で、過信や設計ミスによって逆効果を招くこともあります。調査によって得られるデータは、商品開発や市場戦略の意思決定に大きく影響するため、メリットだけでなくデメリットも正しく理解しておくことが欠かせません。ここでは、ニーズ調査がもたらす効果と、見落としがちな注意点について詳しく解説します。
ニーズ調査がもたらす新規事業の成功メリット
ニーズ調査は、新規事業の成功確率を大きく高める重要な調査です。顧客の課題や期待を正確に捉えることで、事業アイデアの実現性が高まり、無駄な開発や投資を避けることができます。
特に、定量データと定性データを組み合わせた調査では、表面的なニーズにとどまらず、顧客の潜在的な不満やインサイトまで把握できるのが強みです。さらに、リサーチ結果に基づいて商品やサービスの方向性を明確にすることで、データに裏付けられた戦略的な意思決定がしやすくなります。
加えて、競合他社との違いを浮き彫りにしやすくなるため、事業の独自性を打ち出すうえでも効果的です。
ニーズ調査の限界や注意すべきデメリット
ニーズ調査は新規事業の成功にとって不可欠ですが、その一方で限界や注意点も存在します。まず、調査で得られるのは「過去の声」にすぎず、将来の行動を予測する確実な根拠にはなりません。顧客の意見に依存しすぎると、かえってイノベーションの可能性を狭めてしまうこともあります。
また、設問設計が不十分な場合には、バイアスのかかったデータや曖昧な結果しか得られず、誤った判断につながるリスクが高まります。さらに、調査対象が偏っていたり、表面的なウォンツ(※)ばかりに注目してしまうと、顧客の本質的なニーズを見落とす恐れもあるでしょう。
こうしたリスクを避けるためには、調査の目的をあらかじめ明確にし、インタビューや観察、定量調査など複数の手法を組み合わせて、多角的に分析する視点が求められます。
(※)ニーズを満たす具体的な商品やサービスへの欲求のこと
新規事業のニーズ調査の主な手法と選び方
ニーズ調査を効果的に行うためには、目的やリソースに応じて適切な手法を選ぶことが重要です。定量調査と定性調査の違いを理解し、アンケートやインタビュー、ユーザーテストなどを組み合わせることで、顧客の表面的な声だけでなく、深層的なインサイトにも迫ることができます。ここでは、主要な調査手法の特徴と選び方について、実践的な視点から解説していきます。
定量調査と定性調査の違い

定量調査と定性調査は、目的や得られる情報の質が異なる手法です。
定量調査は、アンケートなどを通じて多くの対象から数値データを収集し、傾向や割合を統計的に把握するのに適しています。一方で、定性調査はインタビューや観察によって、顧客の感情や行動の背景にある「なぜ」を深く掘り下げる方法です。
例えば、「何%の人が購入したか」といった情報は定量調査で把握でき、「なぜ購入に至ったのか」という動機や背景は定性調査で明らかにできます。
新規事業においては、初期段階で定性調査を実施して仮説を構築し、その後に定量調査で裏付けをとるといった併用が効果的です。調査の目的に応じて両者を適切に使い分けることが、実効性の高いニーズ把握につながります。
アンケート、インタビュー、ユーザーテストの活用法
アンケート、インタビュー、ユーザーテストは、それぞれ異なる視点から顧客ニーズを捉える有効な手法です。新規事業の立ち上げ時には、これらも適切に使い分けることで、より深いインサイトが得られます。
アンケートは定量調査として広範なデータを短期間で収集でき、ユーザーの属性や満足度、行動傾向などを数値で把握するのに適しています。一方、インタビューは個々の利用者の感情や動機に迫る定性調査であり、潜在的なニーズや改善のヒントを掘り下げるのに効果的です。
さらに、ユーザーテストでは、実際のプロダクトやプロトタイプを使ってもらいながら、操作時の行動や戸惑いを観察することで、使い勝手やUI/UXの課題を具体的に洗い出すことが可能です。
これらの手法を組み合わせることで、表面的なウォンツだけでなく、顧客の本音や真の課題に迫る調査設計が実現できます。
予算や目的別の調査手法の選び方
ニーズ調査を成功させるには、調査の目的や予算に応じた適切な手法の選定が重要です。例えば、新商品の方向性を探る初期段階では、インタビューやグループディスカッションといった定性調査が有効とされています。一方で、市場規模や購買意向を具体的な数値で把握したい場合には、Webアンケートやネットリサーチなどの定量調査が適しています。
さらに、SNS投稿の分析や社内データの活用といった低コストな手法を組み合わせることで、限られた予算内でも効果的な調査が実現できます。調査目的を明確にしたうえで、得たい情報に最適な方法を見極めることが成功のカギとなります。
新規事業のニーズ調査で使えるツール・サービス
新規事業の立ち上げにおいて、顧客ニーズを正確に捉えるには、適切なツールやサービスの活用が欠かせません。限られたリソースでも効率的に調査を進めるためには、目的や予算に応じて手法を選び、最適なツールを使い分けることが重要です。ここでは、無料で使えるフォーム作成ツールから、本格的な調査会社のサービス、さらにはSNSや社内データを活用した実践的な手法まで、幅広く紹介します。
無料・低コストで始められる調査ツール
無料または低コストで利用できる調査ツールとしては、Google Forms、Questant、formrunなどが代表的です。なかでもGoogle Formsは完全無料で提供されており、質問のカスタマイズやリアルタイムでの集計が可能です。さらに、Google スプレッドシートと連携することで、より詳細なデータ分析にも対応できます。
Questantやformrunも、無料プランで基本的な機能を備えており、質問数や回答数に制限はあるものの、テンプレートや入力補助機能が充実しています。いずれも直感的な操作でフォーム作成ができ、Web上で簡単に配布・回収できる点が特長です。
こうしたツールは、新規事業の立ち上げ初期において、コストを抑えながら顧客の声を集める手段として効果的です。目的に応じて、それぞれの機能や制限を確認し、最適なツールを選定しましょう。
高度な分析が可能なプロ向けサービス
新規事業のニーズ調査において、より精緻で戦略的な意思決定を行いたい場合は、プロフェッショナル向けの調査サービスを活用するのがおすすめです。
例えば、マクロミルやクロス・マーケティング、インテージといった大手の市場調査会社では、数千万規模のパネルデータとAI分析技術を組み合わせることで、高精度なデータ収集と分析が可能です。ユーザー属性ごとの深掘りはもちろん、購買履歴や行動ログとの連携によって、トレンドの可視化や顧客インサイトの抽出にも対応しています。
また、ビザスクのように業界経験者に直接ヒアリングできる「エキスパートサーベイ」では、現場の実情に基づいた定性情報を迅速に得ることができます。
これらのサービスは、調査設計から実施、分析、レポート作成までを一貫して支援してくれるため、仮説検証や戦略立案の精度を高めるうえで心強い選択肢となるでしょう。
社内データやSNSを活用する裏技的アプローチ
社内データやSNSは、低コストかつスピーディにニーズの兆しを掴む“裏技的な”調査手段といえます。例えば、既存の顧客アンケートや問い合わせ履歴、営業日報といった社内データには、ターゲット層のリアルな課題や要望が蓄積されています。これらを丁寧に分析するだけでも、事業のヒントにつながるケースは少なくありません。
一方、SNSでは顧客の本音がリアルタイムで交わされており、商品やサービスに対する率直な声を拾うには最適な場です。ハッシュタグ検索やコメントの傾向を探ることで、トレンドや潜在的なニーズをすばやく把握できます。ただし、SNSは属性の特定が難しいため、社内データと組み合わせて活用するのが効果的です。
このように、社内資源と外部データを掛け合わせることで、調査コストを抑えつつも精度の高いインサイトを得ることが可能になります。
実際に行われた新規事業のニーズ調査の成功事例
新規事業の成功には、机上の空論ではなく実際の顧客ニーズに基づいたアプローチが欠かせません。ここでは、ニーズ調査を的確に行い、実際に市場で成果を上げた企業やスタートアップの具体事例を紹介します。
大手企業による市場ニーズの先取り事例
大手企業が市場ニーズを先取りし、新規事業を成功させた事例は数多く見られます。例えば、富士フイルムは、写真フィルムの需要減少という逆風の中で、コラーゲン研究やナノテクノロジーといった既存の技術資産を応用。徹底した市場分析をもとに化粧品・医療分野へと舵を切り、スキンケアブランド「アスタリフト」を展開しました。結果として、ブランドは大きな支持を獲得しています。
一方、ユニ・チャームは介護現場の生の声に耳を傾け、肌へのやさしさと使いやすさを両立したおむつを開発。「ライフリー」シリーズとして高齢者市場で高い評価を受けています。
いずれの事例にも共通するのは、丁寧なニーズ調査と自社技術の再活用、そして変化を恐れない柔軟な姿勢です。こうした取り組みが、新たな価値の創出につながっています。
スタートアップがユーザー調査で生んだヒット商品
スタートアップが限られたリソースの中でヒット商品を生み出すには、綿密なユーザー調査と、そこから得たデータの迅速な反映がカギとなります。ある成長中のスタートアップでは、ユーザーの行動データや導線の分析を通じて課題を洗い出し、Webサイトの構成や行動導線を改善。小さな改善を積み重ねた結果、無料トライアルの申込数が増加し、短期間で導入数を大きく伸ばすことに成功しました。
このように、ユーザー調査を通じて顧客の反応やつまずきポイントを把握し、プロダクトやサービスに素早く反映することで、コストを抑えながらも大きな成果を生み出すことが可能です。
ニーズ検証からピボットした成功パターン
Slackは、もともとオンラインゲーム「Glitch」の開発企業としてスタートしました。しかし、ゲーム事業は市場の反応が振るわず、やがて撤退に至ります。その過程で社内用に開発していたチャットツールが外部から注目され、ニーズを検証した結果、ビジネス向けメッセージプラットフォームへとピボットしました。
ユーザーの声を反映しながらUIを磨き、柔軟に機能を追加していったことで、多くの企業から支持を獲得し、最終的には日間アクティブユーザー1,000万人を超える大規模なサービスへと成長を遂げました。もともとのリソースを活かしつつ、顧客ニーズに沿って方向転換を図った典型的な成功事例といえます。
新規事業のニーズ調査の具体的なステップ
ニーズ調査は、新規事業の成否を左右する重要なプロセスです。しかし、「どのように進めればよいのか」が曖昧なままでは、調査結果も活かしきれません。ここでは、調査目的の明確化から仮説立て、実施、分析、そして事業への反映まで、段階的に押さえるべきステップを具体的に解説します。
【ステップ1】調査目的の明確化と仮説立て
新規事業におけるニーズ調査では、まず「調査の目的を明確にし、仮説を立てること」が欠かせません。目的が曖昧なままでは、得られたデータをどう活用するかが不明確になり、調査全体の精度も低下してしまいます。
最初に「何を知りたいのか」「なぜ調べるのか」をはっきりさせ、自社の課題や市場に関する不明点を整理しましょう。そのうえで、顧客ニーズや市場構造に関する仮説を設定します。例えば「若年層はSNSを主な情報源としている」といった前提があれば、それに沿った調査設計が可能です。
ただし、仮説はあくまで検証の出発点であり、思い込みではなく根拠に基づいて立てることが重要です。適切な仮説を軸に調査を進めることで、結果の解釈が明快になり、次のアクションにもつなげやすくなります。
【ステップ2】ターゲット設定と調査設計
ニーズ調査の第2ステップでは、「誰に対して調査を行うか(ターゲット設定)」と「何をどう聞くか(調査設計)」を明確にすることが重要です。
まずは、自社の商品やサービスが解決すべき課題を持つ人物像を具体化し、年齢・性別・地域・関心領域などの観点から対象を絞り込みます。そのうえで、仮説に基づいて調査項目を設計し、アンケートやインタビュー、ユーザーテストなど、目的に合った手法を選びましょう。
調査設計では、質問内容が調査目的と整合しているか、回答しやすい構成になっているかを確認することも大切です。さらに、必要な情報に応じて定量調査と定性調査を組み合わせることで、表面的な傾向だけでなく、対象者の深層心理まで把握することが可能になります。
ターゲットと設計の精度は、調査全体の成果を大きく左右するポイントです。
【ステップ3】実施・回収・分析のポイント
ニーズ調査の実施段階では、事前に設計した調査計画に沿ってスムーズに進行できる体制づくりが重要です。定量調査では、設問の誤解や回答漏れを防ぐために、あらかじめプリテストを実施しておくと安心です。一方、定性調査においては、対象者の選定やインタビューフローの構築が深いインサイトを得るためのポイントとなります。
調査後は、未記入や内容に矛盾のある回答を除外し、有効なデータのみを分析対象とします。分析では単なる数値の集計にとどめず、仮説に基づいたクロス集計やセグメント分析を行うことで、顧客行動の背景まで深く理解できます。さらに、定量データと定性データを組み合わせることで、数値だけでは見えにくい顧客の本音や深層心理にもアプローチしやすくなります。
【ステップ4】調査結果を事業プランに反映させる
調査で得られた結果は、分析して終わりではありません。事業プランに的確に反映させることが重要です。
顧客の声やデータから見えてきたニーズをもとに、商品やサービスの方向性、提供価値を具体的に落とし込んでいきましょう。例えば、定量調査で「価格に対する敏感さ」が明らかになった場合は、価格帯の見直しやキャンペーン施策の検討が有効です。
また、定性調査で「操作の難しさ」が課題として浮かび上がった場合には、UIの改善など、具体的な改良案として反映する必要があります。
こうした調査結果は関係部署とも共有し、社内での合意形成を図ることが成功のカギとなります。単なるアイデア評価にとどめず、実行可能なアクションプランとして具体化することで、調査の成果を最大限に活かすことができます。
新規事業のニーズ調査を成功させるためのポイントとコツ
ニーズ調査を行う際は、ただ情報を集めるだけでは不十分です。顧客理解を深め、仮説をもとに調査を設計し、実行可能なアクションへとつなげる視点が求められます。ここでは、インサイトの活かし方や仮説立てのポイント、スモールスタートの活用法など、実効性の高いニーズ調査を実現するための具体的なコツを紹介します。
調査結果のインサイトを的確に活かす方法
調査で得られたインサイトを活かすには、「気づき」を単なる情報として終わらせず、実行可能な施策へと落とし込むことが重要です。なかでもカギとなるのは、そのインサイトがどのような顧客体験や課題解決につながるのかを具体的に捉え、商品企画やサービス改善へと展開する視点を持つことです。
例えば、潜在ニーズとして「忙しさゆえに手軽さを求める心理」が見えた場合には、UIの簡略化や時短機能の追加が有効な対応策となります。さらに、部門間でインサイトを共有し、解釈のズレを防ぐ取り組みも欠かせません。
顧客理解を深めながら、仮説検証と施策の実行を繰り返すことで、インサイトを持続的な競争優位へと昇華させる姿勢が求められます。
ターゲット設定と仮説立ての重要性
ターゲット設定と仮説立ては、ニーズ調査を成功させるうえでの出発点です。まず、誰のニーズを明らかにするのかを具体的に定めることで、調査の精度と有効性が大きく向上します。年齢や性別、行動特性に加え、生活習慣や価値観まで含めて「課題を抱える人物像」を描くことが重要です。
あわせて、仮説の立案も大切です。仮説は単なる予想ではなく、既存のデータや事実に基づいて検証可能な形で設定する必要があります。例えば、「若年層は価格に敏感である」といった仮説を立てることで、調査項目や設問の設計方針が明確になります。
こうした準備を丁寧に行うことで、得られたデータから具体的な示唆を導きやすくなり、戦略的な意思決定につながる実効性の高い調査が実現できます。
小さく試して改善を繰り返すスモールスタート戦略
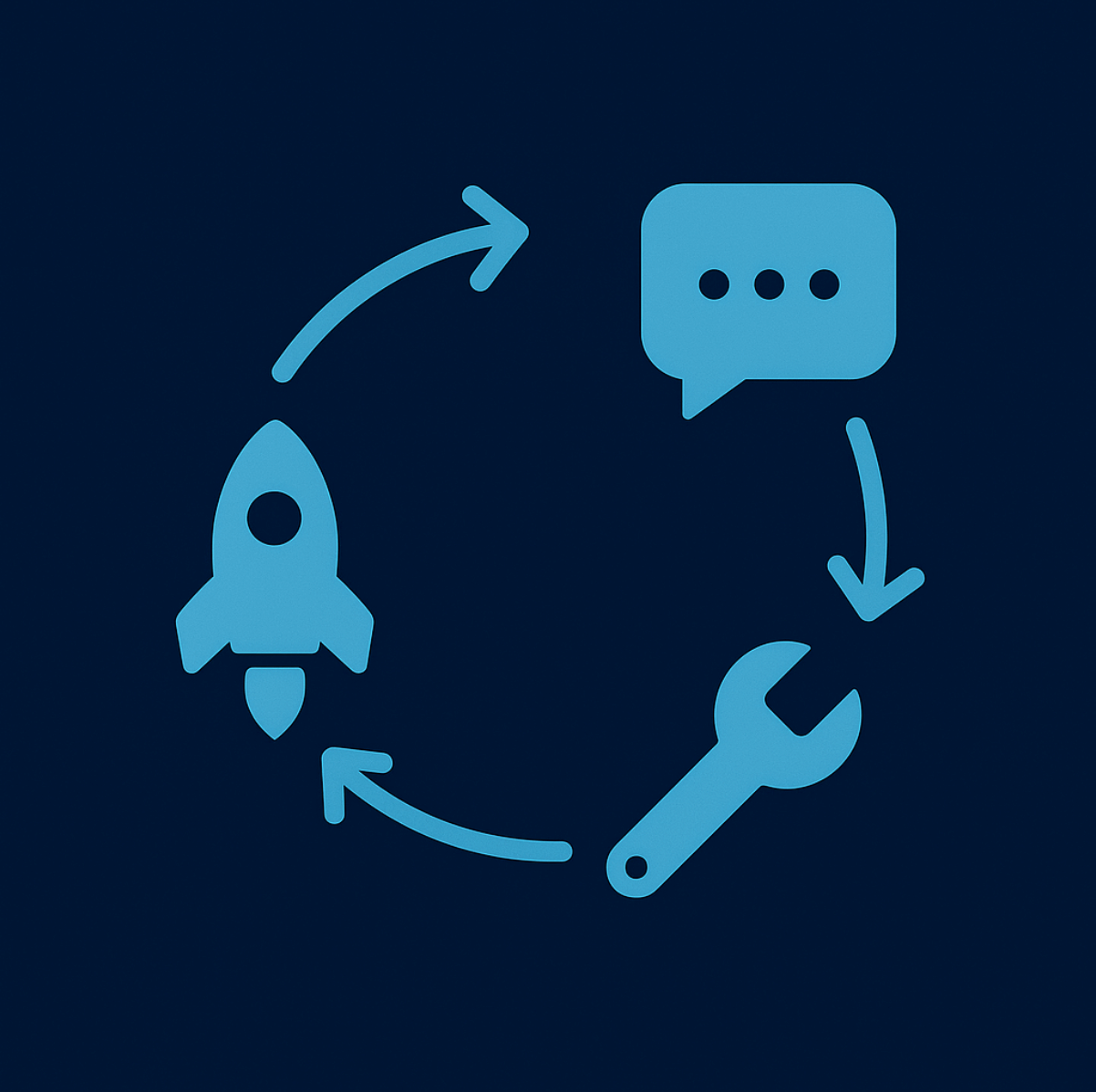
スモールスタート戦略とは、最小限のリソースで事業や施策を小さく始め、市場の反応を見ながら改善を重ねていくアプローチです。新規事業においては、ニーズ調査の結果を活かし、完璧な製品やサービスを一度に提供するのではなく、まずはMVP(Minimum Viable Product)として形にすることが重要となります。
初期段階で実際の顧客からフィードバックを得て、都度改善を加えることで、初期投資のリスクを抑えつつ、顧客に本当に求められている価値を見極められます。さらに、変化するニーズにも柔軟に対応できる体制を整えておくことで、スムーズな方向転換も可能になります。
スモールスタートは、仮説を現実の行動で検証しながら進められるため、ニーズ調査の成果を具体的な事業成長へとつなげるための実践的な手法といえるでしょう。
新規事業成功の土台になるニーズ調査を的確に行おう!
新規事業を成功に導くには、優れたアイデアだけでなく、顧客の本質的なニーズを見極める力が欠かせません。仮説の構築と検証を繰り返すプロセスや、スモールスタートによる市場の反応確認といったアプローチを理解すれば、実効性のある事業設計が可能になります。
実際、多くの企業が精度の高いニーズ調査を軸に事業の方向性を定め、成果を上げています。さらに詳しい事例や最新トレンドを知りたい方は、スタートアップと大手企業の協業実績をまとめた「ILSオープンイノベーションレポート2024」も参考にしてみてください。
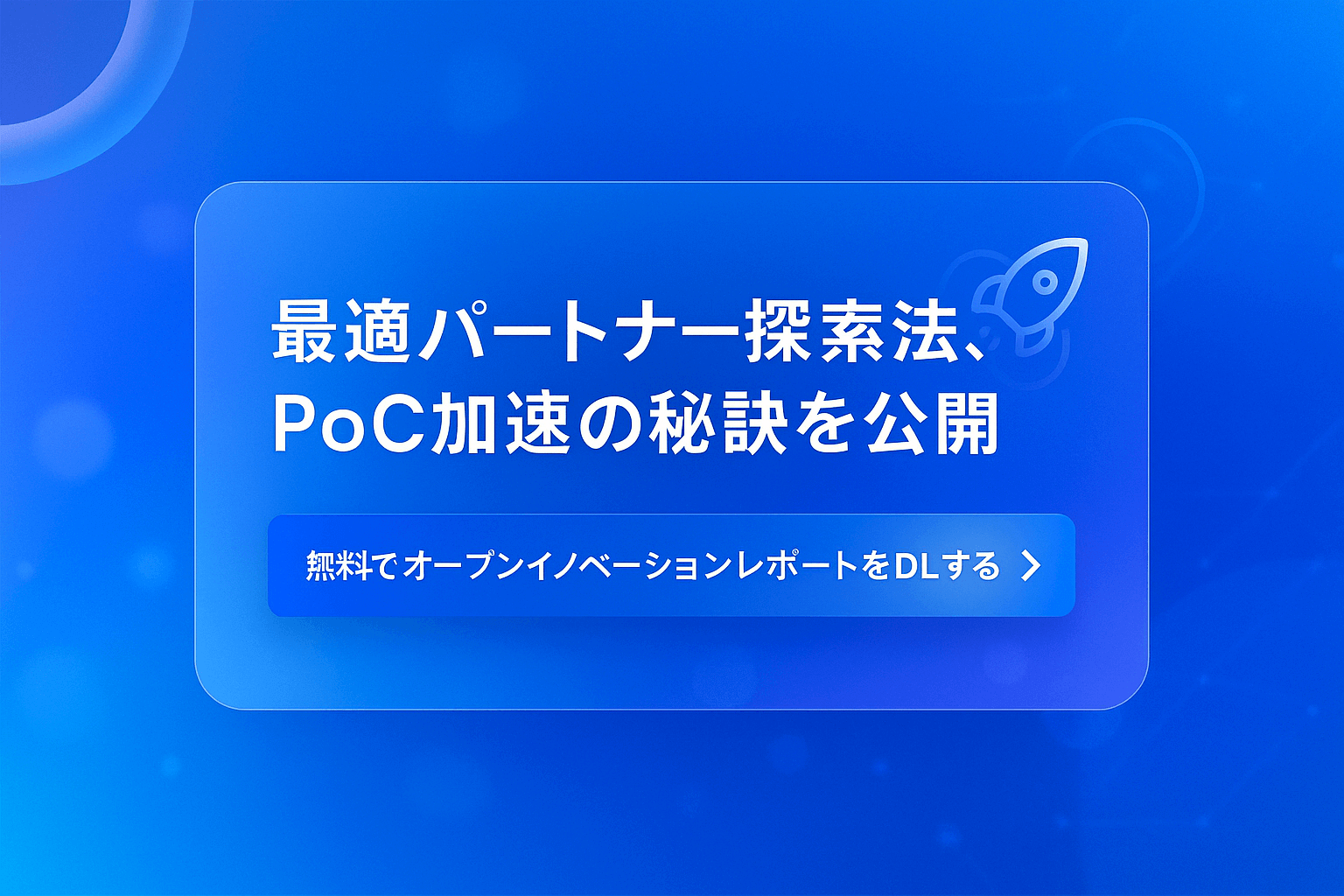
ニーズ調査で見つけた課題は外部連携で解決する企業が増えています
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。ニーズ調査で発見した市場機会を外部連携で事業化する具体的な手法や、スタートアップの市場知見を活用したニーズ発見の成功事例を豊富に扱っているので、ぜひ貴社の新規事業推進にご活用ください。