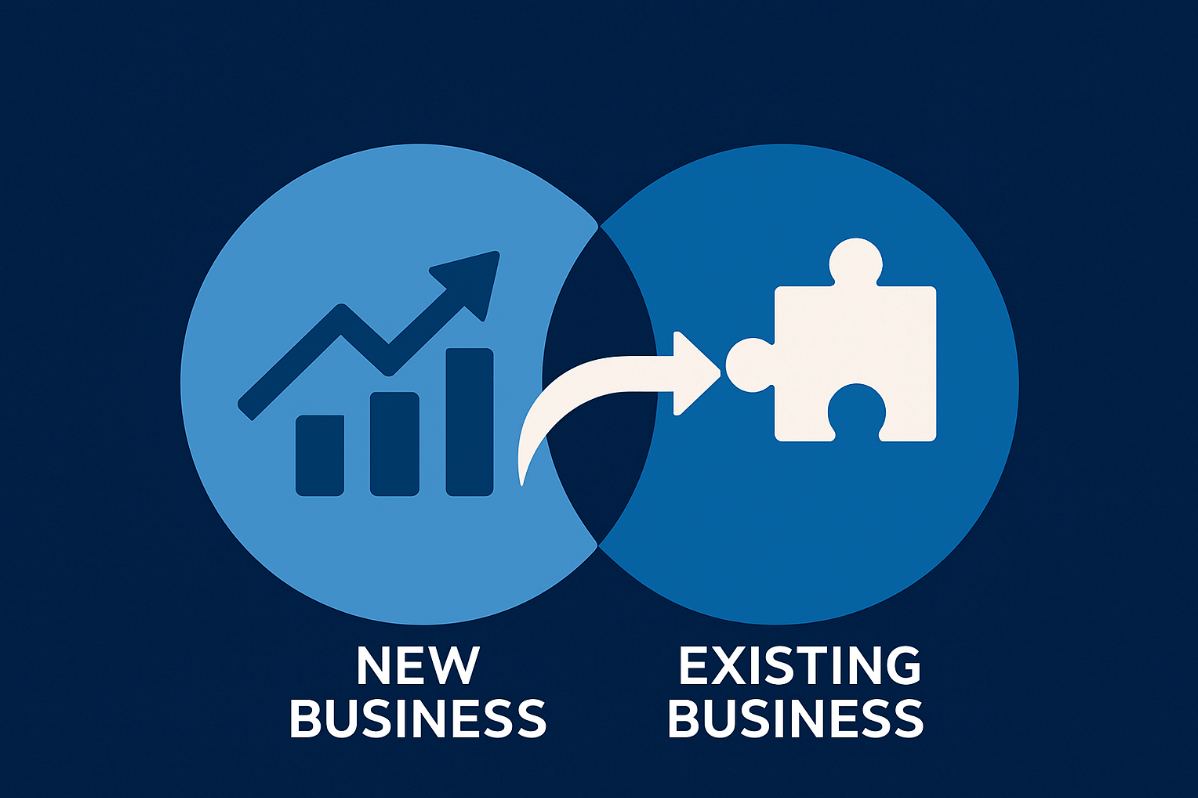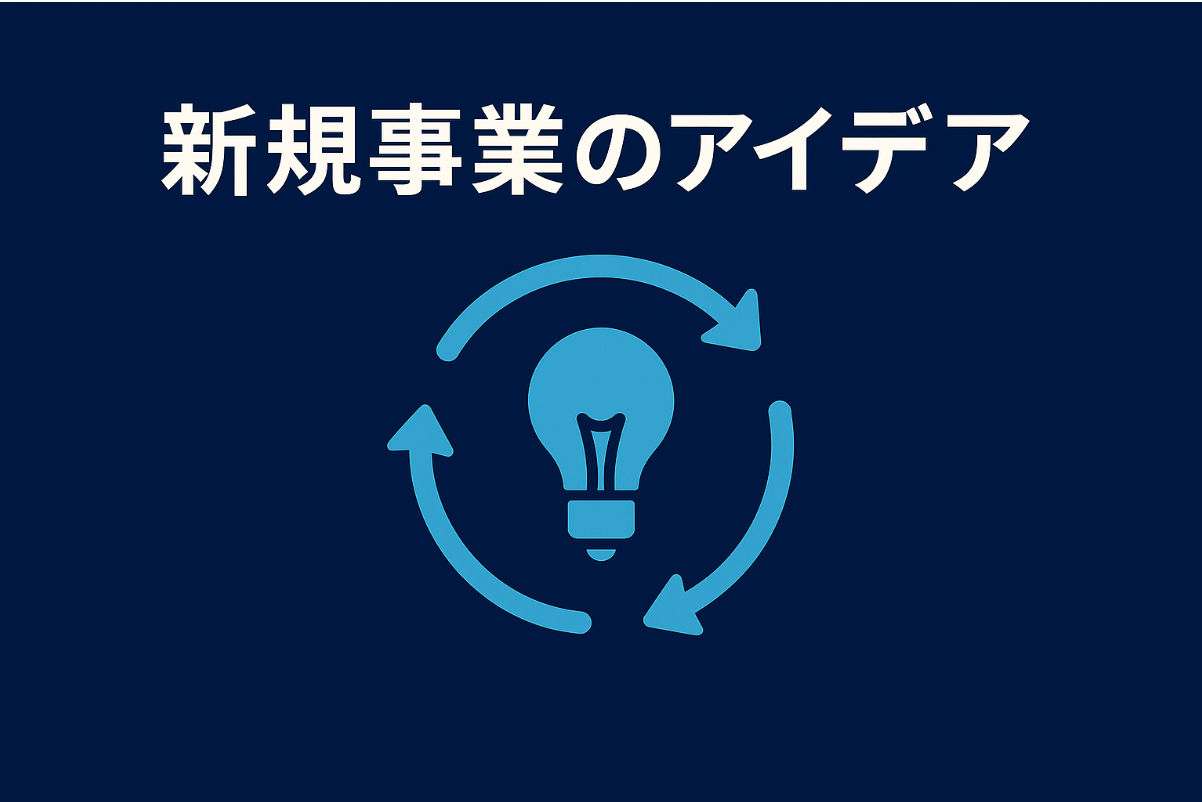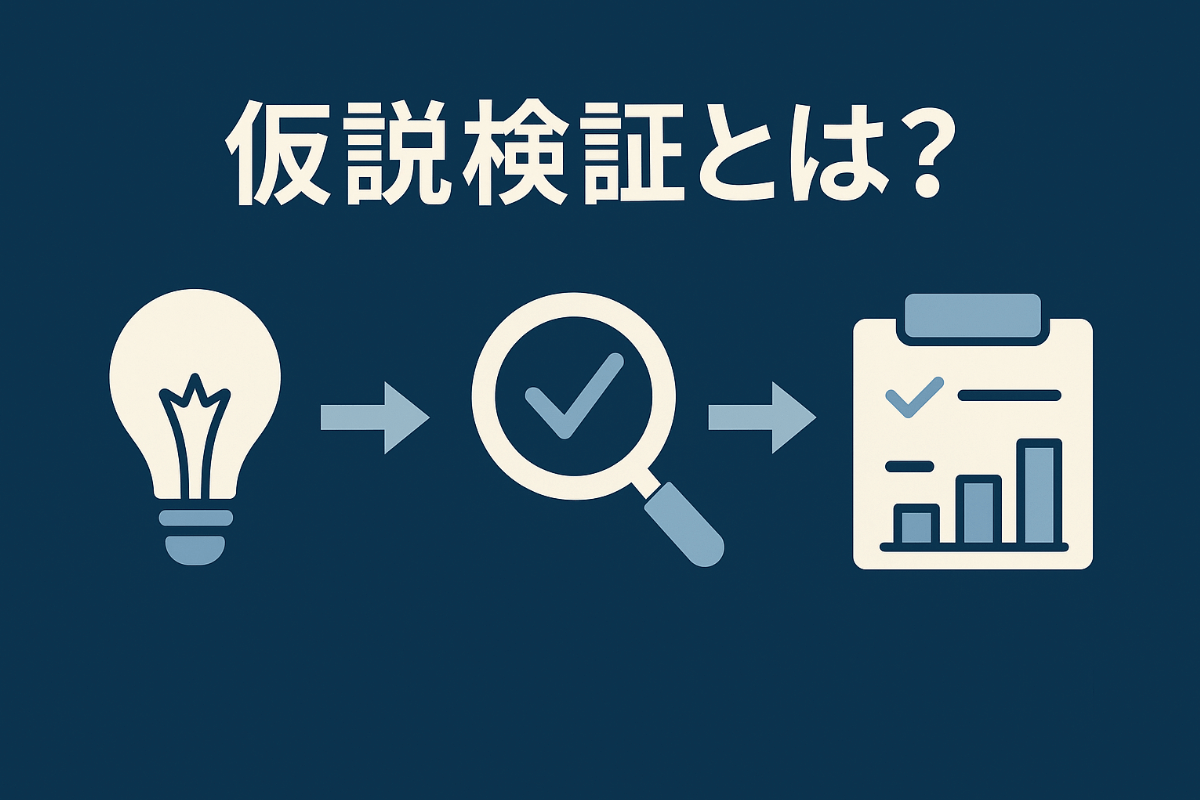企業の成長を持続させるには、既存事業の収益を維持しながらも、新たな価値を創出する新規事業の取り組みが欠かせません。しかし、両者は目的・リスク・組織体制などが大きく異なるため、同じ発想や手法で運営しようとすると、さまざまなギャップに直面してしまいます。新規事業は不確実性の高い環境で仮説検証を繰り返し、スピード感のある判断が求められる一方、既存事業は確立された体制のもと、安定性と効率性を重視して運営されるのが一般的です。
そこで今回は、こうした違いを踏まえながら、両事業をいかに共存・両立させ、さらにはシナジーを生み出していくべきかを、成功事例や実践的なポイントとともに解説します。新規事業に取り組む企業担当者の皆さまにとって、課題解決のヒントとなる内容を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
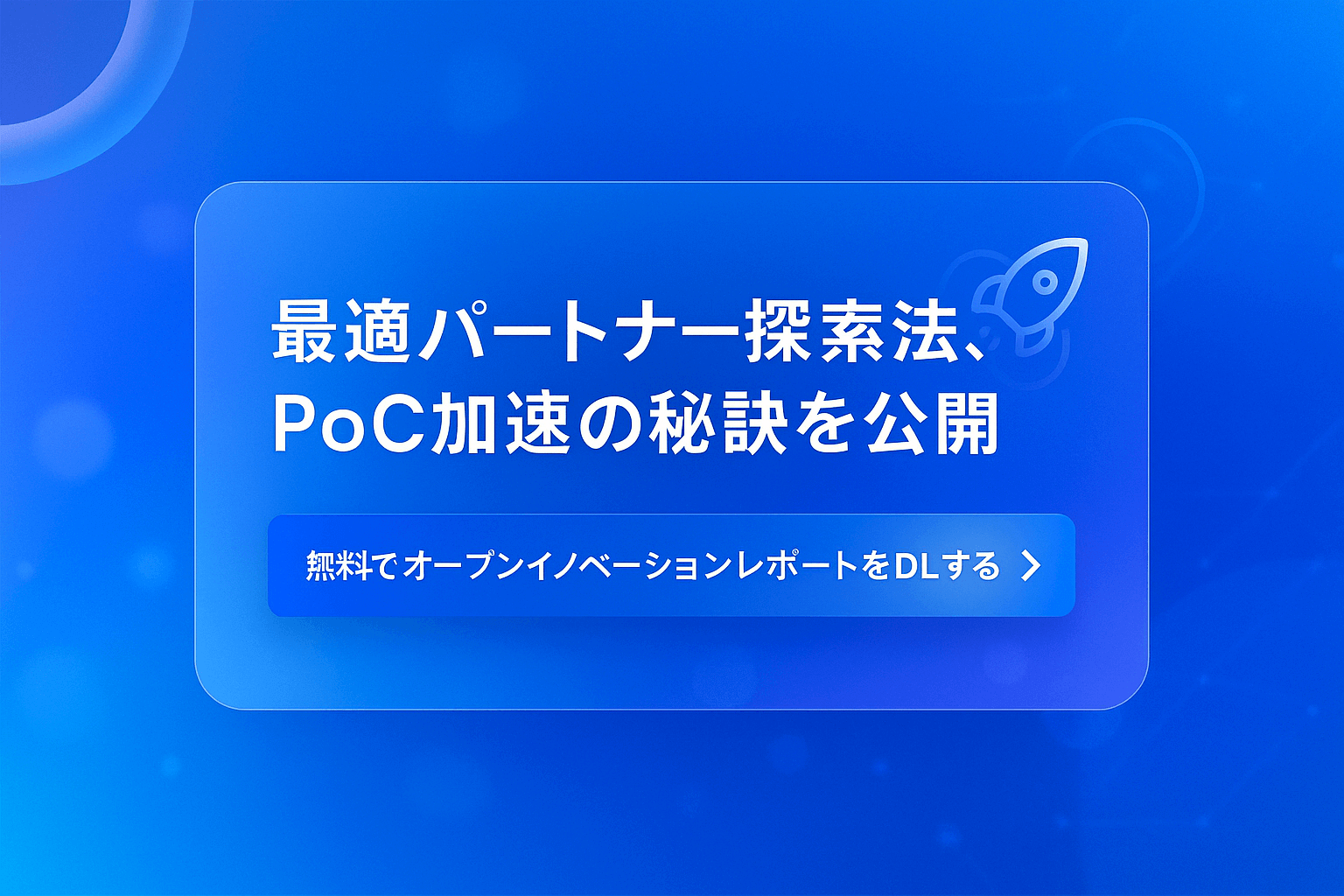
既存事業と新規事業のシナジー創出には外部連携が効果的です
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
既存事業の強みを活かしながら新規事業を成功に導く具体的な外部連携手法やシナジー創出のポイントを豊富に扱っているので、ぜひ貴社のオープンイノベーション推進にご活用ください。
新規事業と既存事業の違いとは?
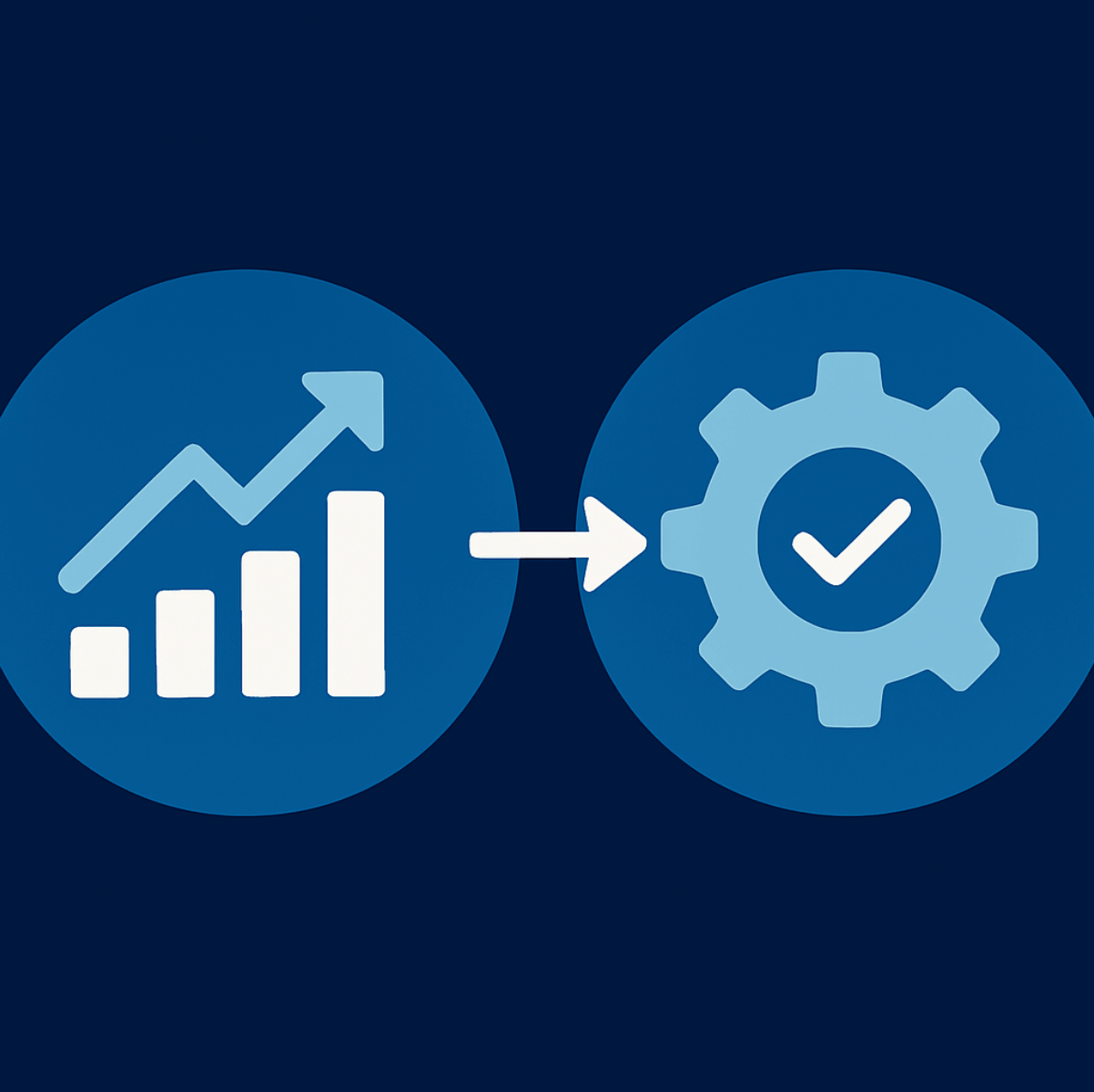
企業が持続的に成長していくためには、新規事業と既存事業の特性を正しく理解することが欠かせません。ここでは、それぞれの違いを明確に整理し、両立やシナジーを考えるうえでの土台となる視点を解説します。
目的の違い
新規事業と既存事業では、そもそもの目的に明確な違いがあります。新規事業は、未知の市場や顧客ニーズに対する仮説を検証し、新たな価値の可能性を探ることが目的です。収益化よりも、学びの深さや市場からの反応を見極める姿勢が重視され、試行錯誤の過程そのものが成果とされる点が特徴です。
一方、既存事業の目的は、確立された市場における収益やシェアの最大化です。設定されたKPIを効率よく達成することが求められ、安定した運営を維持することが最優先となります。
リスクの違い
新規事業と既存事業では、直面するリスクの性質が大きく異なります。新規事業は未開拓の市場や未知のニーズを対象とするため、不確実性が高くなりがちです。ビジネスモデルの検証段階から多くの失敗リスクを伴い、顧客獲得や収益化の見通しも立ちにくいのが実情です。そのため、仮説検証を繰り返し、リスクを一つずつ抑えていく慎重な姿勢が求められます。
一方で、既存事業はすでに確立された市場や顧客基盤を持つため、比較的安定した収益が見込めます。ただし、競合の増加や市場の縮小といった中長期的なリスクには常に備える必要があります。環境の変化に適応できなければ、徐々に競争力を失ってしまう可能性もあるためです。
体制の違い
新規事業と既存事業では、求められる組織体制にも大きな違いがあります。新規事業ではスピードと柔軟性が重視されるため、少人数でフラットな組織が適しています。意思決定も現場主導で行われることが多く、立ち上げ期には仮説検証を迅速に繰り返せる体制が望ましいでしょう。
一方、既存事業では安定性や再現性が重視され、役割分担が明確な階層型の組織が一般的です。承認プロセスも整備されており、効率的な運営を支える基盤が確立されています。
また、新規事業ではリソースを兼任で補おうとすると、業務の進捗が鈍るケースも少なくありません。可能な限り専任体制を敷き、スピード感を損なわない運営が求められます。
業務比率のバランス
新規事業と既存事業を兼務する体制では、業務比率の調整に悩む担当者が少なくありません。SONYが行った調査では、兼務先である既存事業に多くの時間を割いていると回答した人が全体の52%を占め、新規事業に十分な時間を確保できている人は33%にとどまっています。
特に管理職層では、既存事業の運営責任が重いため、新規事業へ集中する時間を捻出しづらい傾向があります。一方で、新規事業には仮説検証や戦略立案など、まとまった時間が求められるタスクが多く、断続的な対応では成果につながりにくいのが実情です。
このような状況を踏まえると、業務比率の最適化は喫緊の課題といえます。
参考:Sony Acceleration Platform「#11 新規事業と既存事業を兼務する場合、どちらの業務比率が高い?」
新規事業と既存事業の両立・共存における課題
新規事業と既存事業を同時に推進する際には、理想と現実のギャップに直面することが少なくありません。ここでは、両立・共存を目指すうえで生じやすい具体的な課題と、その背景について詳しく見ていきます。
「食い合い」になってしまうリスク
新規事業と既存事業を両立させるうえで注意すべき課題のひとつが、「カニバリゼーション(共食い)」のリスクです。これは、新たに立ち上げた事業や製品・サービスが、既存の市場や顧客層と重なり、自社内でシェアや売上を奪い合ってしまう現象を指します。
特にターゲット層が重なる場合や提供する価値に差がない場合、社内でのリソース配分や販促の優先順位が曖昧になり、いずれの事業も成長が鈍化するおそれがあります。結果として、経営資源を非効率に消費し、企業全体の競争力が低下する可能性も否定できません。
こうしたリスクを避けるには、ターゲットの明確化と製品・サービスの差別化が不可欠です。
既存事業側の抵抗をどう乗り越えるか
新規事業の推進には、既存事業部門の協力が欠かせません。しかし現場では、「やらされ感」やリソース配分への不満から、抵抗が生まれることもあります。特に評価制度や意思決定権限が既存事業に偏ったままでは、新規事業への関与が損と捉えられがちです。
こうした状況を打開するには、まず経営層が当事者意識を持ち、企業全体にビジョンを浸透させる姿勢が求められます。そのうえで、既存事業側との連携を深めるには、共通の目標設定と役割分担の明確化が重要です。
また、両事業の橋渡し役となる人材を配置し、相互理解を促す体制づくりも効果的です。
共通資産と独立性のバランス
新規事業と既存事業の共存を図るうえでは、企業が保有する共通資産の活用と、各事業の独立性をどう確保するかのバランスも重要なテーマとなります。共通資産には、人材やノウハウ、インフラ、ブランドなどが含まれ、これらを適切に活用することで、コストの抑制や、事業立ち上げのスピードアップが期待できます。
ただし、既存事業の価値観やルールに過度に従うと、新規事業の柔軟性やスピード感が損なわれる可能性もあります。特に評価制度や意思決定プロセスについては、それぞれの事業特性に応じた設計が不可欠です。
そのため、共通資産は「必要な範囲で選択的に」活用する意識が求められます。たとえば、立ち上げ初期は既存のリソースを有効活用しつつ、事業の成長に応じて徐々に専任体制や独自のルールへと切り替えていくアプローチが効果的です。
新規事業と既存事業の両立・共存を目指すうえでのポイント
新規事業と既存事業は、目的や体制、求められる成果が大きく異なるため、両立や共存は容易ではありません。ここでは、両者の特性を踏まえたうえで、共存を実現するために押さえるべき実践的なポイントを解説します。
両者の違いを十分に理解する
新規事業と既存事業を両立させるには、まず両者の本質的な違いを正しく理解することが欠かせません。新規事業は、不確実性の高い市場を対象に、仮説検証を繰り返しながら新たな価値を見出す挑戦型の取り組みです。一方、既存事業では、確立された顧客基盤と収益モデルを活かし、効率的かつ安定的な成果が求められます。
求められる人材やスキル、組織体制、リソースの配分方法なども大きく異なるため、それぞれに適した戦略やマネジメント手法を用いる必要があります。違いを整理しないまま一括管理しようとすると、意思決定のスピードや事業成果に悪影響が及ぶ可能性もあるでしょう。
そのため、両者の特性を踏まえて、目的や役割、運営方法の違いを明確に認識し、それぞれに最適な支援体制と判断基準を設けることが重要です。
両者のバランスをどう保つべきか判断する
新規事業と既存事業のバランスを保つには、経営資源の配分や体制の柔軟性を継続的に見直し、変化に応じて適切に判断する姿勢が求められます。たとえば、新規事業の初期段階では、既存事業から人材や資金を段階的に移しながら、最小限の影響で立ち上げを進めることが理想です。
ただし、既存事業の安定性が損なわれる兆しが見られた場合には、資源配分を再調整し、企業全体の基盤を優先的に守る判断も必要です。
どちらに重きを置くべきか迷う場合は、事業同士の親和性やシナジーの有無、成長性と収益性のバランスなど、複数の観点から総合的に評価しましょう。状況によっては、いずれかに集中する「選択と集中」という戦略も効果的です。
分析に応じていずれかに振り切る判断が最適解であることも
新規事業と既存事業の両立は理想的ですが、実際には両立が難しい場面もあります。市場環境の変化や経営資源の限界、新規事業の成長ポテンシャルなどを総合的に見極めた結果、いずれかに軸足を置く判断が最適となるケースも少なくありません。
たとえば、将来的な成長が見込まれる新市場がある場合には、一定のリスクを受け入れてでも新規事業に集中投資するという選択が効果的です。逆に、既存事業の収益性が高く、市場も安定しているのであれば、新規事業への展開を控え、既存事業の深耕に経営資源を集中させる判断も合理的といえます。
新規事業と既存事業の相乗効果(シナジー)を生む仕組みとポイント
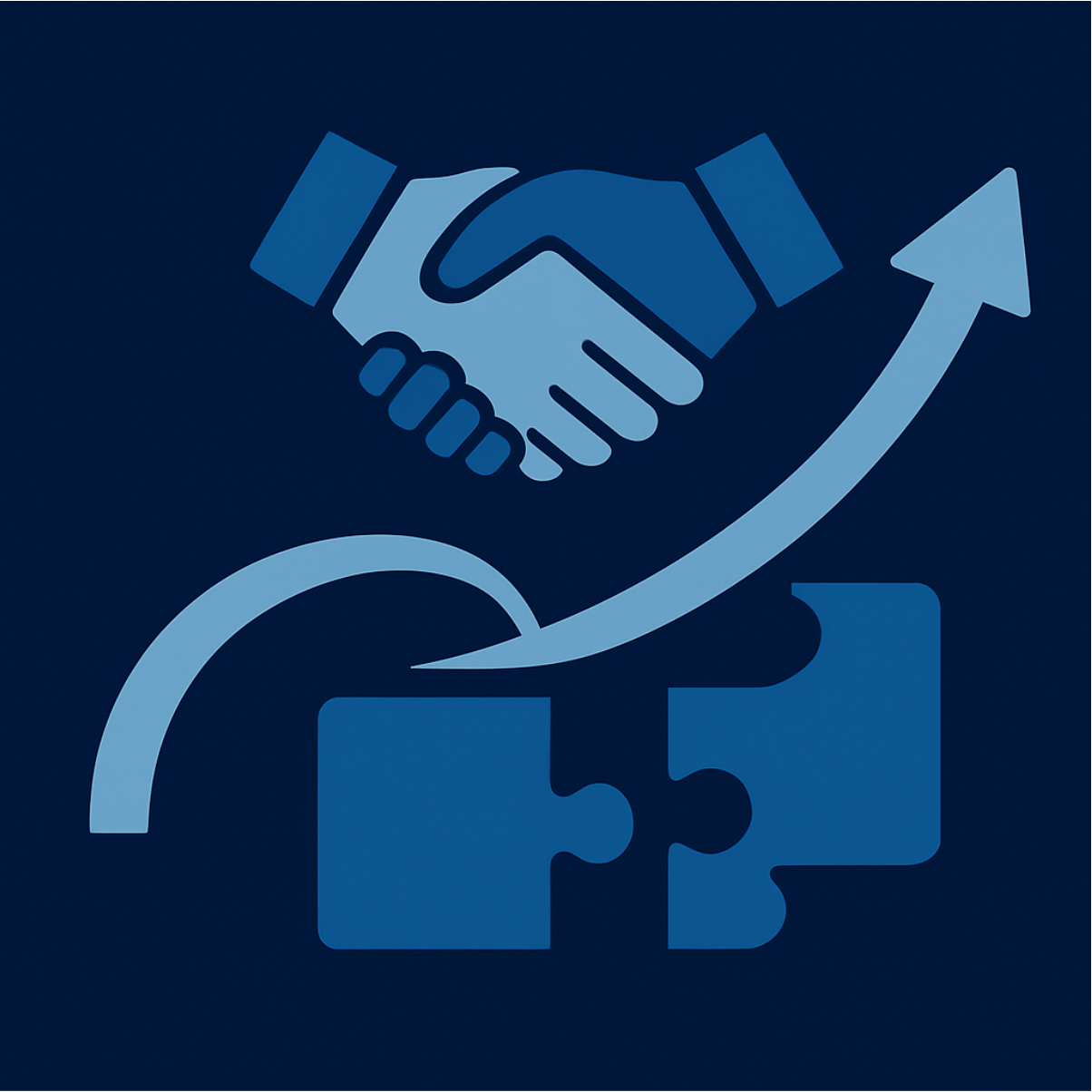
新規事業と既存事業は目的や体制こそ異なりますが、適切な設計と運用次第で、互いの強みを活かしたシナジーを生み出すことが可能です。ここでは、それぞれの事業が補完し合いながら成果を最大化するための仕組みと実践のポイントを解説します。
組織構造の分離と連携の最適解
新規事業と既存事業のシナジーを高めるには、組織構造における「分離」と「連携」のバランス設計が重要です。たとえば、出島戦略のように、既存組織の制約から切り離した独立ユニットで事業検証を行う方法は、新規事業に必要な柔軟性やスピードを確保するうえで効果的といえます。
ただし、完全に既存組織と切り離してしまうと、ブランド力や顧客基盤といった既存資産を活かしづらくなり、組織内で孤立するリスクもあります。
そこで有効なのが、「探索ユニットを物理的に分離しながらも、資源や知見を共有できる接点を意図的に設ける」というアプローチです。いわゆる「両利きの経営」と呼ばれるこの手法は、成長段階や目的に応じて連携の度合いを柔軟に調整できます。
リソースの再配分と意思決定の設計
新規事業と既存事業のシナジーを最大化するには、経営資源の再配分と意思決定プロセスの設計も重要です。特に新規事業では、迅速な仮説検証や市場適応が求められるため、既存事業と同じ仕組みでは対応が遅れやすくなります。そのため、現場が主導してスピーディに判断できるよう、意思決定の分権化が効果的です。
また、限られた人員や資金、時間をどう振り分けるかは、企業全体の戦略と一貫性を持たせることが前提となります。たとえば初期段階では、既存事業の余剰リソースを一部活用し、成長に応じて専任体制へと移行していく段階的なアプローチが効果的です。
意思決定プロセスの設計では、判断基準や責任の所在を明文化することが重要です。
KPIと評価制度の設計方法
新規事業と既存事業では、成果を測るKPIや評価制度の設計方針が大きく異なります。既存事業では、売上や利益率、業務効率といった定量指標が中心です。安定的な運営と継続的な改善が求められるため、達成度の数値管理が軸となります。
一方、新規事業は立ち上げ期にあるため、成果がすぐに数字に表れにくい特徴があります。そのため、仮説の数や検証の質、意思決定のスピードといったプロセス重視のKPI設定が重要です。早期段階では、結果よりも学びや検証の積み重ねに価値を置く設計が適しています。
また、人事評価においても配慮が必要です。短期成果のみに偏ると、挑戦的な行動が抑制される可能性があります。新規事業では、「失敗からの学び」や「主体的な行動」といった行動指標を盛り込み、挑戦を後押しする仕組みが求められるでしょう。
両者の特性を踏まえ、それぞれに適したKPIと評価軸を明確にすみ分けることが重要です。
成功事例に学ぶ|新規事業と既存事業が相乗効果を生み出した事例3選
新規事業と既存事業は対立するものではなく、うまく連携すれば互いの強みを引き出し、企業全体の成長を加速させることが可能です。ここでは、実際に相乗効果(シナジー)を生み出した企業の取り組み事例を3つ紹介します。
日清食品×D2Cブランド展開「美・健康系ドリンクのD2C進出」
日清食品は、自社ECを軸としたD2C(Direct to Consumer)戦略により、美容ドリンク市場へ新たに参入。通販限定で展開する『ヒアルモイスト』シリーズが好調に推移しています。ヒアルロン酸を生み出す特別な乳酸菌とコラーゲンを配合した同商品は、「おいしい美容ドリンク」としてSNSや口コミで話題を集め、ECチャネルにおける主力商品へと成長しました。
本事業は、社員の実体験を起点に企画が立ち上がり、SNSを活用したプロモーションや即日配送、単品注文対応など、顧客視点に立ったUXの工夫も重ねられています。こうした取り組みが功を奏し、6年間で年商は10倍に拡大。新規事業で得た学びや資産を既存ブランドと有機的に組み合わせた好事例といえます。
Komatsu(小松製作所)×IoT活用による顧客支援サービス「KOMTRAX」
Komatsu(小松製作所)は、建設機械に搭載するIoTシステム「KOMTRAX(コムトラックス)」を活用し、既存事業の強みを生かしながら新たな顧客価値の創出に成功しています。KOMTRAXは、GPSや無線通信により建機の位置情報、稼働状況、故障データなどを遠隔で可視化できるシステム。これにより、保守や省エネ支援、車両管理の効率化など、顧客に対する付加価値の提供を実現しています。
1999年に市場投入されたKOMTRAXは、2001年から国内機に標準搭載されるようになり、業界に先駆けたデータ活用型のサービスモデルとして定着しました。特に中国市場では、稼働状況の見える化によって、与信管理の材料として活用され、販売拡大にも貢献しています。
IoT技術を製品に組み込みながら、既存サービスの高度化と新規事業の推進を両立した好例といえるでしょう。
NTTドコモ×スタートアップ連携「39works」オープンイノベーション拠点の活用
NTTドコモは、スタートアップとの共創による新規事業創出プログラム「39works」を通じて、既存事業と新規事業の両立を図っています。このプログラムでは、社内外のアイデアを小さく素早く形にするため、アジャイル開発や高速PDCAを導入。これまでに41件の事業化を実現しています。
特徴的なのは、受発注の枠を超えた、対等な立場での協働体制です。「Loupe」や「embot」といったサービスは、社内の起業家と外部パートナーがチームとなり、企画から運用までを共同で推進。ドコモブランドに依存せず、実際の市場での検証を重ねてきました。
また、成果が見込めない場合は早期撤退も可能とする「ステージゲート方式」を採用しており、迅速な意思決定と失敗からの学びが組織に蓄積される仕組みも整えています。
新規事業を既存組織に組み込むときの注意点
新規事業を既存組織に組み込む際には、両者のスピード感や意思決定プロセスの違いに注意が必要です。ここでは、統合を円滑に進めるための具体的な注意点を解説します。
成長スピードと意思決定のズレ
新規事業と既存組織の間には、意思決定に対するスピード感の違いから、しばしばギャップが生じます。新規事業では、不確実な市場に対して仮説検証を重ねる必要があり、迅速な判断と柔軟な対応が欠かせません。一方、既存組織は安定した運営を優先するため、リスク管理や承認プロセスが重視され、判断が慎重になる傾向があります。
このような違いがあることで、新規事業側で早急に意思決定したい案件が社内稟議で停滞したり、スピード感を求める現場と慎重な経営層の間で温度差が生じたりすることもあります。ズレを放置すると、意思決定の遅れによって機会損失が発生し、現場のモチベーション低下につながるおそれもあります。
こうした課題に対応するには、新規事業専用の意思決定プロセスを設け、現場に権限を委譲する体制を作ることが重要です。
トップダウンと現場主導のバランス
新規事業を既存組織に組み込むうえで、トップダウン(上意下達)とボトムアップ(現場主導)のバランスは非常に重要です。トップダウンは全社的な方針の統一や迅速な意思決定に強みがありますが、現場の実情に応じた柔軟な対応には不向きな面もあります。一方で、ボトムアップは現場の創意工夫や課題意識を反映しやすいものの、意思決定の遅れや方向性のばらつきといった課題を招く可能性があります。
そのため、理想的なのは「経営層が方向性を示し、現場が自律的に動ける仕組み」を整えることです。たとえば、トップがビジョンや戦略を明確に伝えたうえで、現場には一定の裁量とリソースを与え、実行段階での柔軟性を尊重する体制が求められます。
また、経営層と現場が双方向に意見を交わせる環境を整えることで、認識のズレを埋めることができます。
戦略に応じた「ポートフォリオ思考」のすすめ
新規事業を既存組織に組み込む際には、「事業ポートフォリオ思考」を取り入れることが効果的です。これは、複数の事業を資源配分の視点から俯瞰し、それぞれの成長性・収益性・戦略的意義を比較・評価する考え方です。
特に新規事業は立ち上げ初期に成果が見えづらく、既存事業と同じ指標で評価すると過小評価されやすい傾向があります。そのため、BCGマトリクスやAnsoffの成長マトリクスなどを活用し、「短期の収益柱」「中長期の成長ドライバー」「戦略的探索枠」といったカテゴリーごとに事業を整理しておくとよいでしょう。
各ポジションに応じたKPIとリソース配分を設計することで、経営判断の透明性が高まり、組織全体で新規事業を支える体制を構築しやすくなります。
新規事業と既存事業の関係を最適化し、持続的成長へつなげよう!
新規事業と既存事業は、目的・リスク・組織体制といった多くの面で性質が異なるため、単純に同一の枠組みで運営することは困難です。組織構造の設計、KPIのすみ分け、リソース配分の最適化などを戦略的に進めることで、企業全体の持続的成長に結び付けることが可能となります。
さらに、新規事業の創出・協業を加速させたい企業様には、経済産業省後援の「イノベーションリーダーズサミット(ILS)」が提供する〈オープンイノベーションレポート2024〉のご活用をおすすめします。国内最大規模のマッチングイベントの実績や最新の成功事例、人気スタートアップの傾向などを網羅的に把握できるうえ、〈個別説明会〉では貴社のニーズに応じた協業ノウハウも詳しく学べます。ぜひこの機会に、未来志向の新規事業推進に向けた一歩を踏み出しましょう。
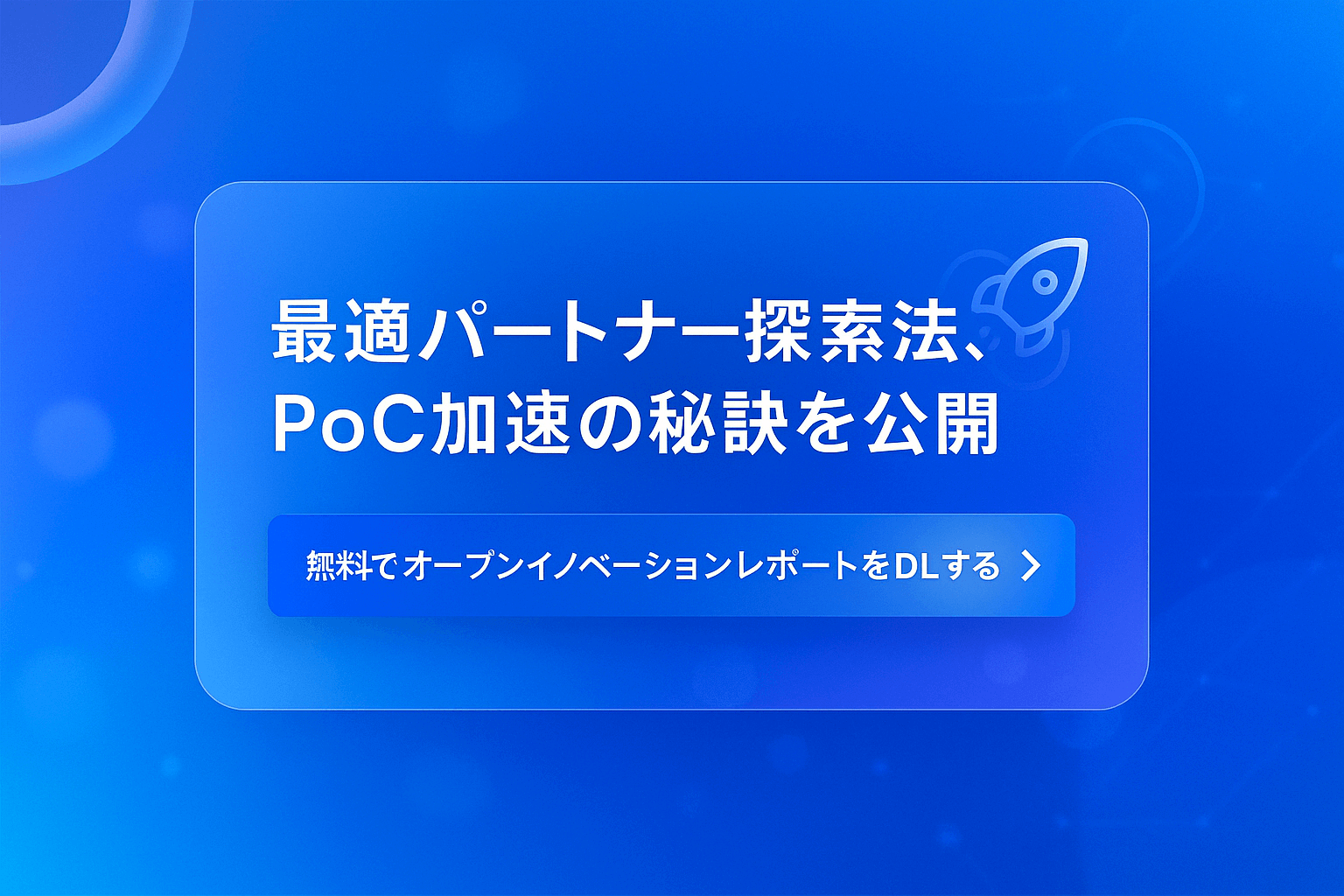
既存事業と新規事業のシナジー創出には外部連携が効果的です
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
既存事業の強みを活かしながら新規事業を成功に導く具体的な外部連携手法やシナジー創出のポイントを豊富に扱っているので、ぜひ貴社のオープンイノベーション推進にご活用ください。