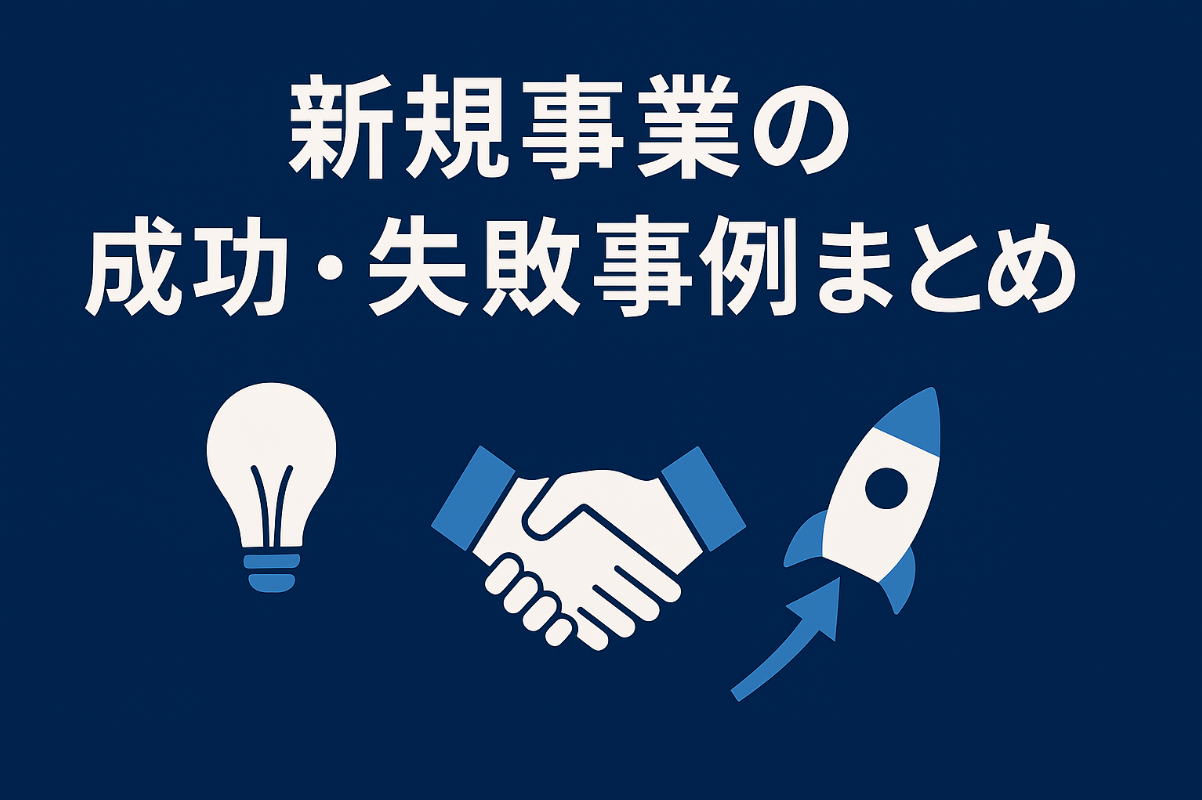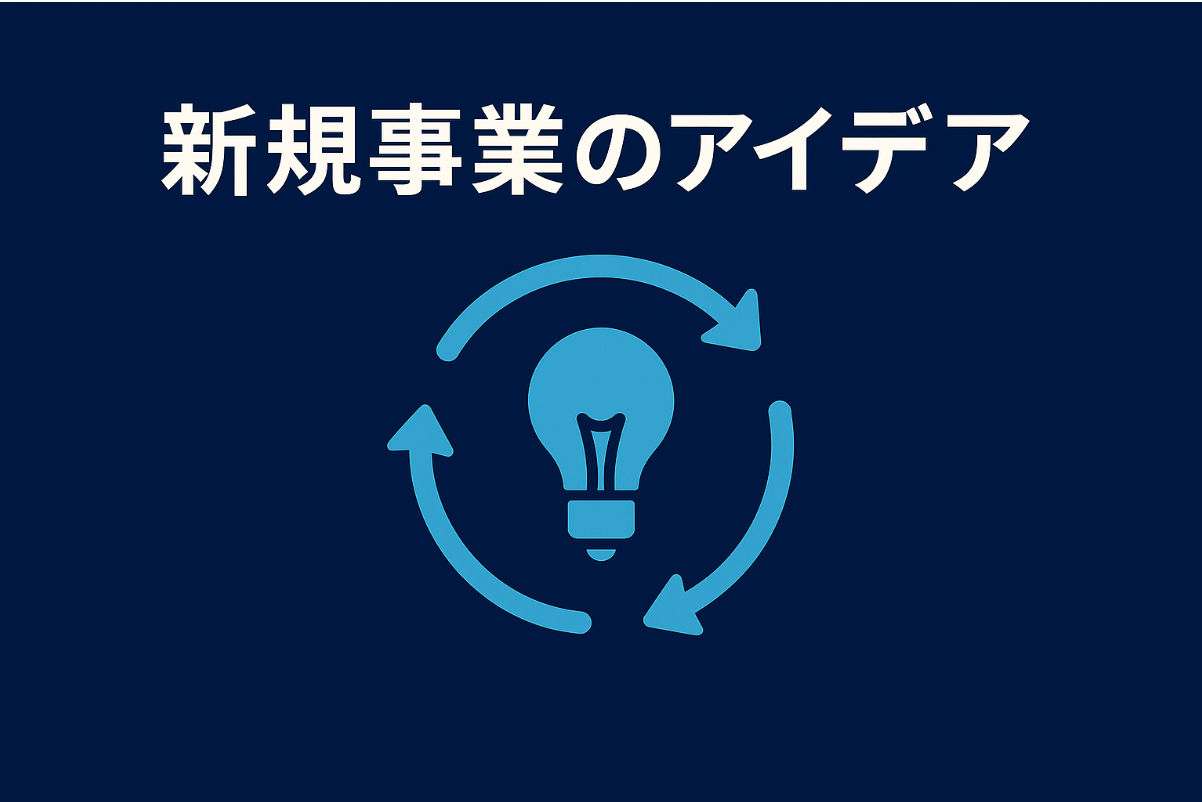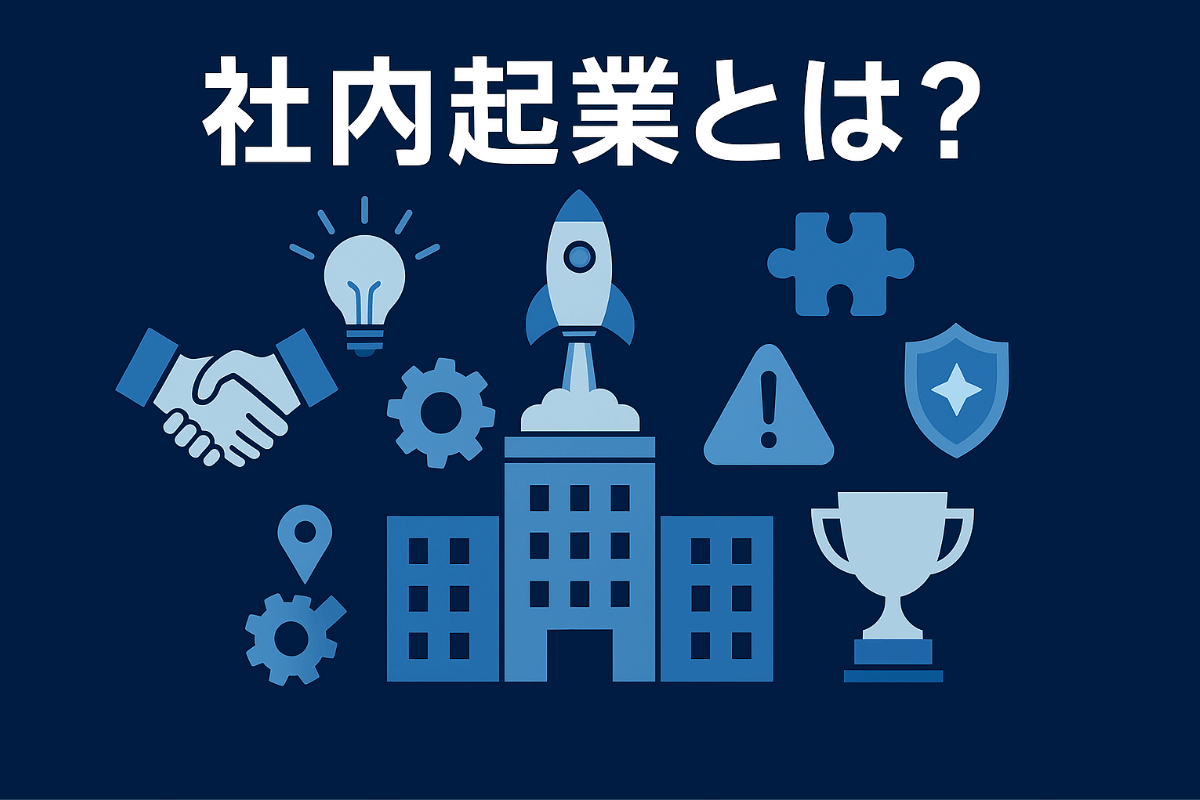変化の激しい現代において既存事業だけに依存していては、市場環境の変化や技術革新、社会課題への対応に遅れをとるおそれがあります。持続的な成長を遂げるためには、新規事業の創出がますます重要になっています。
とはいえ、新規事業の立ち上げには多くのリスクや不確実性がともないます。そのため、成功企業の事例や失敗から学ぶことは、実践に役立つヒントを得るうえで非常に効果的です。
そこで今回は、大手企業やスタートアップによる新規事業の成功・失敗事例を通じて、進め方やアイデアの見つけ方、立ち上げのステップまでを網羅的に解説していきます。新規事業に取り組む際の実践的なポイントを整理したい方は、参考にしてみてください。
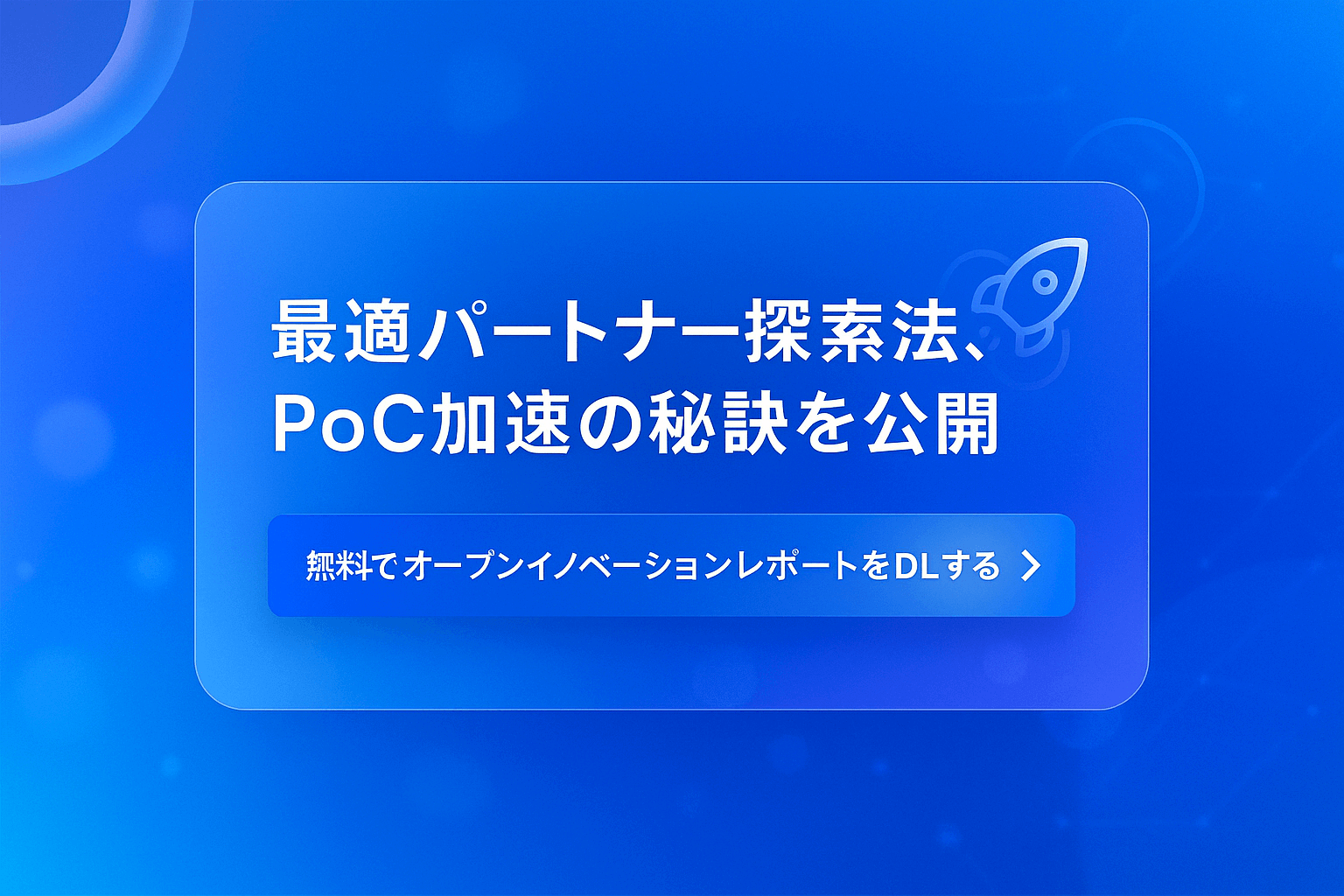
新規事業の成功確率を高めるには外部連携という選択肢があります
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。新規事業の立ち上げに必要な技術やノウハウを持つパートナーとの具体的な連携方法や成功のポイントを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の新規事業推進にご活用ください。
新規事業とは? 定義と重要性をおさらい
ここでは、新規事業の定義や既存事業との違い、そして企業にとっての重要性についてあらためて整理します。
新規事業の定義と既存事業との違い
新規事業とは、企業がこれまで関与してこなかった市場や技術分野に挑戦し、新たな収益源の創出を目指す取り組みです。既存事業が、安定した売上や利益を維持することに重点を置くのに対し、新規事業は変化する市場ニーズへの対応や、将来的な成長機会の確保を目的としています。
両者の違いは多岐にわたります。たとえば組織構造の面では、既存事業は効率性を重視した階層的な体制で運営されるのに対し、新規事業ではスピードと柔軟性を重視したフラットな組織体制が求められます。また、既存事業が確立されたターゲットやビジネスモデルに基づいて安定的に展開されるのに対し、新規事業は仮説の構築と検証を繰り返す、探索型のアプローチが特徴です。
なぜ今、新規事業が求められているのか?
現代は「VUCA時代」と呼ばれるほど、ビジネス環境の不確実性が高まっています。AIやIoTの進化、商品ライフサイクルの短期化、脱炭素に向けた規制の強化、パンデミックによる生活様式の変化、国際情勢の不安定化など、既存事業の安定性を脅かす要因は多岐にわたります。
このような状況下で、従来の収益モデルに依存し続けるだけでは、企業の持続的な成長は困難でしょう。新たな市場や価値を創出する「新規事業」への取り組みが、これまで以上に重要です。
新規事業の成功事例とその背景

変化の激しい市場環境の中で、数々の企業が新規事業に挑み、成果を上げています。ここでは、大手企業からスタートアップまで、多様な成功事例を取り上げ、それぞれの背景にある取り組みや意思決定のポイントをひもといていきます。
大手企業による革新的な成功事例
市場環境の急変や技術革新が進むなか、大手企業も従来の事業モデルに依存せず、新たな価値創出に挑戦しています。まずは、写真フィルムから化粧品への転換を果たした富士フイルムや、IoT住宅を展開するパナソニック、医療分野へ進出したキヤノンなど、既存の強みを活かして革新的な新規事業を成功させた事例を紹介します。
富士フイルム「アスタリフト」|カメラから化粧品へ大胆転換
富士フイルムは、写真フィルム市場の急速な縮小を受け、2000年代以降に大規模な事業転換を図りました。その象徴的な取り組みが、化粧品ブランド「アスタリフト」の展開です。
一見すると無関係に思える分野ですが、同社は写真フィルムで培ったコラーゲン素材やナノテクノロジー、抗酸化技術を応用し、高機能なスキンケア製品を開発しました。
なかでも、ナノ化したアスタキサンチンの浸透技術は大きな注目を集めています。当初は社内から驚きや不安の声も上がりましたが、「第二の創業」と位置づけ、全社を挙げて新規事業に取り組んだ結果、アスタリフトは同社ヘルスケア事業の中核ブランドに成長しました。
パナソニック「HomeX」|IoT住宅プラットフォームの展開
パナソニックは、AIやIoTを活用した次世代型住宅プラットフォーム「HomeX」を立ち上げ、住空間のあり方を根本から見直す挑戦を進めています(※HomeXは2025年12月末を目途にサービス終了予定。新サービスへ移行予定)。
従来の家電や住宅設備は、購入時が価値のピークとされてきました。しかし、HomeXではソフトウェアによる機能を通じて、暮らしの質が時間とともに高まる「進化するくらし」を実現しています。
このプラットフォームはオープン設計を採用し、スタートアップなどの外部パートナーとの共創によってサービスを拡充しました。実証モデルとして展開された都市型IoT住宅「カサート アーバン」では、HomeXを中心とした体験型空間が実現されています。
キヤノン「メディカル事業」|ヘルスケアへの事業多角化
キヤノンは、カメラやプリンターといった映像・印刷機器分野にとどまらず、ヘルスケア分野への本格的な参入を進めています。その中核を担っているのが、CTやMRI、X線診断装置などを手がけるキヤノンメディカルシステムズです。近年では、AIや3D技術を活用した画像解析ソリューションに加え、電子カルテなどの医療ITシステムへと提供領域を広げています。
2022年には、ヘルスケアIT事業の強化を目的に、病院情報システムのSI機能をキヤノンITSメディカルへ統合。医師の働き方改革や、遠隔診療への対応といった課題に応える体制を整えました。
中小企業・スタートアップの成功事例
中小企業やスタートアップは、大企業にくらべて限られたリソースの中で、独自の視点とスピード感を武器に、新規事業で成果を上げています。次は、急速な市場変化に柔軟に対応し、ピンチをチャンスに変えた事例を紹介します。
株式会社ビー・ファクトリー|オンライン音楽レッスンで売上90%減からV字回復
音楽レッスン事業を手がける株式会社ビー・ファクトリーは、新型コロナウイルスの影響により、一時売上が90%減少するという深刻な打撃を受けました。そうしたなかで、顧客から寄せられた「オンラインでもレッスンを受けたい」という声をきっかけに、同社は新たな事業への転換を決断します。緊急事態宣言からわずか2ヶ月後にはオンラインレッスンを開始。広告を出していないにもかかわらず、開始直後から問い合わせが相次ぎ、全体の10〜15%がオンラインレッスンを希望するという高い反応が得られ、注目を集めました。
また、オンラインの特性を活かすことで地域問わず生徒を受け入れられるようになり、新たな顧客層の開拓にもつながっています。
日本郵政×Yper株式会社|置き配バッグ「OKIPPA」でラストワンマイルの課題を解決
日本郵政は、新たなラストワンマイルの課題解決を目指し、Yper株式会社と連携して置き配バッグ「OKIPPA」の導入を進めました。再配達の負担が社会問題となるなか、OKIPPAは盗難対策機能を備えた折りたたみ式バッグとして注目されており、不在時でも安心して荷物を受け取れます。
設置工事が不要で価格も手頃な点から、日本郵政は宅配ボックスの設置が難しい集合住宅にも対応可能な配送ソリューションとして活用を推進。また、専用アプリを通じて配送状況の可視化が可能となり、利用者と配達員双方の負担軽減や業務効率化にもつながっています。
新規事業の失敗事例と主な原因
新規事業には夢や期待が込められる一方で、多くの企業が失敗という現実に直面しています。ここでは、実際の失敗事例をもとに、新規事業がつまずく主な要因を明らかにしていきます。
市場ニーズとのミスマッチによる失敗
新規事業が失敗する原因のひとつに、市場ニーズとのミスマッチが挙げられます。社内で高く評価されたアイデアであっても、実際の顧客が求める価値とズレていれば、市場で受け入れられることはありません。
たとえば、技術的に優れた製品であっても、使い勝手が悪かったり、手間がかかると感じられたりすれば、ユーザーの利用意欲は下がってしまうでしょう。
社内体制・意思決定プロセスの問題
新規事業の失敗要因として見落とされがちなのが、社内体制や意思決定プロセスの不備です。とくに、責任の所在が曖昧なままプロジェクトを進めると、重要な判断に時間がかかり、適切なタイミングを逃すリスクがあります。
新規事業には、フラットで俊敏な組織体制と、現場主導で迅速な意思決定を可能にする仕組みが求められます。
リソース不足・スピード感の欠如
新規事業が失敗に陥る要因として、リソース不足とスピード感の欠如も見逃せません。既存事業と兼務する体制では、担当者が十分な時間や人材を確保できず、検証や改善のサイクルが停滞しがちです。
さらに、社内の承認フローが複雑なままでは、意思決定に時間を要し、市場の変化に迅速に対応できません。このような状況では、競合他社に先を越されるリスクも高まります。
成功率を高めるには、専任チームを設置して機動力を確保するとともに、意思決定の権限を現場に委ねることが重要です。
戦略不在・検証不足による撤退事例
新規事業の失敗要因としてよく見られるのが、明確な戦略を持たずに進めてしまうケースです。とくに、初期段階で仮説の構築や検証を十分におこなわないまま進行すると、顧客ニーズや市場の実態と乖離したままプロジェクトが進み、早々につまずくリスクが高まります。
たとえば、十分な市場調査をおこなわずに事業を立ち上げた結果、需要が見込めなかったり、競合との差別化が図れなかったりすれば、継続は困難になります。さらに、収益モデルが不明確なまま開始すると、コストばかりがかさみ、売上が追いつかずに撤退を余儀なくされることもあるでしょう。
こうした失敗を防ぐには、段階的な検証と戦略的な意思決定が欠かせません。
新規事業の成功事例に共通する4つのポイントとは?
新規事業の成功は、単なるアイデアや資金力だけでは不十分です。ここでは、顧客視点の徹底や既存資産の活用、段階的な検証体制、社内外の巻き込み体制といった、成功企業に共通する4つのポイントを詳しく解説します。
顧客起点で課題を捉えたプロダクト設計
顧客起点で課題を捉えるプロダクト設計は、新規事業を成功に導くうえで重要な視点です。多くの企業がつまずく要因のひとつに、顧客ニーズの見誤りがあります。その背景には、企業側の論理だけで課題を定義してしまう傾向が見られます。
重要なのは、実際の顧客の言動や行動、利用環境に目を向け、真の課題を丁寧に掘り下げることです。たとえば、「移動手段が欲しい」という表層的なニーズの奥に、「手間なく人と会話したい」といった本質的な動機が潜んでいるケースもあります。
このような気づきを得るには、ユーザーインタビューを通じた仮説検証が効果的です。さらに、デザイン思考やリーンスタートアップの手法を組み合わせることで、顧客にとって本当に価値あるプロダクトの設計が可能になります。
既存資産・強みの活用によるレバレッジ
既存の資産や強みを新規事業にレバレッジ(小さな力で大きなものを動かす仕組み)することで、成功の確率を高めながら、コストやリスクをおさえることが可能です。たとえば、技術力やブランド力、販売チャネル、顧客基盤といった既存のリソースは、新たな価値提案の基盤として活用できます。
代表的な例として、前述の富士フイルムが写真フィルムの技術を応用し、化粧品分野に「アスタリフト」を展開したケースが挙げられます。また、パナソニックやキヤノンも、自社の得意分野を活かして異業種へと事業領域を拡大し、新たな成長の柱を築いてきました。
こうした成功には、自社の資産や強みを正確に棚卸しし、それを異なる市場ニーズに合わせて転用・再定義する姿勢が求められます。
段階的な検証とスピーディな改善
新規事業の成功に欠かせないのが、段階的な検証とスピーディな改善サイクルの確立です。高い不確実性をともなう新規事業において、初期から完璧なプロダクトやサービスをつくり上げるのは現実的ではありません。そこで有効なのが、MVP(Minimum Viable Product)を活用し、最小限の機能で市場に投入して顧客の反応を確認するアプローチです。
実際の利用データやフィードバックを早期に収集することで、仮説とのズレをすばやく見極め、次の改善につなげることが可能になります。さらに、このサイクルを高速で回すためには、意思決定の迅速化と検証プロセスの簡素化が不可欠です。
社内外の巻き込みと推進体制の構築
新規事業を成功させるには、社内外の関係者を巻き込んだ推進体制の構築が欠かせません。とくに、既存事業とは異なる文化や意思決定プロセスを要する新規事業では、事業の目的やビジョンを明確に共有し、全社的な理解と協力を得ることが出発点となります。
さらに、他部署や外部パートナーとの連携によって視野を広げ、必要な知見や技術を柔軟に取り入れる姿勢が求められます。プロジェクトの推進役となるリーダーには、熱意や柔軟性に加え、関係者の利害を調整する高いコミュニケーション力が不可欠です。
新規事業アイデアの見つけ方
新規事業を立ち上げるには、まず「どのようなアイデアをもとに取り組むか」が重要な出発点となります。そこでここからは、顧客ニーズの深掘り、既存資産との掛け合わせ、業界トレンドの把握といった実践的な視点から、アイデア創出のヒントを紹介します。
詳細は新規事業のアイデアを生み出す方法|アイデア創出の事例やフレームワークも解説をご覧ください。
顧客ニーズから逆算するフレームワーク
新規事業のアイデアを生み出すうえでは、「顧客が本当に求めていること」から逆算して発想することが重要です。たとえば、ペルソナ分析やカスタマージャーニーマップを活用することで、顧客の生活背景や抱える課題、感情の変化を可視化できます。その結果、表面的なニーズだけでなく、より深いインサイトにも気づきやすくなります。
さらに、4C分析を取り入れることで、顧客視点から価値・コスト・利便性・コミュニケーションといった要素を最適化する思考が育まれます。こうしたフレームワークを用いることで、企業の論理ではなく、顧客の期待や体験を出発点としたアプローチが可能になるでしょう。
既存資産の活用と掛け合わせ発想
新規事業のアイデアを生み出すうえでは、自社の既存資産を見直し、異なる分野の要素と組み合わせて発想する方法が効果的です。技術やノウハウ、設備、人材、顧客基盤といった資産は、視点を変えることで新たな価値の源になります。
たとえば、前に挙げた成功事例では、富士フイルムが写真技術を応用して化粧品事業に進出し、パナソニックが家電の強みを活かしてIoT住宅の開発を進めました。このように、自社の強みと異業種のニーズを結びつけることで、独自性の高いビジネスが生まれています。
また、既存の成功事例に不足している要素を補ったり、異なるターゲット層に展開したりする「かけ算思考」も、ヒットにつながる有力な手段です。
業界トレンドや外部パートナーの活用法
業界トレンドや外部パートナーとの連携は、新規事業のアイデア創出において有力なヒントをもたらします。他業界の成功事例やスタートアップの取り組みに目を向けることで、自社内だけでは捉えきれない市場変化や技術動向を把握することが可能です。
特に、AIやIoT、脱炭素といった社会的テーマに関する技術革新は、新たなニーズや市場創出の起点となる可能性があります。また、外部パートナーとの共創を通じて、自社にない技術やノウハウを補完できれば、スピーディな事業立ち上げにもつながるでしょう。
新規事業を立ち上げるステップと実行の流れ
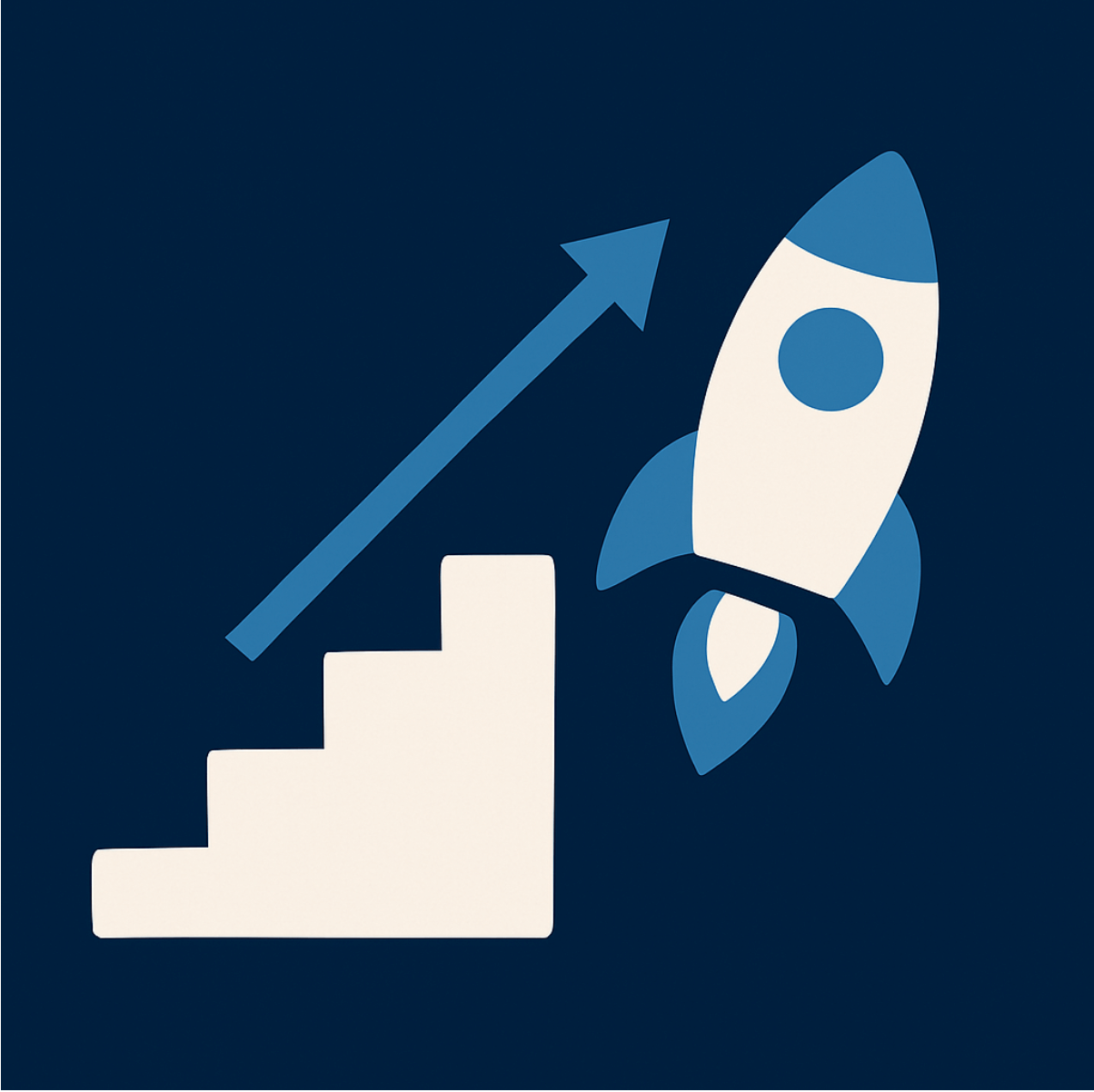
新規事業を成功に導くためには、アイデアのひらめきだけでなく、戦略的なプロセス設計と段階的な実行が欠かせません。ここでは、立ち上げ初期のステップから社内提案、ローンチ後の運用改善まで、新規事業を着実に形にするための実行フローをわかりやすく解説します。
【ステップ1】市場リサーチと仮説構築
新規事業の立ち上げでは、まず「市場リサーチと仮説構築」に取り組むことが重要です。最初のステップとして、PEST分析や競合調査をおこない、マクロ・ミクロの両面から市場環境を把握します。そのうえで、自社の強みや保有リソースと照らし合わせながら、事業機会を探りましょう。
次に、明らかになった課題やニーズに対して、「誰に、どのような価値を、どう届けるのか」という形で仮説を構築します。この仮説は、MVP(Minimum Viable Product)の開発やユーザー調査など、今後の検証プロセスにおける指針となります。
【ステップ2】アイデア検証とMVP開発
新規事業を成功に導くには、構想段階のアイデアが実際のニーズと合っているかを早期に見極めることが重要です。その手段として有効なのが、MVPの開発です。
MVPとは、コアとなる価値を最小限の機能で体験できる製品のことです。ランディングページや簡易的なサービス提供を通じて、ユーザーの興味や利用意欲を確認できます。そこで得られた顧客の反応をもとに、仮説の妥当性を検証し、必要に応じて改善を繰り返します。
このプロセスを通じて、無駄なコストや開発リスクをおさえながら、根拠ある判断ができるようになります。
【ステップ3】社内提案・意思決定プロセス
新規事業を実現するためには、社内での的確な提案とスムーズな意思決定のプロセスが不可欠です。。まず重要なのは、MVPの開発や仮説検証によって得た成果をもとに、事業の意義や実現可能性を具体的かつ明確に伝えることです。説明は経営層だけでなく関連部署にもおこない、全社的な共通理解の形成が求められます。
さらに、既存事業とは異なる評価基準を設定し、短期的な収益性ではなく、中長期的な成長性や社会的意義を重視した判断軸を採用することも大切です。市場変化のスピードに遅れないためにも、複雑な承認フローを見直し、現場主導で柔軟な判断ができる体制を整えておくと効果的でしょう。
【ステップ4】ローンチ・初期運用・改善
事業計画の承認を経てローンチにいたった後は、本格的な実行フェーズに移ります。まずはスモールスタートでパイロット展開をおこない、実際のユーザーから得られるフィードバックを迅速に収集することが重要です。
初期段階では完成度を追求するのではなく、仮説検証と改善を前提としたスピード重視の運用が求められます。とくに、PDCAサイクルやOKRを活用して成果指標を可視化し、課題を早期に把握・対応できる体制を整えておきましょう。市場から想定外の反応があった場合には、柔軟な対応と軌道修正も重要です。
新規事業を成功に導くための5つのポイント
新規事業を成功させるには、勢いだけでは乗り越えられない多くの壁が存在します。ここでは、実際の成功事例にも共通する5つの重要ポイントを紹介しながら、持続的に成果を生むための実践的な視点を解説します。
スモールスタートでリスクを抑える
新規事業には常に不確実性がつきまといます。そのため、いきなり大規模に展開するのではなく、まずはスモールスタートで小さくはじめることがおすすめです。
スモールスタートとは、限られたリソースで事業を立ち上げ、市場の反応を見ながら段階的に規模を広げていくアプローチです。
この方法を採用すれば、初期投資をおさえつつ、ユーザーの声を反映しながら改善を重ねることができます。結果として、プロダクトの完成度を高めながら、失敗時のリスクも最小限におさえられます。また、小回りが利くため、ピボット(方向転換や路線変更)がしやすく、市場環境の変化にも柔軟に対応できます。
さらに、スモールスタートは仮説検証の精度を高めるうえでも効果的です。
検証とピボットを前提にする
新規事業には常に不確実性がともないます。そのため、最初から完璧を目指すのではなく、「仮説の検証とピボットを前提とする」姿勢が重要です。ここでいうピボットとは、当初の方針に固執せず、市場の反応や顧客の声を受けて、柔軟に方向転換する戦略的な対応を指します。
実際、多くのスタートアップは、初期のビジネスモデルから何度も軌道修正を重ねながら、PMF(Product Market Fit)にたどり着いています。小さく試し、仮説が崩れたら素早く立て直す。この繰り返しが、プロダクトの完成度を高めつつ、市場に適応するためのカギとなります。
外部の知見やリソースを活用する
新規事業を成功に導くには、外部の知見やリソースを積極的に取り入れる姿勢も重要です。自社内で完結しようとすると、発想の幅や実行スピードに限界が生じやすくなります。
外部人材やスタートアップとの共創を通じて、自社にはない専門性や視点を取り入れることで、アイデアの創出から仮説検証、事業化までのプロセスが加速されます。また、第三者の視点により、社内の固定観念やバイアスを取り払った客観的な意思決定も可能となり、戦略の精度向上にもつながります。
さらに、外部人材は即戦力として活躍できるため、限られた社内リソースで既存業務と並行して事業開発を進める場面でも効果的です。た単なる業務委託にとどまらず、得られた知見を社内に蓄積し、今後の事業活動に活かしていく仕組みづくりも重要です
社内巻き込みと意思決定のスピード感
新規事業を成功させるには、社内の関係者を早い段階から巻き込み、迅速な意思決定体制を築くことが求められます。大企業では、既存事業の承認フローや評価基準にとらわれることで、意思決定のスピードが損なわれがちです。そこで重要となるのが、経営層による明確なコミットメントと、現場の主体性を尊重したフラットな組織体制の構築です。
加えて、アイデア段階から部署を横断した対話や情報を共有することで、協力体制を築きやすくなります。スムーズな判断を実現するには、事前にキーマンとの合意形成や調整も効果的です。
中長期の成長戦略を描いておく
新規事業を一過性の取り組みに終わらせないためには、開始当初から中長期の成長戦略を構想しておくことが重要です。とくに、数年後に目指す姿を明確に描き、そこに至るまでの数値目標や成長シナリオを設定することで、事業の方向性がぶれにくくなります。
また、「全天候思考」の視点から順調な成長を前提とした計画だけでなく、成長が停滞した場合や想定外のリスクに備えた複数のシナリオも用意しておくと安心です。中長期戦略には、既存資産の活用だけでなく、新規投資や撤退ラインの設定といった財務面での判断軸も必要となります。
このように、中長期の視点を持つことで目先の成果に左右されず、継続的な改善とリソース配分の最適化が可能になります。
成功事例と失敗事例から学び、自社に活かす新規事業のヒントを得よう!
本記事では、新規事業に取り組む企業の成功・失敗事例を通じて、実行プロセス、組織体制、仮説検証の進め方など、事業を軌道に乗せるための視点を多角的に紹介しました。成功のカギは、顧客視点に立った課題設定や、既存資産の活用、段階的な検証と柔軟なピボット、そして社内外を巻き込む推進体制の構築にあります。反対に、明確な戦略やニーズ理解を欠いたまま進めた場合、早期の撤退に至るリスクも高まります。
こうした実践知を自社に取り入れるうえでは、外部パートナーとの共創も効果的です。「ILS(イノベーションリーダーズサミット)」では、大手企業とスタートアップの協業事例やマッチング戦略をまとめた【無料レポート】を提供しています。新たな事業機会を模索する方は、ぜひこのレポートを活用し、次の一手を見つけましょう。
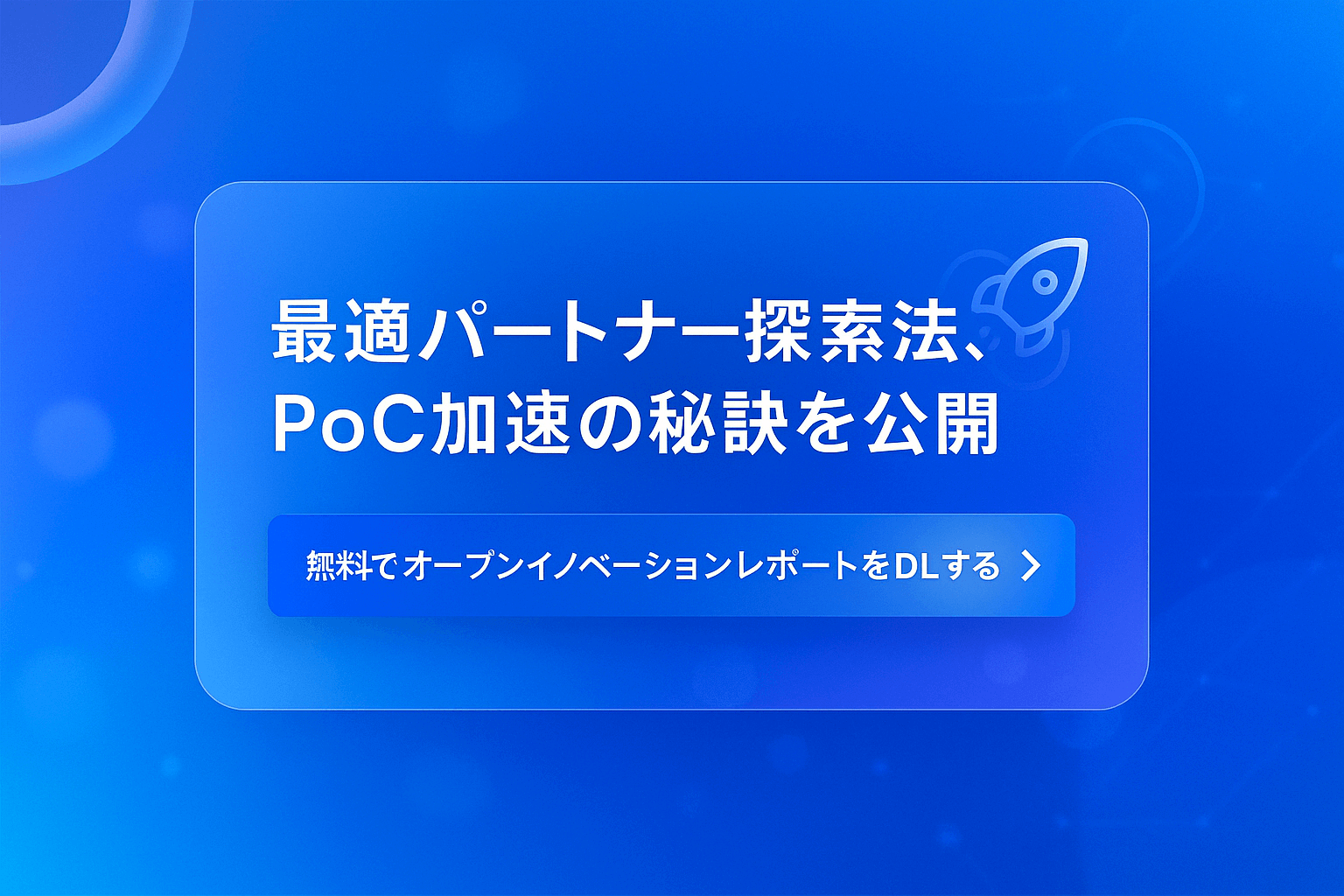
新規事業の成功確率を高めるには外部連携という選択肢があります
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。新規事業の立ち上げに必要な技術やノウハウを持つパートナーとの具体的な連携方法や成功のポイントを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の新規事業推進にご活用ください。