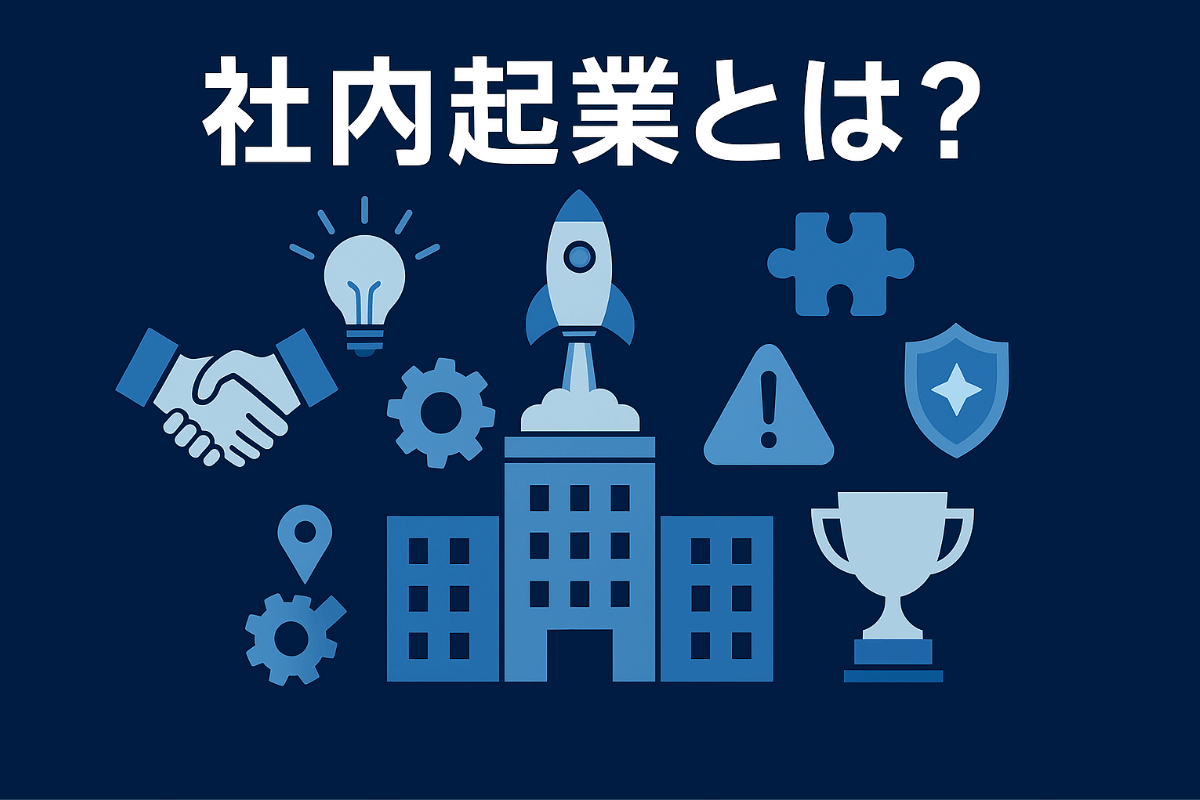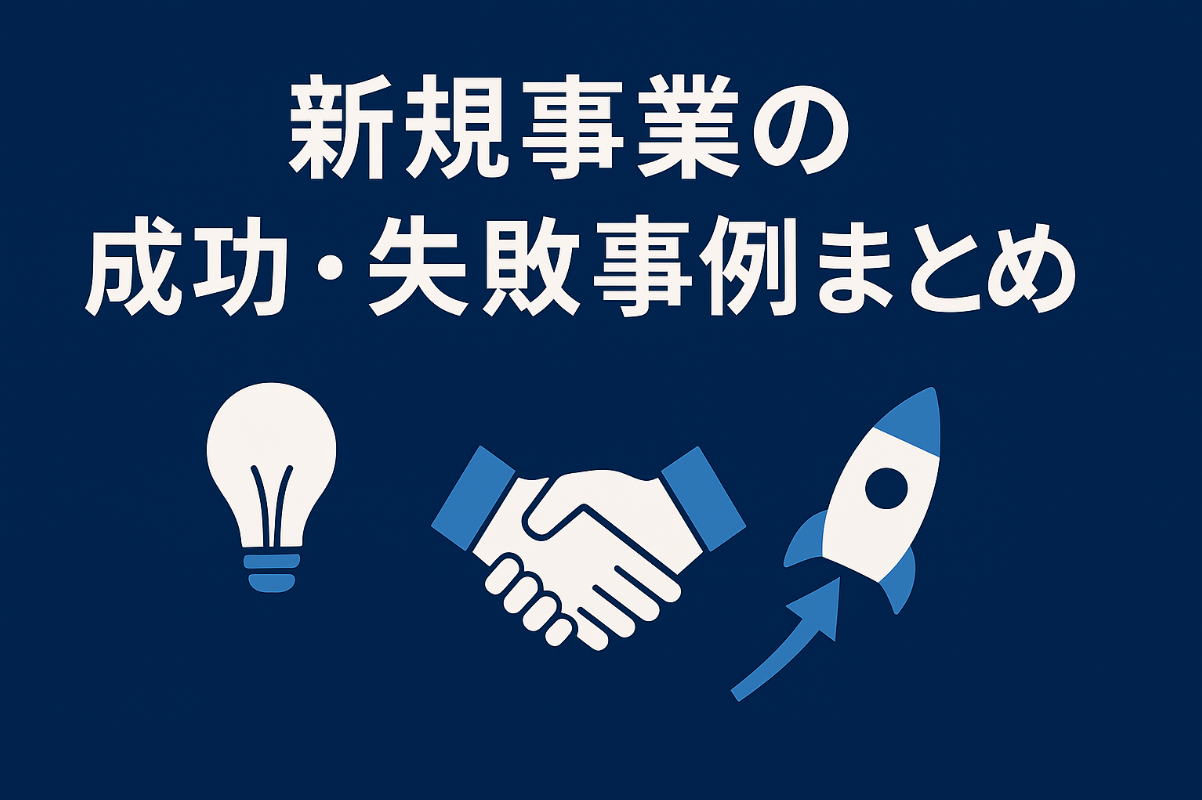企業に所属しながら、新たなビジネスに挑戦できる「社内起業制度」が注目を集めています。従業員は安定した環境のもとで、アイデアの実現に向けて挑戦できるため、独立起業に比べてリスクが抑えられるのが大きな特徴です。企業にとっても、制度を通じてイノベーションの創出や優秀な人材の流出防止、企業文化の活性化といったメリットが期待されており、導入を進める動きが加速しています。
そこで今回は、社内起業の仕組みや成功・失敗の実例、メリット・デメリット、そして実際に制度を活用する際の具体的なステップまでを詳しく解説します。制度がある企業だけでなく、制度が整っていない環境でもできるアクションも紹介していますので、自身のキャリアに新たな可能性を見出したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
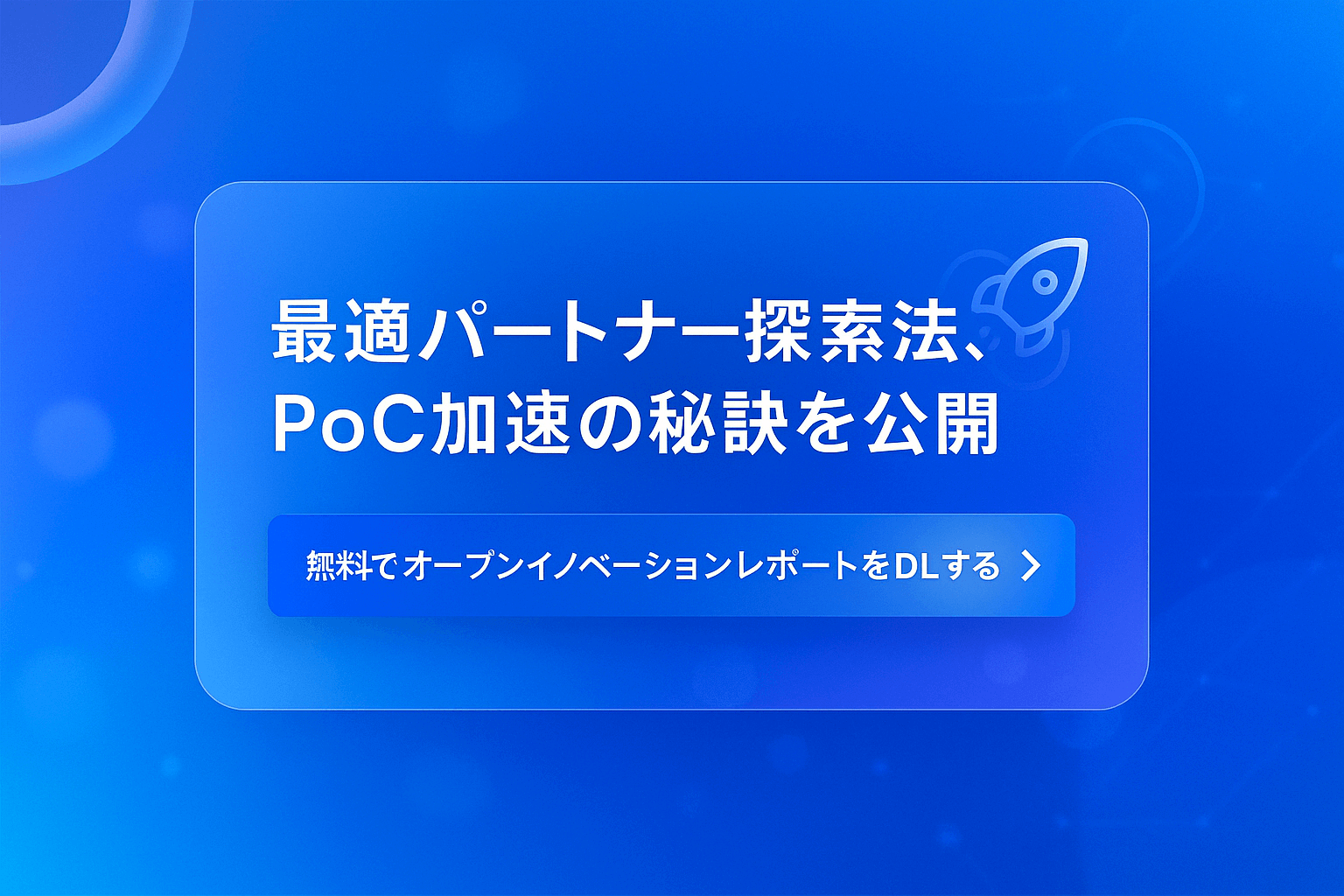
社内起業だけでなく外部連携も新規事業創出の有力な選択肢です
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
社内起業と並んで注目される外部連携による新規事業創出の具体的な手法や成功パターンを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の事業開発戦略にご活用ください。
社内起業とは?意味や仕組みをわかりやすく解説
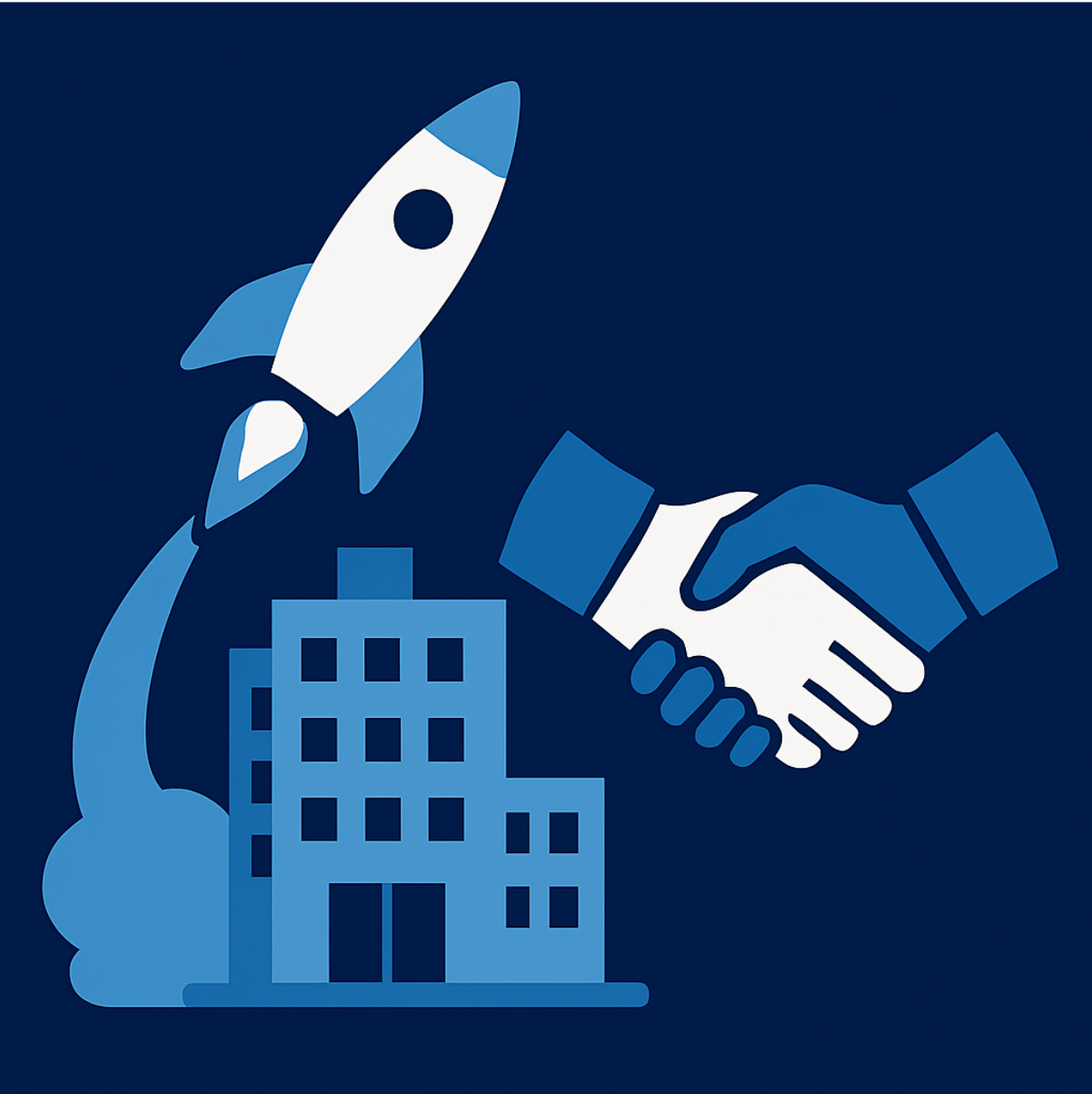
社内起業とは、企業に所属したまま新規事業の立ち上げに挑戦できる仕組みです。既存の資金やノウハウ、リソースを活用できるため、独立起業よりも低リスクでチャレンジできるのが特徴です。ここでは、社内起業の意味や独立起業との違い、制度の導入状況などをわかりやすく解説します。
「社内起業制度」とは
社内起業制度とは、企業内で従業員が新規事業を立ち上げる仕組みを制度化したものです。従業員から事業アイデアを募り、評価・選定された企画には、企業側が資金やリソースを提供し、別部門や子会社として起業する機会が与えられます。
従業員は企業に所属したまま起業に挑戦できるため、リスクを抑えながらイノベーションを追求できるのが特徴です。制度は主に大企業を中心に導入されていますが、近年では柔軟な組織運営を目指す中小企業でも活用が進んでいます。
起業家精神の醸成や人材育成にもつながることから、企業の成長戦略の一環として注目を集めている制度です。
社内起業と独立起業との違い
独立起業とは、会社を離れ、資金調達から人材確保、運営までをすべて自分の力で行うスタイルです。自由度が高い反面、あらゆるリスクを自身で負う必要があります。
社内起業には企業の支援があるため、失敗しても一定のセーフティネットがあり、従業員にとって挑戦しやすい環境といえます。さらに、企業のブランドやインフラを活かすことで、初期段階からスピード感のある事業展開が可能です。
ただし、意思決定の自由度や方針には企業側の制約があるため、完全に自分の裁量で進められるわけではない点には注意が必要です。
どのような企業に導入されているのか
社内起業制度は、市場の変化に柔軟に対応しながら新規事業を生み出す仕組みとして、また人材育成の観点からも注目を集め、制度を整える企業が増えています。
特に、既存の枠組みにとらわれず挑戦を歓迎する柔軟な企業文化を持つ企業に多く見られ、ITや通信、メーカー、商社など、さまざまな業種で導入が進んでいます。
また、多くの企業が「事業提案制度」や「社内公募型コンテスト」などを通じて、社員からのボトムアップによるアイデア創出を重視している点も特徴的です。
なお、実際の導入企業については、以下の「社内起業制度が活発な企業5選」で詳しく紹介します。
社内起業を導入する主な目的
企業が社内起業を導入する背景には、新たな収益源の確保やイノベーションの創出、人材育成といった多様な狙いがあります。ここでは、社内起業制度の導入によって企業が得られる主なメリットや目的について詳しく解説します。
イノベーション創出と新規事業の加速
社内起業制度の導入は、企業が継続的にイノベーションを生み出すための仕組みとして注目されています。変化の激しい市場環境において、既存事業の枠にとらわれず新たな価値を創出するには、柔軟でスピーディな事業開発が求められます。
社内起業では、従業員のアイデアを起点に新規事業の立ち上げを図ることで、企業内部から革新を生み出しやすくなるのが特徴です。さらに、社内にある人的・技術的リソースを活用できるため、外部からの調達に比べて初期投資やリスクを抑えやすく、事業化までのスピードも速まります。
こうした取り組みは、将来的な成長の原動力を社内から育てる仕組みとして、多くの企業が導入を進めています。
優秀な人材の流出防止とモチベーション維持
社内起業制度は、優秀な人材の流出を防ぎ、社員のモチベーションを高める有効な手段とされています。従業員が自らのアイデアをもとに事業を立ち上げる機会を得ることで、既存の業務にとどまらない挑戦意欲が育まれます。
このような環境は、自社内で新たなキャリアパスを描けるという可能性を提示し、他社への転職を思いとどまらせる要因にもなり得ます。また、活躍の場が広がることにより、社員一人ひとりの成長意欲が刺激され、組織全体の活性化にもつながるでしょう。
こうした制度設計を通じて、企業は採用や人材育成にかかるコストを抑えながら、人材力を持続的に高めていくことが可能となります。
企業文化の活性化・起業家的マインドの育成
社内起業制度の導入は、企業文化の活性化や起業家マインドの育成にも貢献します。従業員が自らのアイデアで新規事業に挑戦できる環境が整うことで、組織には「挑戦を歓迎する空気」が生まれ、保守的になりがちな企業風土にも変化が生じます。
挑戦を通じて従業員は経営視点を養い、実行力や判断力を高めていきます。これは経営人材の育成という観点からも大きな意義があります。
このような文化が根付けば、社内にいながら多様なキャリアを描けるという実感が育ち、社員の成長意欲や組織の活力を持続的に引き出す好循環へとつながるでしょう。
社内起業のメリットとデメリット
社内起業は、安定した環境の中で起業経験を積める点が魅力ですが、一方で企業の方針や評価制度とのズレが壁となることもあります。ここでは、従業員・企業それぞれの視点から、社内起業制度のメリットとデメリットを整理し、その活用における注意点を解説します。
従業員側のメリット・デメリット
社内起業制度は、従業員が自身のアイデアを事業化できる貴重な機会です。既存の組織に属したまま挑戦できるため、給与やリソースの支援を受けながら、経営スキルや実行力を養える点が大きなメリットといえます。たとえ失敗してもキャリアを失う可能性は低く、再挑戦しやすいことも魅力です。
一方で、企業の方針に従う必要があるため、意思決定の自由度には一定の制限があり、自主性を発揮しづらい場面もあります。また、制度の存在自体がモチベーションの維持につながらず、プロジェクトが途中で頓挫してしまうケースも見受けられます。
従業員にとってはリスクを抑えつつ挑戦できる制度である一方、主体性や責任感も強く求められる取り組みといえるでしょう。
企業側のメリット・デメリット
社内起業制度を導入することで、企業側にもいくつかのメリットがあります。まず、新たな収益源の確保や市場の拡大が期待でき、既存事業に依存しない柔軟な展開が可能になります。これにより、業績の向上や経営の安定にもつながります。
さらに、従業員の起業家精神が刺激されることで、挑戦を重視する企業文化の醸成や、将来の経営人材の育成にも貢献します。
一方で、デメリットも無視できません。新規事業が失敗した場合の資金的な損失は企業側が負担することになり、経営リスクの増加につながります。また、優秀な人材が既存事業から抜けることで、組織のバランスが崩れ、業績に影響を与える可能性もあります。加えて、意思決定のスピードや柔軟性が親会社の意向に左右されやすいという課題も見られます。
給料・報酬制度はどうなる?実際の待遇変化とは
社内起業制度における給料や報酬の仕組みは、企業ごとの制度設計によって異なりますが、一般的には「既存の給与体系に成果連動型の報酬を加える形式」が多く見られます。従業員としての雇用契約は継続されるため、一定の給与は保証されつつ、新規事業の成果に応じてインセンティブが付与される仕組みです。
事業が軌道に乗り、分社化された場合には、ストックオプションの付与や役員報酬の対象となるなど、起業家に近い待遇へ移行するケースもあります。一方で、初期段階では従来の評価制度と噛み合わず、報酬体系の不透明さがモチベーションの低下につながる懸念もあります。
企業側としては、新規事業への挑戦が正当に評価されるよう、専用の報酬制度やキャリアパスの整備が求められます。社内起業は挑戦の場であると同時に、待遇面での変化が生じやすい領域でもあるため、制度の内容については事前に十分確認しておくことが大切です。
社内起業の進め方|アイデア立案から事業スタートまでのステップ
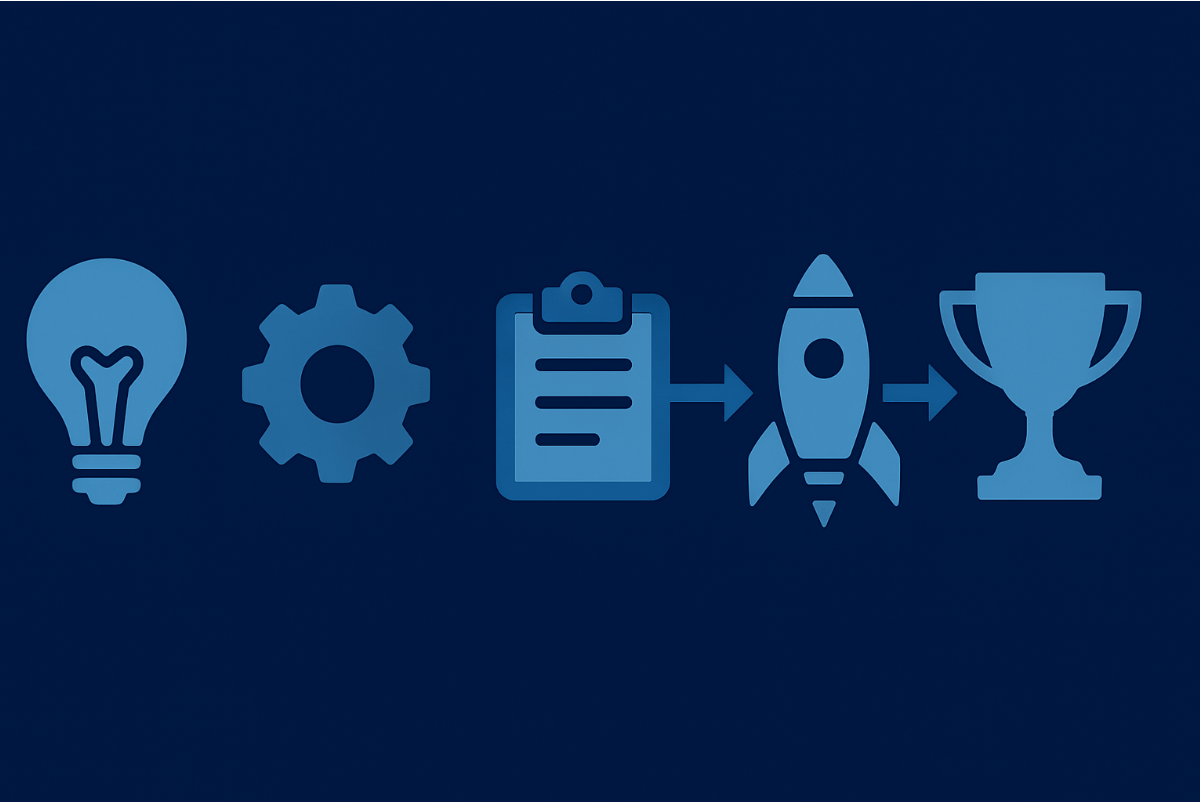
社内起業を成功させるには、単にアイデアを思いつくだけでは不十分です。課題の発見から事業化に至るまでには、段階的な準備と周到な戦略が欠かせません。ここでは、社内起業の進め方として、アイデアの立案からビジネスモデルの構築、社内提案、チーム体制の整備、そして事業の本格始動まで、具体的なステップを順を追って解説します。
STEP1|課題やニーズを見つけて事業アイデアを練る
社内起業の第一歩は、自社や市場に潜む課題やニーズを的確に見極めることです。日々の業務で感じる「不便さ」や「もっとこうしたい」といった気づきは、新たなビジネスの種になります。特に現場に近い従業員ほど、ユーザー視点で本質的な課題を捉えやすいため、日常業務からヒントを得ようとする姿勢が重要です。
また、最初から完璧なアイデアを目指す必要はありません。小さな仮説でも数多く出すことが大切とされており、初期段階では失敗を恐れず、自由な発想で積極的にアイデアを出す姿勢が求められます。周囲との対話を重ねながら、アイデアを磨いていくことが成功への近道です。身近な課題を深掘りし、そこに事業化の可能性を見出すことが、社内起業の土台となります。
STEP2|ビジネスモデルを構築し、企画書に落とし込む
ビジネスモデルの構築は、社内起業を成功へと導くための中核的なプロセスです。STEP1で得たアイデアをもとに、「誰に」「何を」「どうやって届け、どう収益を得るか」を明確にする必要があります。
この段階では、ビジネスモデルキャンバスや4P分析、5フォース分析などのフレームワークを活用し、事業の全体像を可視化します。そのうえで、競争優位性や実現可能性を多角的に検証していくことが求められます。
さらに、製品・サービスの収益性や継続性も考慮しながら、KPIを含めた実行可能な計画として企画書に落とし込むことが重要です。
STEP3|上司や関係部署に提案し、社内調整を行う
STEP2で完成したビジネスモデルと企画書は、次に上司や関係部署への提案段階へと進みます。このフェーズでは、単にアイデアの独自性をアピールするだけでなく、組織内の理解と協力を得るための「調整力」が求められます。
特に複数部門にまたがる企画では、各部署の利害や優先順位が異なることから、事前の根回しや意見交換が不可欠です。その際にポイントとなるのが、人と組織を動かす「ディープスキル」です。共通の目的意識を共有し、関係者を味方につけることで、企画の実現性は飛躍的に高まります。
さらに、提案のタイミングや伝え方にも工夫を凝らし、丁寧な対話を重ねることで、合意形成を円滑に進めることができます。それが結果として、承認プロセスのスムーズな進行につながるのです。
STEP4|承認後の準備とチーム体制の構築
承認を得たあとは、実行フェーズに向けた体制づくりが重要です。まずは、事業計画を具体的な行動レベルに落とし込み、目標やKPIをメンバー間で共有します。次に、業務を担うチーム体制を整備し、必要に応じて専任スタッフや外部人材の補強も視野に入れましょう。
社内起業では、既存部門とは異なる役割と責任が求められるため、独立した組織としての意識を持たせることが大切です。意思決定を迅速に行うためには、リーダーを中心とした権限移譲に加え、専用の予算や資源の確保も事前に整えておく必要があります。
また、事業が軌道に乗るまではさまざまな課題が予想されます。想定外の事態にも対応できるよう、柔軟なリスク管理体制や、心理的安全性を確保した職場づくりにも配慮が必要です。安定して実行に移すためには、失敗を恐れずチャレンジできる環境と、持続可能なチーム体制の構築が不可欠となります。
STEP5|小さく検証・改善を繰り返しながら本格始動へ
本格始動の前段階では、アイデアの実現可能性を見極めるために、PoC(概念実証)を繰り返すアプローチが効果的です。特に「リーンスタートアップ」の考え方に基づき、最小限の機能を備えた製品やサービスを市場に投入し、顧客の反応をもとに仮説を検証・修正していくプロセスが重視されます。
この検証フェーズでは、失敗を前提に柔軟な対応と迅速な改善を重ねていく姿勢が重要です。改善のたびに仮説と検証を繰り返すことで、提供価値の精度が高まり、ユーザーのニーズとのズレも最小限に抑えられます。
準備が整ったら、スケールアップに向けて営業やマーケティングの強化、人材体制の整備に取り組み、着実に本格展開へと移行していきましょう。
社内起業制度が活発な企業5選
一部の企業は、制度を単なる枠組みにとどめず、積極的に活用し成果を上げています。ここでは、社内起業を推進する代表的な5社を取り上げ、その制度内容や具体的な取り組みを紹介します。
リクルート
リクルートは、社内起業制度が非常に活発な企業として知られています。その中心にあるのが、1982年に始まった新規事業提案制度「Ring(リング)」です。この制度は、全従業員が自由に参加でき、既存の事業領域にとらわれないアイデアを対象としています。これまでに『ゼクシィ』『スタディサプリ』『カーセンサー』など、同社を代表する数多くの事業がここから生まれてきました。
Ringでは、複数の審査とブラッシュアップを経て事業化を目指す仕組みが整えられています。審査を通過したあとは、新規事業開発室が支援を行い、「ステージゲート方式」により段階的に予算とリソースが投入されます。
こうした制度設計と企業文化が、従業員の挑戦を後押しし、社内から次々とイノベーションが生まれる環境を育んでいます。
サイバーエージェント
サイバーエージェントは、社内起業制度を積極的に活用し、新規事業の創出を企業成長の中核に据えています。独自の取り組みとして、「あした会議」や「CAKK制度」を通じて、事業責任者や執行役員が未来志向の事業を提案・推進できる場が整備され、さらに、社内コンテスト「CA PoCMOCK CONTEST」では、エンジニアやクリエイターの視点を活かした、実現可能性の高いアイデアの育成を後押ししています。
また、各事業の成長段階に応じて資源を柔軟に再配分し、意思決定のスピードも重視しており、変化の激しいインターネット業界において、継続的な成長を実現しています。挑戦を歓迎する企業文化が社内に根付き、社内起業に適した環境が整っている企業の一例といえるでしょう。
ディー・エヌ・エー
ディー・エヌ・エー(DeNA)は、社内外からのイノベーション創出を促すため、独自の「ベンチャー・ビルダー事業」を展開しています。この取り組みでは、社員自身がプロジェクトのリーダーとなり、新規事業の立ち上げに主体的に関わる制度が整備されており、スピンアウトや独立起業を前提とした支援体制により、起業家としての成長を後押ししています。
さらに、100億円規模のファンド「デライト・ベンチャーズ」を通じて、出資やメンタリング、グローバルネットワークの提供なども実施。社員の挑戦を多角的に支える環境が用意されています。DeNAの社内起業制度は、起業家精神を育む先進的なモデルとして、注目を集めています。
ガイアックス
ガイアックスは、「人と人をつなげる」をミッションに掲げ、社内外から起業家を輩出する「スタートアップスタジオ」としての取り組みを進めています。特に注目されているのが、社員が担当事業を法人化し、株式や報酬を含めた経営権を委ねる「カーブアウト・オプション制度」です。
この制度により、社員は自社に属したまま起業家としての裁量と責任を持ち、新規事業にのびのびと挑戦できます。さらに、独立採算制や議事録の全社公開、3カ月ごとの面談など、社員が主体的にキャリアを設計できる仕組みも整えられています。
過去にはこの制度を活用して上場を果たした企業も複数あり、実績の面でも注目されています。挑戦する個人の意思を尊重し、その成長を制度として支えるガイアックスは、社内起業を志す人材にとって理想的な環境といえるでしょう。
プレックス
プレックスは、柔軟な組織運営と挑戦を歓迎するカルチャーを土台に成長を続ける企業です。社内起業制度に通じる取り組みとして、「顧客・高み・一丸」の3つのバリューを軸に、従業員の主体性と挑戦心を尊重しながら、個々の力を掛け合わせるチーム体制を整えています。
急成長する組織においても離職率を低水準に保っている点が特徴で、オンボーディングや行動指針の浸透に力を注いでいるのもその一因です。また、新規事業創出にも積極的で、物流・建設・製造といった分野ですでに成果を上げています。今後はさらなる事業の多角化も見据えています。
社員の声を取り入れながら組織を進化させる姿勢は、起業家精神を育むうえで重要です。プレックスは、社内で起業的マインドを磨きたい人にとって、理想的な環境を備えた企業の1つといえるでしょう。
社内起業で実際に成功した事例5選
社内起業制度を活用することで、企業の支援を受けながらも従業員が自らのアイデアを形にする事例が増えています。なかでも、実際に成果を上げ、事業として独立や上場を果たした成功例は、制度の有効性を裏付ける好例です。ここでは、代表的な5つの社内起業成功事例を取り上げ、それぞれがどのようにして成長を遂げたのかを具体的に紹介していきます。
モノタロウ(住友商事)
モノタロウは、住友商事の社内ベンチャーとして誕生し、後に東証一部上場を果たした成功事例です。創業者の瀬戸欣哉氏は、米国でのMBA留学中にECの可能性に着目し、帰国後に間接資材の通販事業を提案しました。2000年には、米グレンジャー社との合弁により「住商グレンジャー」として事業をスタート。
巨大なカタログをインターネット上に再構築し、少量多品種かつ即納対応のBtoBプラットフォームを構築しました。2006年に社名を「MonotaRO」に変更して以降も堅実な成長を続け、現在では営業利益率13%超の高収益体制を築いています。
社内起業制度がまだ十分に整っていなかった当時、情熱と構想力で事業を形にした瀬戸氏の取り組みは、社内ベンチャーのロールモデルとして多くの企業に影響を与えています。
スープストックトーキョー(三菱商事)
スープストックトーキョーは、三菱商事の社内ベンチャーから誕生した代表的な成功事例です。創業者の遠山正道氏は「生活に身近な仕事をしたい」という想いから、出向先の日本ケンタッキー・フライド・チキンでスープ専門店のアイデアを得ました。1999年にお台場で1号店を開業し、翌年には社内の支援と自己資金をもとに株式会社スマイルズを設立。制度がなかった当時、自らを“社内ベンチャー0号”と称し、新たな道を切り拓いた点が特徴です。
2008年にはMBO(マネジメント・バイアウト)を実施し、会社として独立。「利益予測」ではなく「スープのある生活」という物語を軸に事業を展開し、全国へと拡大していきました。企業の枠を超えて、強い意志と行動力があれば新たな価値を生み出せることを示す好例といえます。
無印良品(西友)
1980年、西友のプライベートブランドとして誕生した「無印良品」は、社内起業の成功事例として高く評価されています。立ち上げ当初は「わけあって、安い。」をキャッチコピーに掲げ、品質を維持しながらも簡素なパッケージと合理的な流通体制によってコスト削減を実現しました。この戦略が消費者の共感を呼び、開始からわずか5年で年商150億円を突破。その後も順調に事業を拡大し、1995年には運営会社である「良品計画」が株式上場を果たします。
一方で、親会社の西友は経営不振に陥り、無印良品との明暗が際立つ結果となりました。最終的には良品計画が独立し、現在では国内外に展開するグローバルブランドへと成長。既存の流通業から誕生した新たなビジネスモデルとして、社内起業の可能性を広く示した好例といえます。
スタディサプリ(リクルート)
「スタディサプリ」は、リクルートの社内起業制度「Ring」から誕生したオンライン学習サービスで、こちらも社内ベンチャーの成功例として知られています。提案者の山口文洋氏は、入社5年目に新規事業コンテスト「New RING」に応募し、グランプリを受賞。その後、社内支援を受けながら事業化が進められ、現在では小学生から大学受験生、社会人の英語学習まで幅広い層を対象としたサービスへと成長しました。
最大の特徴は、有名講師による質の高い授業を、月額プランやパック料金など自分に合った料金体系で、いつでもどこでも受講できる点です。教育の“公共料金化”を掲げ、既存の教育ビジネスの常識を覆す仕組みとして注目を集めました。リクルートの自由な社風と挑戦を後押しする企業文化が、新たな価値創出の原動力となった好例といえるでしょう。
ウエルシアケアトランスポート(ウエルシア)
ウエルシア薬局の社内起業制度「ウエルシア・ベンチャー・チャレンジ・プログラム」から生まれたのが、介護タクシー事業「ウエルタク」です。要介護者や身体に障害がある方の移動を支援するサービスで、通院や買い物など保険適用外の用途にも柔軟に対応できる「ケアタクシー」として提供されています。
2024年には「ウエルシアケアトランスポート」が設立され、2025年3月に埼玉県坂戸市で営業を開始。薬局併設の営業所を拠点に、看護師や救急救命士などの有資格者による移送サービスを展開しています。さらに、買い物代行や通院時の付き添い、訪問介護との連携など、多様なニーズに応えるサービス体制も整備。既存インフラを活かした事業連携にも取り組んでおり、地域に密着した支援が特徴です。
2025年時点では営業エリアや台数が限定的であるものの、明確なターゲット設定と医療・介護領域に強みを持つ人材活用、そしてグループ内のシナジーを意識した展開は、他の社内起業事例と比較してもユニークです。今後の事業拡大や地域貢献度によって、社内起業の成功モデルとしての評価が高まる可能性があります。
社内起業の失敗事例とその主な要因
社内起業制度は従業員の挑戦を後押しする魅力的な仕組みですが、必ずしもすべてのプロジェクトが成功するわけではありません。現実には、企画が途中で頓挫したり、組織の壁に阻まれたりするケースも多く見られます。ここでは、社内起業が失敗に終わった具体的な事例をもとに、その背後にある主な要因を解説します。
社内起業だけでなく外部連携も新規事業創出の有力な選択肢です
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
社内起業と並んで注目される外部連携による新規事業創出の具体的な手法や成功パターンを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の事業開発戦略にご活用ください。
上司や経営陣の理解不足により潰されたケース
新規事業の芽が潰れてしまう要因の1つに、上司や経営陣の理解不足があります。現場から生まれたアイデアが正当に評価されず、プレゼンテーション力や収益計画の整合性ばかりが重視される一方で、市場ニーズや顧客課題への共感が得られないケースは少なくありません。
さらに、「儲かるかどうか」という基準に偏るあまり、本質的な価値提供の視点が見落とされてしまうこともあります。こうした環境では、挑戦する側が萎縮し、組織全体のイノベーション意欲が損なわれがちです。
実際、社内で有望とされながら上司の判断で採用されず、その後に外部で成功を収めた企画も存在します。新規事業を育てるためには、トップ層の理解と支援は欠かせません。あわせて、失敗を恐れず挑戦できる企業文化の醸成も重要です。
市場ニーズの見誤りでサービスが立ち上がらなかったケース
新規事業が立ち上がらない典型的な失敗例として、市場ニーズの見誤りも挙げられます。
ある社内起業プロジェクトでは、先進的な技術や斬新なアイデアに注目し、「競合不在の独自性」を強みとして打ち出しました。しかし実際には、ユーザーが求める機能や使いやすさとは大きくかけ離れており、市場投入後も反応は低調でした。
失敗要因は、ユーザーインタビューや検証フェーズを軽視し、社内評価だけを頼りに意思決定を進めていたことです。いかに社内で注目を集めるアイデアであっても、顧客の本質的な課題に向き合えていなければ成功にはつながりません。
サービスを立ち上げる際には、徹底した市場調査に加え、小規模な検証(MVP開発)を行うことが大切です。こうした取り組みを通じて、仮説と実際のニーズとのギャップを早期に発見することが重要となります。
社内リソースの確保に失敗し、継続不能になったケース
社内起業では、リソースの確保に失敗したことで継続不能に陥るケースも少なくありません。あるプロジェクトでは、有望なアイデアが評価され、事業化に向けてスタートを切りました。しかし、必要な人材や時間を既存部門から十分に割くことができず、特に中核メンバーが本業との兼務状態にあったことで、開発や検証が後回しになってしまいました。
この遅れが致命的となり、スピード感が求められる市場環境に対応できず、競合に先を越される結果に。最終的には、撤退を余儀なくされています。社内リソースには限りがあるからこそ、立ち上げ段階から専任体制を整え、役割分担を明確にしておくことが重要です。加えて、経営層が新規事業の優先度を正しく見極め、継続的に支援する体制づくりも不可欠といえるでしょう。
実行フェーズでのスピード感不足により競合に先を越されたケース
実行フェーズでのスピード感の欠如は、社内起業における大きな失敗要因の1つです。ある企業では、アイデア段階から承認までは順調に進んだものの、実行段階に入ると社内調整や開発プロセスに時間を要し、市場投入が後手に回ってしまいました。リリース直前には競合が類似サービスを展開し、先行者利益を奪われる形に。結果として注目度は急落し、投入したリソースに見合う成果を得られないまま、プロジェクトは中止されました。
新規事業においては、スピードこそが命ともいえます。リーンスタートアップの考え方を取り入れ、最低限の機能で早期に市場へ投入し、ユーザーの反応をもとに検証と改善を重ねる体制が大切です。迅速な意思決定と柔軟な実行力が、成功を左右する重要な要素といえるでしょう。
評価制度とのミスマッチでメンバーのモチベーションが低下
社内起業においては、既存の評価制度と新規事業の性質がかみ合わず、メンバーのモチベーションが低下するケースは少なくありません。従来の制度では営業成績や定量的な成果が評価の中心となりがちですが、新規事業は成果が現れるまでに時間がかかるため、短期的な指標では正当な評価が難しい傾向があります。
その結果、挑戦したにもかかわらず十分な評価を得られず、努力が報われないと感じることで意欲を失うメンバーもいます。さらに、責任に見合う裁量や報酬が与えられない場合、不満が蓄積しやすくなります。
こうした評価のミスマッチは、社内起業の魅力を損なう要因となり、優秀な人材の流出を招くリスクも高まります。制度の形骸化を防ぐためには、新規事業に適した評価・報酬体系の構築が求められます。加えて、結果だけでなく「挑戦そのもの」を正当に評価する仕組みづくりが重要です。
既存事業との利害対立で妨害されたケース
社内起業が失敗する要因の1つに、既存事業との利害対立による妨害もあります。特に、新規事業が既存の業界構造や商慣習を根本から覆すようなモデルである場合、同じ企業内の既存部門や業界関係者から強い反発を受けることも少なくありません。
例えば、理美容機器の中古販売ビジネスを立ち上げた企業では、業界誌に広告掲載を断られたり、展示会への出展を妨害されたりと、業界からの強い圧力に直面しました。
こうした状況を乗り越えて事業を継続するには、独自の販路を開拓したり、サービスを強化したりといった柔軟な対応が欠かせません。たとえ社内での起業であっても、新規事業が既存の収益モデルを脅かす場合、足並みが揃わず内部対立に発展する恐れがあります。そのため、あらかじめ部門間の調整体制や説明責任の仕組みを整えておくことが重要です。
社内起業制度を活かして成功するためのアクションと準備
社内起業制度を活用して成功を目指すには、制度の存在を確認するだけでは不十分です。アイデアの練り方や企画の通し方、社内での立ち回り方など、具体的な準備と行動が求められます。また、制度がない場合でも実現への道はあります。ここでは、社内起業を実行に移すために必要なアクションと、その前段階で押さえておきたい準備事項について詳しく解説します。
まず確認すべき「制度の有無」と社内ルール
社内起業を目指すうえでの第一歩は、自社にその制度があるかどうかを確認することです。制度が存在する場合は、提案の受付時期や審査基準、活用できる支援内容(資金・人材・リソースなど)を事前に把握しておきましょう。
制度が整っていない企業であっても、類似の仕組みや柔軟な異動制度が導入されているケースがあります。また、制度が設けられていても、実態としては形骸化している可能性も否めません。実際に制度を利用した社員の事例や、過去の事業提案における通過率などを調べ、現実的に活用できるかを見極めることが求められます。
さらに、自社が重視している事業領域や価値観を理解し、「なぜこのアイデアを自社が手がけるべきなのか」を自らの言葉で語れるよう準備しておくことが、成功へのカギとなります。
制度を活用する場合に押さえるべきポイント
社内起業制度を実際に活用するには、制度の概要を把握するだけでなく、具体的な活用手順や社内での立ち回り方も理解しておく必要があります。まずは、提案から承認までのフローを確認し、「いつ」「どこで」「誰に」働きかけるべきかを明確にしておきましょう。
さらに、企画を通すためには、上層部の関心や企業の重点方針に合致していることが大きな判断材料になります。そのため、自身のアイデアが企業にどのような利益をもたらすのかを、説得力をもって語れるよう準備しておくことが大切です。
加えて、制度が形だけになっていないか、過去の活用実績や提案の通過率も事前に確認しておくと、現実的な判断がしやすくなります。制度の存在に頼るのではなく、自ら動き、実現へと導く意志と行動力が問われます。
制度がない場合に取れる選択肢とは?
制度が整備されていない企業であっても、社内起業への道が完全に閉ざされているわけではありません。まず注目したいのは、既存制度に代わる「事業提案制度」や「社内公募型コンテスト」の有無です。これらを活用すれば、アイデアを上層部に届ける手段として機能します。
また、柔軟な人事異動制度を活用し、関連部署への異動を通じてプロジェクトの実現に近づける方法も有効です。制度が一切存在しない場合でも、既存業務の枠内で新規性のある施策を打ち出し、小規模な検証を積み重ねることで、上層部の関心を引くことができます。
さらに、制度そのものの新設を提案するというアプローチもあります。社内起業が企業にもたらす利益や意義を丁寧に示し、制度化に向けて働きかけることで、自ら挑戦の場をつくり出すことも可能です。
社内起業は「会社にいながら挑戦できる」新しいキャリアの選択肢
社内起業は、従業員が企業に所属したまま新たな事業に挑戦できる仕組みとして、近年ますます注目を集めています。既存のリソースを活用しながら、イノベーション創出やキャリア開発に貢献できる点が大きな魅力です。挑戦を社内で叶えたい方にとって、本制度はキャリアの新しい可能性を切り開く選択肢といえるでしょう。
なお、具体的な事例や最新のマッチングトレンドを知りたい方は、オープンイノベーションに積極的な大企業とスタートアップの連携実績をまとめた「オープンイノベーションレポート2024」もぜひご参照ください。次なる一歩を踏み出すヒントが見つかるはずです。
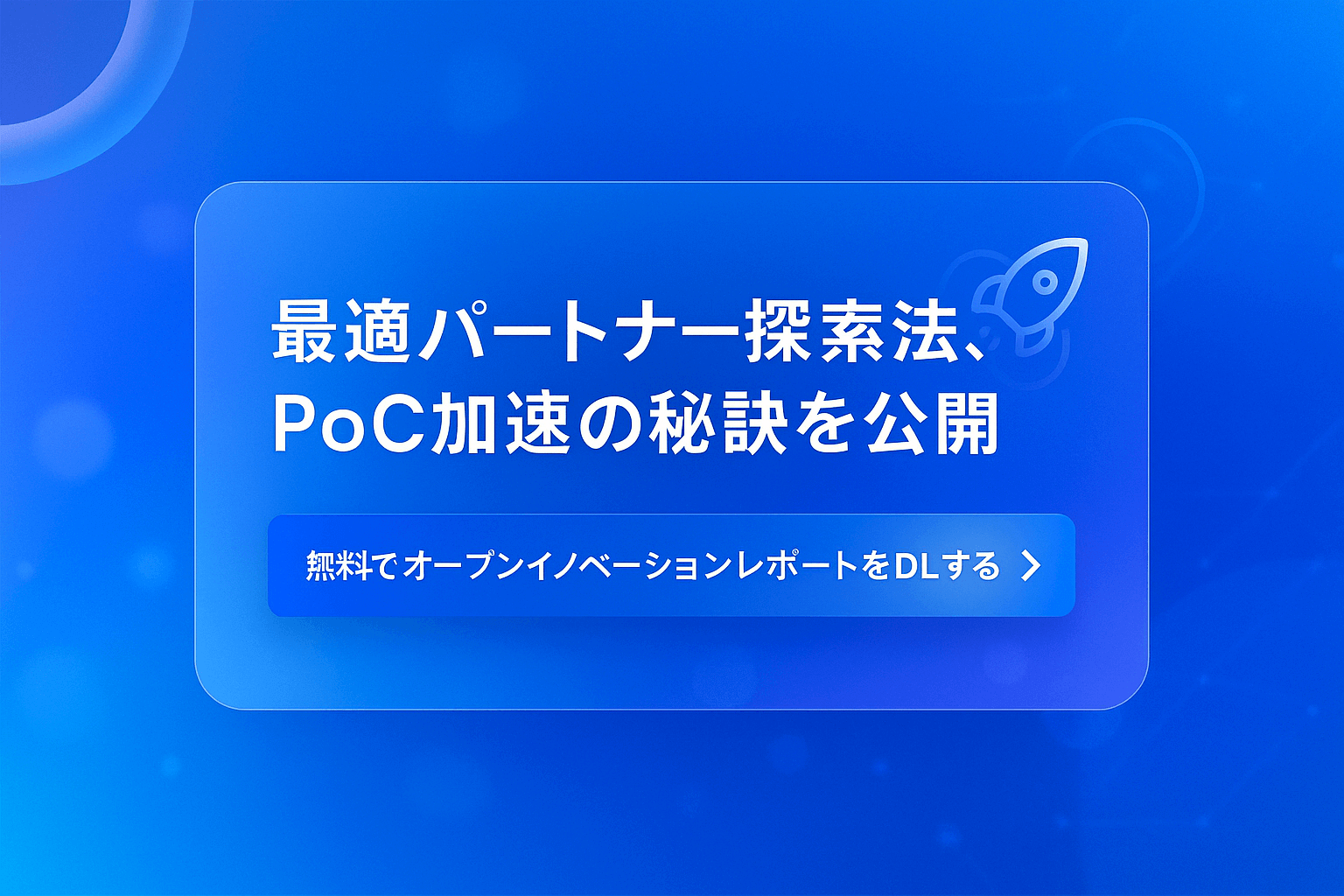
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
社内起業と並んで注目される外部連携による新規事業創出の具体的な手法や成功パターンを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の事業開発戦略にご活用ください。