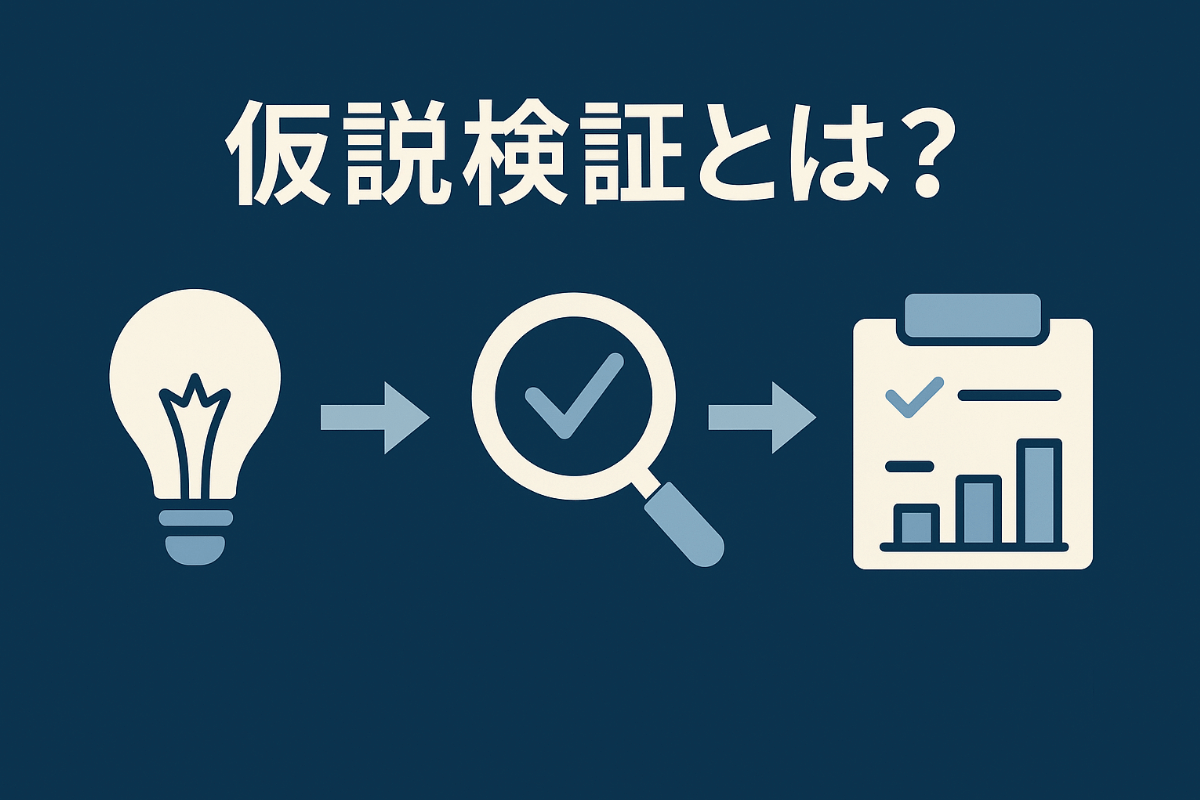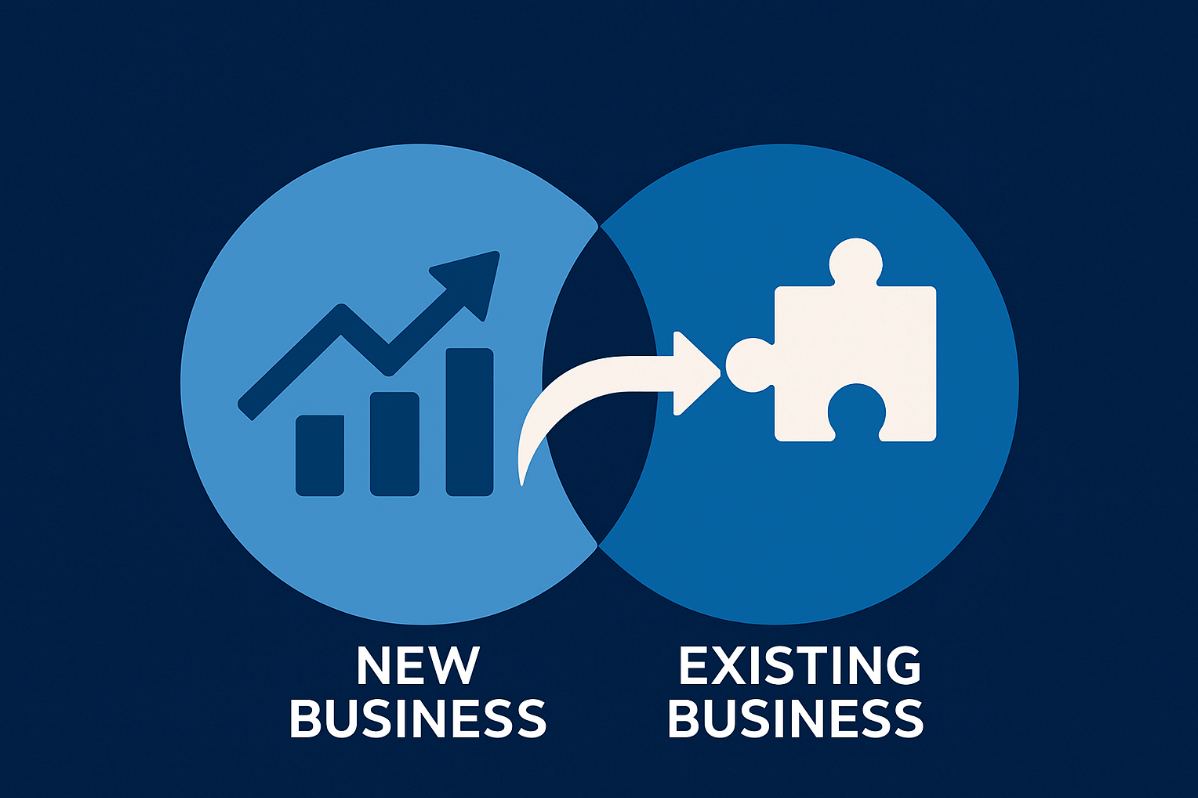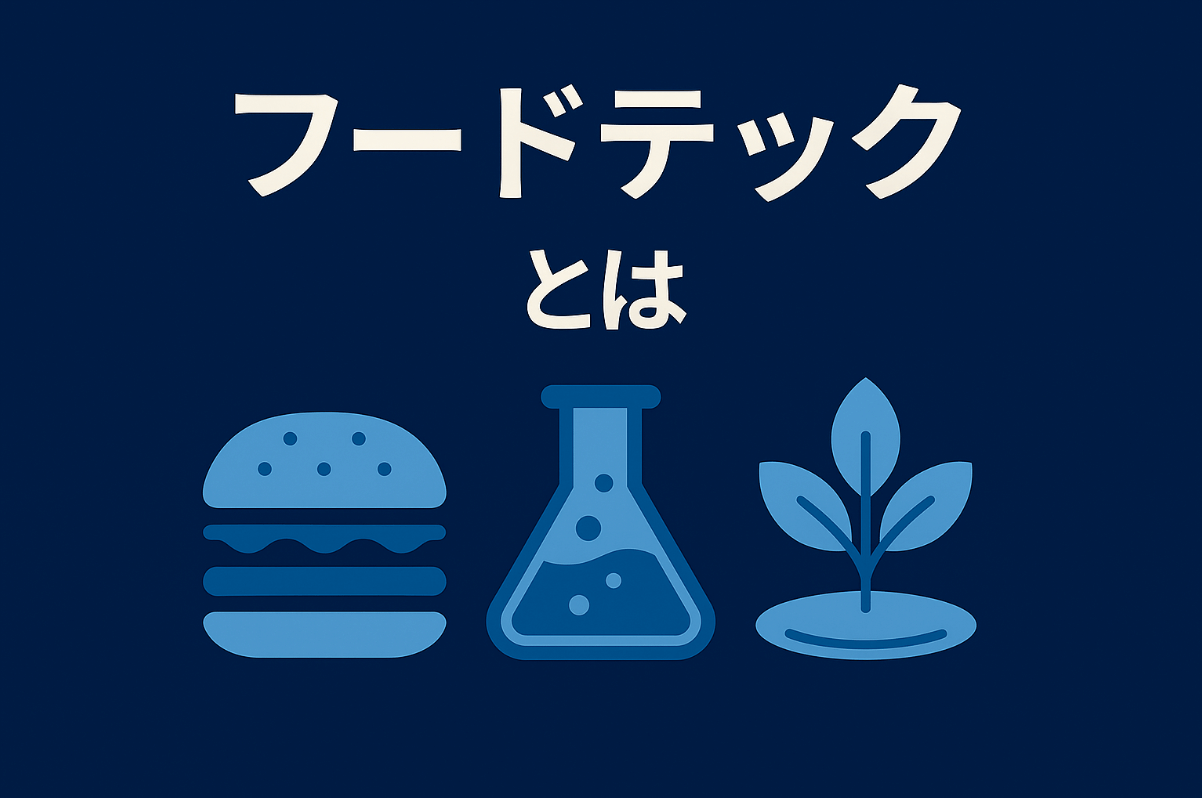新規事業の成功には、アイデアを形にするだけでなく、それが市場や顧客に受け入れられるかを確かめる「仮説検証」が欠かせません。しかし、具体的にどう進めればよいのか迷っている方も多いでしょう。
本記事では、仮説検証の基本的な意味や重要性をわかりやすく解説し、実践に役立つ5つのステップや具体的な手法、成功例・失敗例まで幅広く紹介します。
これから新規事業に取り組む企画担当者やマーケティング担当者は、ぜひ参考にしてください。
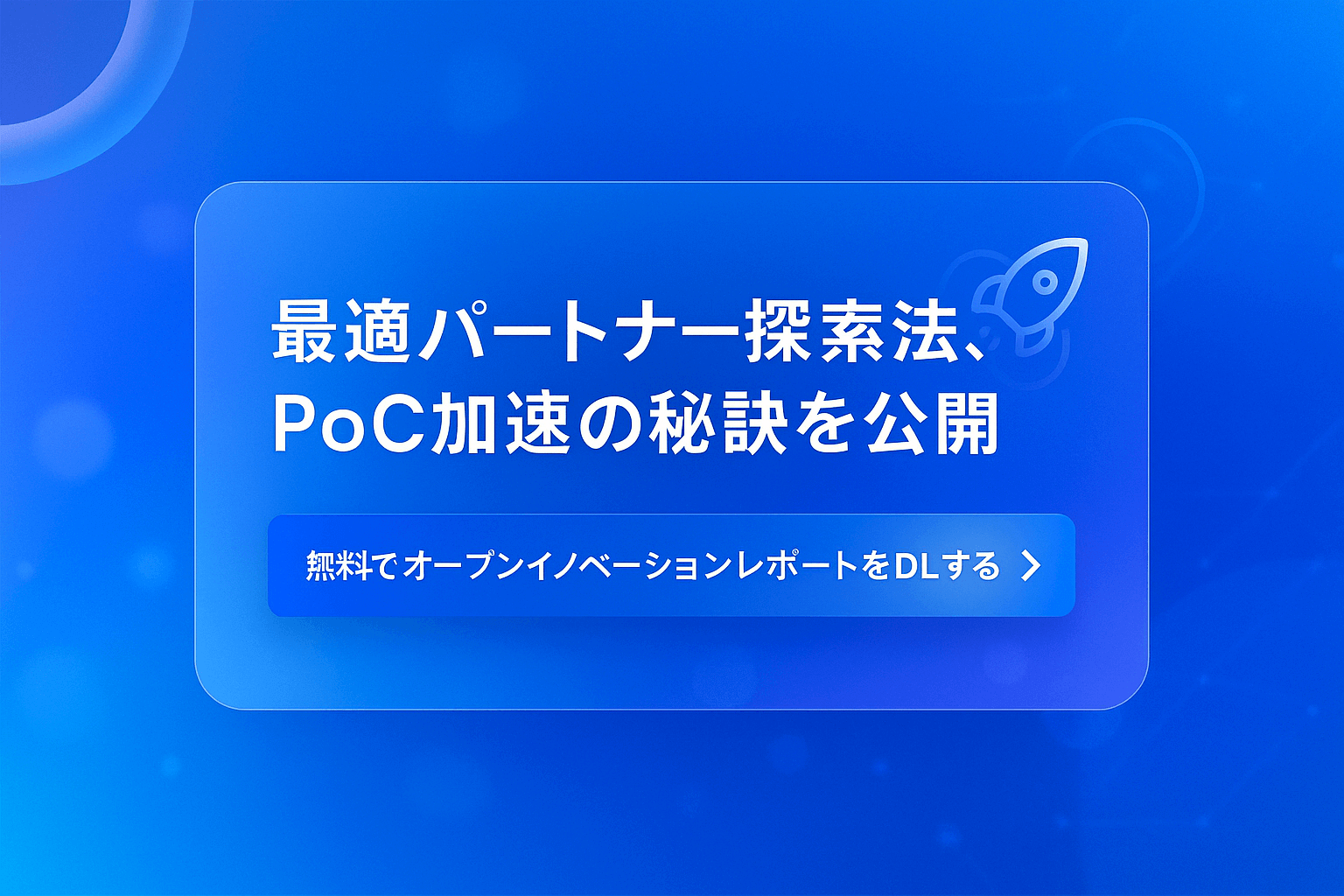
新規事業を確実に事業化に繋げる企業の秘訣をご覧ください
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。
大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。研究開発の成果を事業化に導く具体的な外部連携手法や成功パターンを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の研究開発事業化推進にご活用ください。
仮説検証とは?意味と重要性を理解しよう
新規事業を成功に導くために欠かせないのが「仮説検証」です。しかし、その言葉はよく聞くものの、具体的に何を意味し、なぜ重要なのかがわからない方も多いでしょう。
ここでは仮説検証の基本的な考え方と、その重要性についてわかりやすく解説します。
ビジネスにおける仮説検証とは何か
仮説検証とは、事業アイデアや仮説が「市場や顧客のニーズに本当に合っているか」を実際に試しながら確認するプロセスです。
PDCAサイクル(品質管理など業務管理における継続的な改善方法)を回しながら仮説の精度を高めていき、高品質なサービスや商品を生み出すことを目的としています。
なぜ新規事業に仮説検証が欠かせないのか
新規事業は不確実性が高く、思い込みだけで進めると失敗しやすいため、仮説検証が不可欠です。「考えたことが実際にニーズや市場に合うか」を早期に確かめることで、時間やコストの無駄を防ぎ、より実現可能性の高い事業へと繋げられます。
新規事業は検討項目が多い分、判断が遅れがちです。判断が遅れると市場ニーズが変わり、商品の寿命が短くなるリスクが高まります。
だからこそ仮説を立てて情報を集め、スピーディーに検証することが重要です。これにより方向性の見極めが早まり、事業推進のスピードも上がります。
このように、仮説検証は単なる確認作業ではなく、限られたリソースのなかで成功確率を高めるための戦略的なプロセスなのです。
PDCAとリーンスタートアップの違いと関係性
仮説検証はPDCAやリーンスタートアップの中核にある重要な考え方です。
PDCAでは計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)を通じて仮説を検証しながら進めます。
一方、リーンスタートアップは、最小限の機能を持つ製品(MVP)で市場の反応を見て仮説を確かめ、必要に応じて方向転換する手法で、仮説検証に特化しています。
つまり、どちらの手法も「試して学び、改善する」という仮説検証の考えが根底にあり、新規事業や改善活動の成否を左右する重要なプロセスです。
仮説検証の進め方|5つのステップで解説
仮説検証はただおこなうだけでは成果に繋がりません。効果的に進めるためには、明確な手順とポイントを押さえることが重要です。
この章では、仮説立案から検証、結果の分析と改善まで、5つの具体的なステップに沿って実践方法を丁寧に説明します。
① 仮説立案
まずは現状の課題を明確にします。「ターゲット層に商品が売れていない」「リピート率が低い」といった具体的な問題を洗い出します。
続いて、その結果になっている原因と具体的な改善方法を考えます。
「ターゲットのニーズと、自社が訴求しているポイントが異なるのではないか」「商品のパッケージを変更すれば、狙い通りのターゲット層の売り上げが伸びるかもしれない」などのように、できるだけ具体的な仮説を立ててみましょう。
効果的な仮説検証を進めるには、観察や実験などの客観的データで真偽を判断できる仮説を厳選することが重要です。
② 検証方法の設計
仮説を立てたら、仮説に合った検証手法を選びます。何をどのように測定するのかを明確にし、調査方法や実験方法を決定します。
商品パッケージを変更するとすれば、「色やデザインを変える」「イラストを写真に変える」「高級感を出すために、素材を紙袋から箱に変更する」など、どの部分をどう変えるかを決めましょう。
その際には、ユーザーインタビューやアンケートでニーズを深掘りしたり、MVP(Minimum Viable Product)を作り、実際に試してもらったりすることが有益です。
予算や期間を考慮しつつ、効果的な手法を組み合わせましょう。
③ 検証の実行
設計した検証を実際におこないます。ユーザーへのヒアリングや実地テスト販売など、多様な手段でリアルな反応を集めるのがポイントです。
たとえば「小ロットの新パッケージの商品をオンライン限定で販売する」「SNS広告で新旧のパッケージを宣伝し、インサイトを比較する」など、数字で比較できる形にするのがおすすめです。
検証の際はすべてのデータを記録し、客観的に評価できるようにしましょう。
④ 検証結果の分析
集めたデータは、定量的な数字(購入率、クリック率など)と定性的な意見(ユーザーの感想や要望)の両方を見て判断します。
数字だけで判断せず、ユーザーの本音を把握することで次の改善点が見えてきます。
⑤ 学びと改善
分析結果の評価に応じて仮説の妥当性を判断します。仮説が正しかったのであれば、本格的に事業や開発を進め、仮説が誤っていた場合は、その要因を深掘りして新たな仮説を立てて検証を繰り返しましょう。
このサイクルを小さく素早く回すことで、事業アイデアの精度を高められます。
仮説検証の手法の選び方と使い分けのコツ
仮説検証にはユーザーインタビューやアンケート、MVPなど多様な手法があります。それぞれの手法には得意な領域や目的が異なるため、目的や検証段階に応じて適切に選び使い分けることが成功の鍵です。
ここでは各手法の特徴を理解し、効果的に組み合わせるコツを解説します。
ユーザーインタビューで深掘りする方法
ユーザーインタビューは、商品やサービスを使用しているユーザーに直接質問し、回答を聞き取る手法です。対面で話を聞くことで、表情やしぐさからユーザー本人すら気づいていないニーズを発見できることもあります。
インタビュー方法には3種類あります。
| インタビュー方法 | メリット | デメリット | |
| 構造化インタビュー | 一問一答方式で決められた質問をする | 多くの回答者から同基準の情報を入手できる | 回答者の心理に踏み込みにくい |
| 半構造化インタビュー | 決められた質問以外にもアドリブで質問する | 聞きたいことだけでなく、回答者の心理まで読み取れる | インタビュアーの技量によって得られる情報の質が異なる |
| 非構造化インタビュー | テーマだけを決めて自由に質問する | 思いもよらない回答から発見できるポイントがある | 話が脱線しやすく時間がかかる |
インタビューをする側の技量や、インタビューできる時間に応じて形式を決めてみましょう。
アンケート調査で傾向を把握する方法
アンケート調査は多数の意見を集めて全体傾向を把握したい場合に適しています。
アンケート実施前には、チェックしておくポイントがいくつかあります。
- 対象者が適切か
- どの程度のサンプルを集められるのか
- 仮説検証のための項目が網羅されているか
- 正しく理解してもらえる質問であるか
- 見やすいレイアウトか
- 回答にかかる時間はどのくらいか
アンケートの回答結果は数値化しやすいため、チーム内での共有も簡単です。
アンケート調査を適切に設計し実施することで、客観的で信頼性の高いデータを得られ、より効果的な意思決定に繋げられるでしょう。
MVPやプロトタイプで仮説を市場でテストする方法
MVPやプロトタイプは、市場で仮説を実際にテストするために欠かせない手法です。
具体的には、最小限の機能を持つ試作品をユーザーに試してもらい、「仕様が適切か」「必要な機能が備わっているか」を検証します。これにより、ユーザーの反応を踏まえて素早く改善が可能となり、プロジェクト後半での大幅な仕様変更リスクを減らせます。
このように、MVPやプロトタイプを活用することで、コストを抑えつつ市場のニーズに合った価値ある製品を効率的に作り上げられます。
複数の手法を組み合わせるメリット
複数の仮説検証手法を組み合わせることで、より多角的かつ精度の高い検証が可能になります。
たとえば、ユーザーインタビューで深い洞察を得た後にアンケートで全体の傾向を確認し、MVPで実際の反応をテストするなどです。
複数の指標を組み合わせることで、信頼性の高い検証が可能になり、事業の成功確率を高められます。
仮説検証の成功例・具体例|業界別に見る実践パターン
実際の新規事業では、業界やサービスの特性に応じた仮説検証がおこなわれています。ここでは、オンライン教育やD2Cスキンケアブランド、SaaSプロダクトなど、具体的な業界ごとの成功事例を紹介し、それぞれの検証手法や工夫点を詳しく解説します。
自社のケースに応用しやすいヒントが見つかるでしょう。
事例① オンライン教育|EdTechスタートアップの「学習ニーズ仮説検証」
起業家輩出のスタートアップスタジオ「Gaiax」では中学生を対象に、事業立ち上げの仮説検証を実践的に指導しています。
リーンキャンバスの作成からユーザーヒアリングのアポイント取得まで、一連のプロセスを体験させるのが特徴です。
たとえば、eスポーツを盛り上げるビジネスアイデアを持つ生徒は、日本の賞金規模の小ささに着目。大手企業の取り組みも調査し、仮説検証を重ねて具体的な事業モデルを練り上げています。
こうした教育現場の取り組みは、若年層における仮説検証成功の具体例として注目されています。
事例② D2Cスキンケアブランド|低コストMVPと価格感検証
D2Cスキンケアブランドの仮説検証では、初期コストが高いため、低コストで市場反応を確かめる方法が重要です。
商品を作る前に価格を明示し、予約注文でニーズの深さを測ります。単なる連絡先の収集では実際の購入につながりにくいため、「お金を払うか」が最大の検証ポイントです。
さらに自宅での小ロット生産や詰め替え販売でコストを抑えつつ、リピート率もチェック。OEM生産はリスクや原価増のため慎重に判断し、在庫は初期少量で対応しながら、確実にニーズをつかんでから拡大します。
こうした段階的な検証がD2C事業成功の鍵となります。
事例③ SaaSプロダクト|機能優先順位とPMF検証
株式会社プレイドが開発したCXプラットフォーム「KARTE」は、2014年のクローズドα版で、プロダクトが未完成ながらも構想に共感したアパレルECサイトのスタートアップ数社とトライアルを開始しました。
PMF(Product Market Fit)検証を通じてユーザーと共同でUI/UXを改善し、クローズドβ版では大手アパレルECでも同様の共感を得て、実際の利用やユースケース開発、UXの磨き込みを進めています。
未完成のプロダクトを前提に、共感するユーザーと価値を共創しながらPMFへと繋げた点が特徴です。
このように、価値に共感した限られたユーザーと密に連携し、段階的に機能を磨くことで、B2B SaaSにおけるPMF達成に近づくモデルと言えます。
検証手法の使い分けと組み合わせ実践例
仮説検証にはさまざまな手法がありますが、単一の方法だけでなく複数を効果的に組み合わせることで、より精度の高い結果が得られます。
ここでは、実際の事例を交えながら、ユーザーインタビューから定量分析への移行や、営業活動を活用した法人向けの検証、さらにMVPとPoC(Proof of Concept:概念実証)を組み合わせた市場導入の進め方など、具体的な使い分けのコツを解説します。
ユーザーインタビュー→定量分析への進化
Photosynth社は、スマートロック「Akerun」の方向転換時に初期ユーザー100社へヒアリングを実施しました。そこで得た意見をもとに複数の市場・顧客セグメントの仮説を立て、ターゲット候補の顧客10人に対し詳細なヒアリングをおこない、強いニーズのあるセグメントを特定します。
このように仮説検証を繰り返すことで、売れる市場とペルソナを精緻化しました。顧客インタビューを定量分析へと進化させ、明確な検証結果をもとに製品戦略を策定した好例です。
営業活動を使った法人向け検証
営業活動を通じた仮説検証の一例として、freeeが新規プロダクト「freee福利厚生」の販売戦略見直しに取り組んだケースがあります。
従来の小規模事業者向けから、より大規模企業への訴求にターゲットを変更し、ABM施策やBDRを強化。1,000人以上の社員を巻き込んだ紹介依頼や手紙送付など、PUSH型の営業施策でアポイントを獲得しました。
さらに、インテントデータを活用し、社宅導入済企業の見極めや新たなターゲット仮説の検証を実施し、営業の現場で仮説と結果を行き来することで、精度の高い検証が進められました。
MVP+PoCで市場導入しながら改善
最小限の機能を持つMVPを用いて実際に市場に投入し、PoCとして顧客の反応や効果を検証しながら改善を進める手法も有効です。
例えば、ルート案内サービスの検証シナリオを考えてみましょう。MVPを用いて対象者にウォーキングを2時間してもらい、体験後のインタビューを通じて仮説を検証します。
PoCの段階では「シニアはウォーキングのルートがあらかじめ決まっている」といった意見が出る可能性があり、シニア層をターゲットにこのサービスを提供してもニーズがないことが明らかになるかもしれません。
このようにMVPとPoCを段階的に組み合わせることで、実際の導入に向けた課題や改善点を浮き彫りにする検証プロセスの一例となっています。
仮説検証でよくある失敗とその対策
仮説検証を進める過程で、よく陥りがちなミスや落とし穴があります。仮説が不明確なまま検証をはじめてしまったり、データのバイアスに気づかず誤った解釈をしたり、結論を先に決めてしまうケースも少なくありません。
本章では、そうした失敗例を挙げつつ、それぞれに対する具体的な対策を紹介し、より効果的な検証プロセスの構築をサポートします。
仮説が曖昧なまま検証をはじめてしまう
仮説が不明瞭だと、検証の方向性が定まらず効率が悪くなります。
検証の目的や対象がはっきりしていないために、集めたデータが散漫で意味を成さない場合が多いです。
そのため、検証をはじめる前に仮説を具体的かつ明確に設定し、範囲や目的をはっきりさせることが不可欠です。
バイアスのかかったデータの解釈
自分の先入観や過去の経験が影響すると、データの正しい読み取りができなくなります。
たとえば、都合のよい情報だけを抜き出して判断し、全体像を見誤ってしまうことがあります。
こうした問題を避けるためには、データは客観的に分析し、異なる視点を持つ第三者の意見も積極的に取り入れましょう。
結論ありきで検証を進めてしまう
最初から「こうなるはず」と結果を決めつけてしまうと、公平な検証が妨げられます。
検証過程で不都合なデータを無視し、自分の仮説を裏付ける情報だけを重視するケースも見られます。
検証の際は、結果に固執せず、データが示す内容を素直に受け止める姿勢を持つことが大切です。
検証結果が事業に反映されない
検証しても事業に結びつかなければ意味がありません。たとえば、課題が明確になっても社内で共有されず、具体的な対応がおこなわれないケースがあります。
検証結果は経営層や関連部署にしっかり伝え、実際の施策に落とし込む仕組みを整えることが必要です。
適切な仮説検証を繰り返し、精度の高い新規事業へと育てよう!
仮説検証は単なるチェック作業ではなく、新規事業を成功に導くための重要な成長プロセスです。小さなステップを素早く回し、データとユーザーの声をもとに仮説を磨き上げることで、リスクを抑えながら確実に成果を積み上げていきましょう。
チーム全員で仮説を共有し、合意形成しながら進めることも忘れずに。こうした積み重ねが成功への近道となります。
新規事業を確実に事業化に繋げる企業の秘訣をご覧ください
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。
大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。研究開発の成果を事業化に導く具体的な外部連携手法や成功パターンを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の研究開発事業化推進にご活用ください。