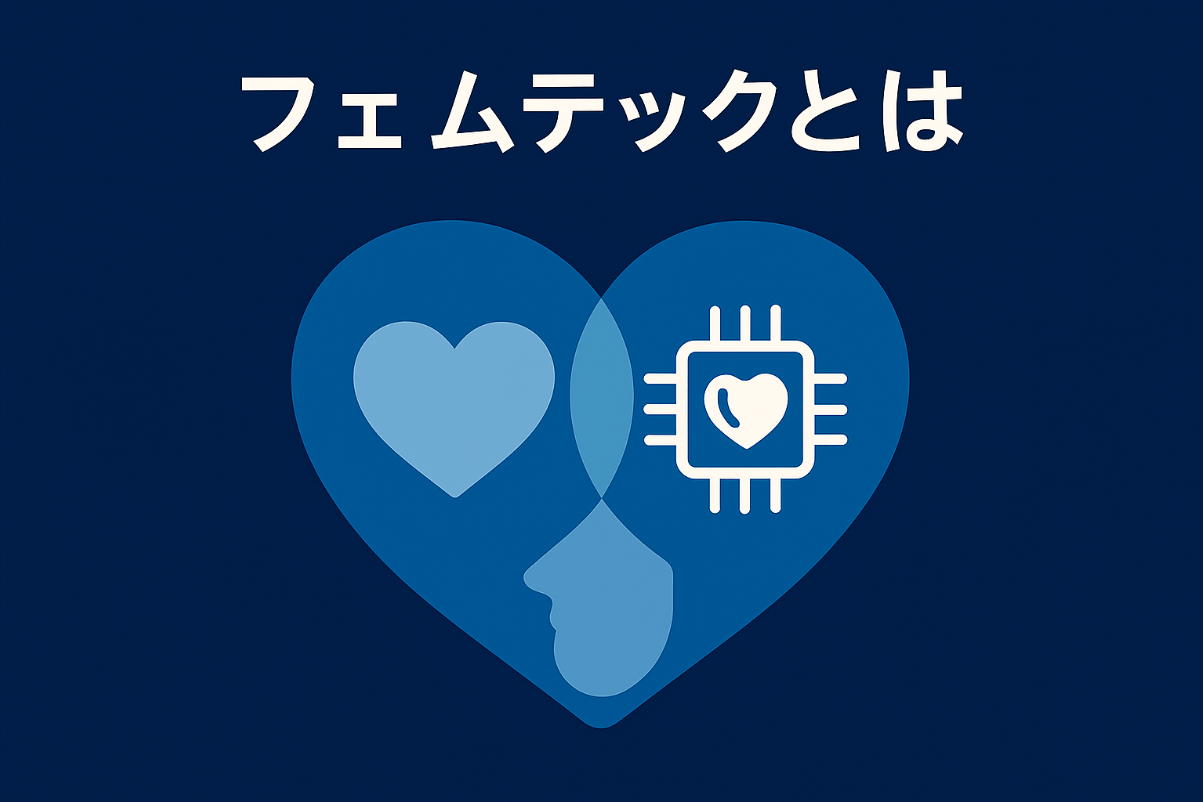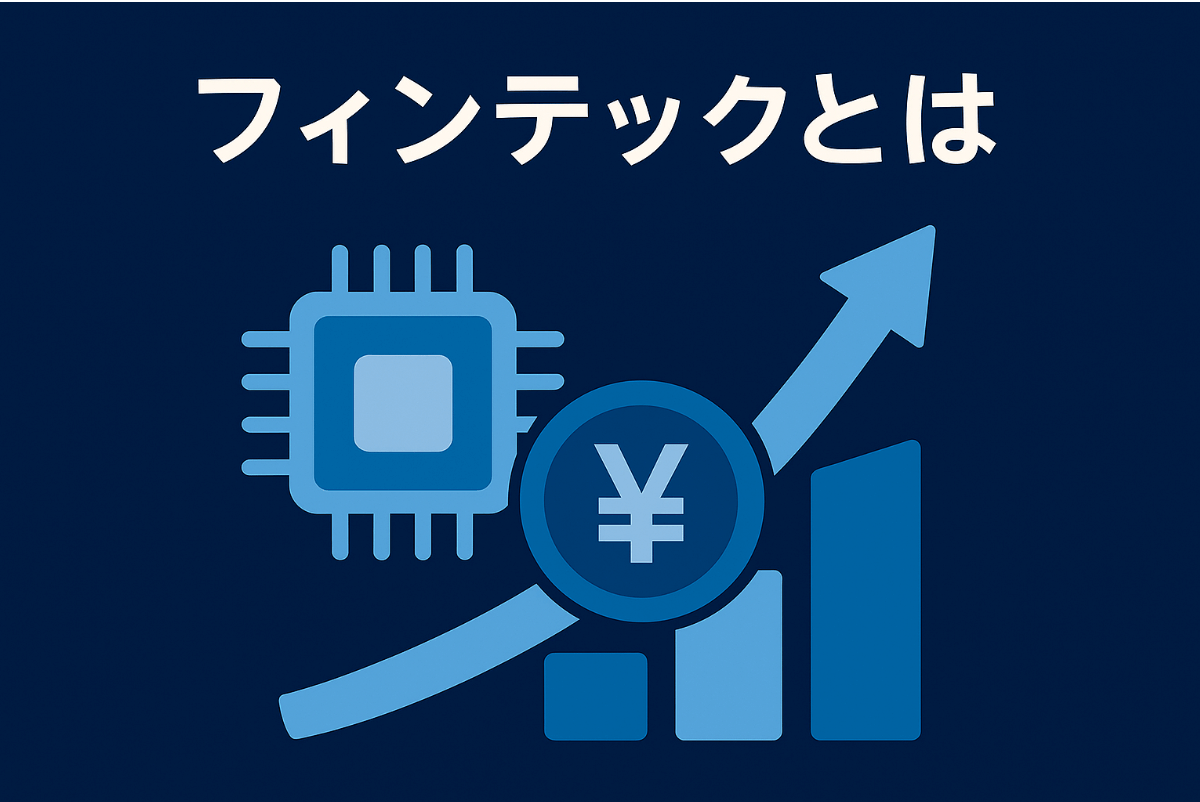近年、女性の健康課題をテクノロジーで解決する「フェムテック」が注目を集めています。月経や妊活、更年期といったライフステージにまつわる悩みは、これまで個人的な問題として扱われがちでしたが、今では社会的・経済的なテーマとして認識され、企業や自治体の関心も高まっています。
そこで今回は、フェムテックの定義や市場動向、主要ニーズ、注目企業の事例、そして事業開発におけるポイントまでを網羅的に解説します。フェムテック領域への理解を深め、新たな事業展開や支援活動のヒントを得たい方は、ぜひ参考にしてみてください。
フェムテック分野への参入は専門スタートアップとの連携が成功の鍵!
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
専門分野での具体的なパートナー探索方法や専門技術を持つスタートアップとの連携ポイントを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の事業開発にご活用ください。
フェムテックとは?|定義と注目される背景
女性の健康課題に対する関心が高まるなか、「フェムテック」という言葉を目にする機会が増えています。月経や妊活、更年期など、これまで見過ごされがちだった課題にテクノロジーでアプローチするこの分野は、社会的意義と市場性の両面で注目を集めています。ここでは、フェムテックの定義や成り立ち、フェムケアとの違い、そして注目される社会的・経済的背景について解説します。
フェムテックの定義と成り立ち
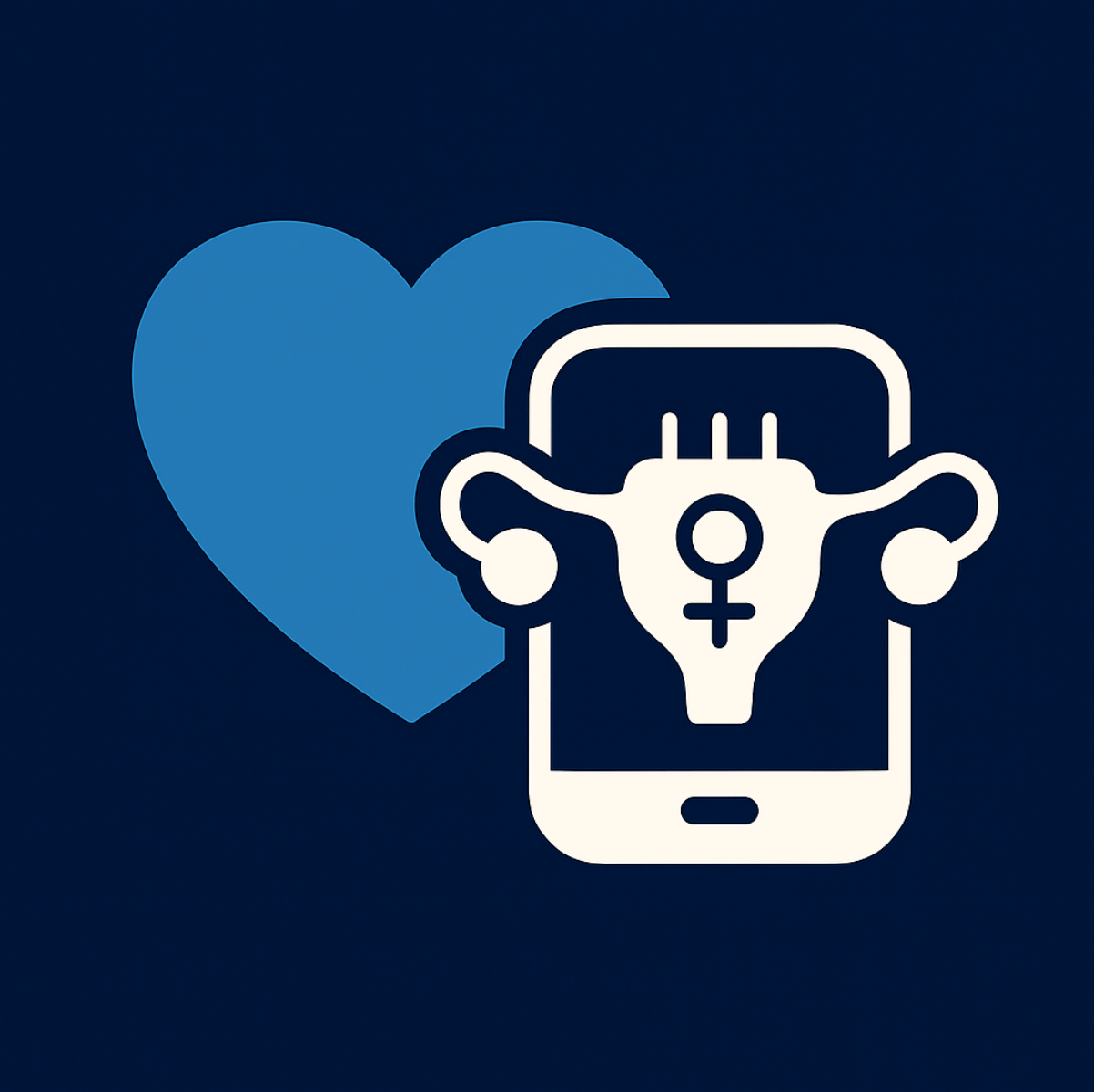
フェムテックとは、「Female(女性)」と「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語で、女性特有の健康課題をテクノロジーで支援する製品やサービス全般を指します。この言葉は、2013年にリリースしたドイツ発の月経管理アプリ「Clue(共同創業:Ida Tin氏)」の創業に際して用いられ始め、投資家向けのキャッチコピーとして2012年頃に考案され、2013年ごろから徐々に浸透し始めたといわれています。
当初は月経管理や妊娠サポートが中心でしたが、現在では更年期ケア、性の健康、骨盤底筋トレーニング、妊活支援など、女性のライフステージ全体を支える領域へと広がっています。
フェムケアとの違い
フェムテックとフェムケアはいずれも、女性特有の健康課題に向き合う製品やサービスを指しますが、アプローチには明確な違いがあります。フェムケアは「Feminine(女性の)」と「Care(ケア)」を組み合わせた言葉で、月経、妊娠、更年期といったライフステージに寄り添うケア用品やサービスを指します。テクノロジーを用いないスキンケア製品や吸水ショーツ、カウンセリングなどが代表例です。
一方、フェムテックはテクノロジーを活用して課題を解決しようとする概念です。AIやIoTを活用した月経管理アプリ、在宅検査キット、ウェアラブルデバイスなどが代表的な例です。
注目される社会的・経済的背景
フェムテックが注目される背景には、ジェンダー平等への意識の高まりや、女性特有の健康課題が可視化されつつある社会的な動きがあります。近年、女性の社会進出が進む一方で、生理による体調不良や更年期、不妊といった健康上の問題が、キャリアの継続や生活の質に影響を及ぼすケースが顕在化しています。
経済産業省の推計によれば、これらの課題による経済損失は年間で約3.4兆円にのぼるとされています。こうした状況の中、フェムテックはテクノロジーを活用することで、女性の体調不良や不安を軽減し、労働生産性の向上や医療費の抑制にもつながる手段として期待されています。
参考:経済産業省「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」
フェムテックがカバーする領域と主要ニーズ
フェムテックは、月経・妊活・更年期といったライフステージごとの健康課題をはじめ、性の健康やジェンダー問題、企業の健康経営まで多岐にわたる領域をカバーしています。ここでは、フェムテックが対応する主な領域とニーズについて詳しく見ていきましょう。
月経・妊活・更年期など、ライフステージ別ニーズ
女性の体はライフステージごとに大きく変化し、それぞれの段階で特有の健康課題が現れます。月経期にはPMS(月経前症候群)や生理痛への対処、妊活期には排卵の把握やホルモンバランスの管理、更年期にはホットフラッシュや不眠といった症状への対応が求められます。
フェムテックは、こうした課題に対してテクノロジーを活用した解決策を提供しています。月経管理アプリ、妊活支援キット、更年期のホルモン変化を測定できるデバイスなどが登場し、女性が自身の体調を客観的に把握しやすくなってきました。
性の健康・ジェンダー課題との接続性
フェムテックは、女性の身体的な健康にとどまらず、性の健康やジェンダーに関する課題とも深く関わっています。たとえば、月経や更年期、不妊といったテーマは、これまで「個人的な問題」として語られることが多く、社会の中で共有されにくい傾向がありました。そうした課題をタブー視せずに可視化し、支え合える仕組みを築くことが求められています。
また、性教育の不足や避妊・性感染症対策への関心の低さといった問題についても、フェムテックを通じた情報提供や自己管理ツールの普及により、改善が期待されます。さらに、LGBTQ+を含む多様な性のあり方を前提とした製品開発も進んでおり、性の自己決定を尊重する姿勢が社会の中で少しずつ広がりつつあります。
企業の福利厚生や健康経営との関係
近年、従業員の健康を経営的な視点で支える「健康経営」が企業の間で広がりを見せており、フェムテックの導入もその一環として注目されています。特に、生理痛や更年期、不妊治療といった女性特有の健康課題に対する支援は、職場環境の改善や離職率の低下に直結する重要な施策です。
たとえば、月経管理アプリや不妊治療支援サービスを福利厚生として導入することで、プレゼンティーズムの軽減や女性のキャリア継続の後押しになります。また、こうした取り組みは企業ブランディングの向上にも貢献し、優秀な人材の確保にもつながります。
フェムテック市場の動向|成長性と注目トピック
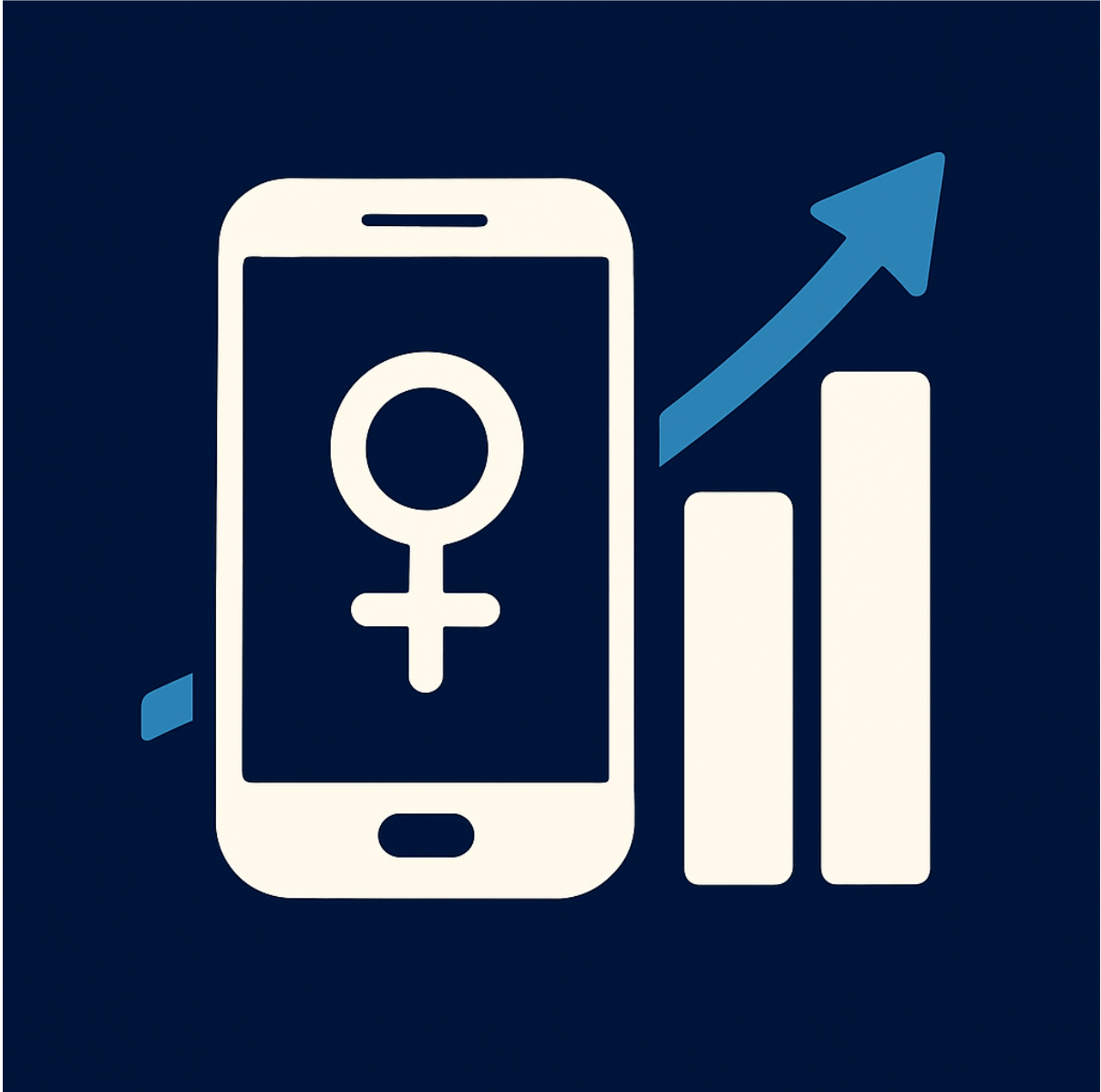
フェムテック市場は、世界的に注目を集める成長分野のひとつです。女性の健康課題に対する関心の高まりやテクノロジーの進化を背景に、各国で市場規模が拡大し、革新的なスタートアップや新規プロダクトの登場も相次いでいます。ここでは、国内外の成長予測や注目されるトピックを詳しく解説します。
国内外の市場規模と成長予測
フェムテック市場は、国内外で急速に拡大しています。調査によると、フェムテック市場は2025年以降も拡大基調が続き、2030年までの5年間で年平均16.37%の成長率を維持すると予測されています。その結果、2030年には市場規模が972億5,000万米ドルに達するとされています。
特に北米や欧州では、女性の健康意識の向上とスタートアップの台頭により、市場が成熟しつつあります。一方、日本市場は2025年時点で約5.5兆円規模とされていますが、経済産業省による実証事業などの取り組みを契機に、今後の成長が期待されるでしょう。
また、アジア太平洋地域ではスマートフォンの普及や医療リテラシーの向上を背景に、最も高い成長率が見込まれています。
フェムテック投資・スタートアップ動向
フェムテック市場の成長にともない、国内外でスタートアップへの投資が活発になっています。世界全体の投資額は2022年に約160億ドルに達し、2027年には1兆2,000億ドル規模に拡大する見通しです。
特に、AIやIoTを活用した月経管理、妊活支援、更年期ケアといった分野では、新興企業による革新的なプロダクト開発が進んでいます。企業向けの福利厚生サービスへと応用される事例も増えてきました。
日本国内においても、2024年はCVCやVCを通じた資金調達が活発化しており、AI解析ソフトを開発する「Spiker」などが注目を集めています。同社は周産期死亡率の低下といった課題に取り組んでおり、自社サイトではアフリカ地域の状況を事例として紹介しています。
政策・支援の動きとビジネスへの影響
フェムテック市場の成長に向け、政府や自治体による支援の動きも広がっています。経済産業省は「フェムテック等サポートサービス実証事業」を実施しており、企業や自治体との連携促進や補助金の提供など、導入支援の枠組みを整えてきました。
特に、月経・妊活・更年期といったテーマに関連するサービス導入や啓発活動が重視され、福利厚生や健康経営の一環としてフェムテックを取り入れる企業も増加傾向にあります。
あわせて、プロダクトの品質基準整備やプライバシー保護に関する仕組みづくりも求められており、産官学の連携によるルール策定が重要な課題とされています。
参考:経済産業省「フェムテックを活用した働く女性の就業継続支援」
注目技術とプロダクトのトレンド|フェムテックを支える要素
フェムテックの発展を支えているのは、日々進化するテクノロジーと、それを活用した革新的なプロダクトの数々です。ここでは、フェムテック領域を牽引する注目技術とプロダクトの最新トレンドを紹介します。
アプリ・IoT・ウェアラブルの活用
アプリやIoT、ウェアラブルデバイスの活用は、フェムテックを支える重要な技術基盤とされています。たとえば、月経管理アプリや基礎体温を自動記録するIoT機器、痛みを緩和するウェアラブルなどが登場し、女性の体調管理や不調の可視化を後押ししています。
なかでも、心拍センサー付きのスマートインナーとチャットボットを連携させ、産後うつリスクの早期把握を目指す取り組みは注目されています。こうした試みは、テクノロジーを通じた予防的支援の可能性を広げています。
一方で、フラー社の調査によれば、2022年9月時点で日本のスマホユーザーにおけるヘルスケアアプリの利用率は53%に達しており、2019年9月と比べて21ポイント増加しています。今後は働く女性のライフスタイルに即したプロダクトの開発と普及が期待されます。
参考:フラー株式会社「スマホアプリユーザーのヘルスケアアプリの利用率は53%と3年前の1.7倍に。」
AI・データ活用によるパーソナライズの進化
AIとデータ解析の進展により、フェムテックにおけるパーソナライズはより精度を増しています。たとえば、月経周期や基礎体温、気分の変化といった日常的なデータをAIが継続的に学習することで、個々の体調や傾向に応じた予測やセルフケアの提案が可能となりました。
こうした機能は、PMSや妊活、更年期のケアにも応用されており、自身の体調リズムを把握しやすくなる点が特徴です。なかには、月経やそれによる肌荒れの予測に加え、睡眠・運動・栄養といった生活習慣に関するアドバイスも個別に提供してくれるアプリもあります。
デザインとUX視点の重要性
フェムテック製品を継続的に利用してもらうためには、機能面の充実だけでなく、ユーザー体験(UX)を重視した設計も必要です。特に、症状が可視化されにくい健康領域においては、「使いやすさ」や「共感を得られるデザイン」が行動変容のきっかけになります。
たとえば、月経管理アプリ「Clue」では、ピンクなどの既存のジェンダーイメージを排し、シンプルかつ上品なUIを採用。多様なユーザーにとって心地よい設計を追求しています。
このようなUX設計の工夫は、ヘルスリテラシーが高くない層にも届きやすい特長があります。
フェムテックの具体事例|国内外の注目プロダクト&企業
フェムテック市場の拡大にともない、国内外で革新的なプロダクトや注目企業が次々と登場しています。ここでは、フェムテックの可能性を体現する先進事例を紹介します。
ルナルナ(MTI)|国内月経管理アプリの先駆け
ルナルナは、株式会社エムティーアイが提供する日本初の月経管理アプリとして、2000年に誕生しました。ガラケー時代に登場し、生理日を手軽に記録できるサービスとして、多くの女性に利用されてきました。
現在では、月経管理に加えて妊活支援やピルの服薬管理、不妊治療のサポート機能などを備え、ライフステージを通じたウィメンズヘルスケアサービスへと進化しています。さらに、医療機関や自治体との連携、大学との共同研究にも積極的に取り組んでおり、フェムテック領域を牽引する存在といえるでしょう。
20年以上にわたり蓄積されたデータは、体調の予測精度向上や啓発活動にも活用されており、国内市場において信頼性の高いプロダクトとして注目されています。
Clue|世界で1,500万人以上利用の月経管理アプリ
ドイツ発の月経管理アプリ「Clue」は、1,500万人以上のユーザーに利用されている国際的なフェムテックプロダクトです。生理日や排卵日の予測に加え、PMSや気分の変化、経血量などを詳細に記録でき、日々の体調を科学的に可視化することができます。
前述のように、Clueはピンクや装飾的な要素を排した中立的なUIを採用しており、ジェンダーに依存しない設計を徹底しています。
また、記録データを広告目的で使用せず、医学的根拠に基づいたヘルスケア情報の提供を重視している点も信頼を集める理由のひとつです。妊活モードや避妊ピルの服用リマインド機能も備えており、ライフステージを問わず女性の健康管理を支援する代表的なフェムテック事例といえるでしょう。
inne|ドイツ発の在宅検査デバイス
ドイツ発のフェムテック製品「inne(インネ)」は、自宅でホルモン変化を手軽に測定できる在宅検査デバイスです。唾液ストリップを使って毎日プロゲステロンの数値を記録することで、月経周期や排卵日の状態を可視化できます。
侵襲性がなく、副作用の心配もないため、妊娠しやすい時期やホルモンの変動を把握したい女性にとって注目のデバイスです。さらに、子宮頸部の状態とホルモンバランスの関連性を確認できる機能も備えており、妊活や体調管理、パートナーとの情報共有にも役立ちます。
専用の読み取り機とアプリ、唾液ストリップを組み合わせたサブスクリプション型の仕組みにより、日々のデータを蓄積しながら、より正確な体調管理が可能になります。
Progyny|BtoEの不妊治療サービス
米国発のフェムテック企業「Progyny(プロジニー)」は、企業向け(BtoE:Business to Employee)の不妊治療支援サービスを展開し、従業員のライフイベントを包括的にサポートしています。従業員は妊活・不妊治療・代理出産・養子縁組・出産・更年期といった幅広い段階において、専門の医療ネットワークとケアアドバイザーによる個別サポートを受けることができます。
企業側にとっては、福利厚生の一環として導入することで、従業員満足度やエンゲージメントの向上、人材定着にも貢献します。現在ではGoogleやMicrosoftなど500社以上が導入しており、女性の健康課題を企業経営の視点から捉える先進的な取り組みとして注目されています。
fermata|フェムテックのプラットフォーム型展開
フェルマータ株式会社(fermata Inc.)は、フェムテック領域に特化した日本発のプラットフォーム型企業。女性特有の健康課題に向き合い、「あなたのタブーがワクワクに変わる日まで」をビジョンとして掲げています。企業・行政・医療機関など多様な関係者と連携しながら、商品開発の支援、流通体制の構築、展示イベント「Femtech Fes!」の開催までを一貫して展開しているのが特長です。
特に、潜在ニーズの可視化や薬機法への対応など、高度な専門支援に強みを持ちます。
フェムテックにおける事業開発・導入のポイント
フェムテック市場の拡大にともない、企業や自治体が事業として参入・導入を検討する動きが活発になっています。ここでは、フェムテック領域における事業開発・導入のポイントや、信頼性の高い展開を実現するための視点を解説します。
参入のポイント|共感・共創・多様性の視点
フェムテック領域への参入においては、単にテクノロジーを活用したプロダクト開発にとどまらず、「共感」「共創」「多様性」を軸とした姿勢が重要です。女性特有の健康課題は、これまで語られにくく、個人の内面にとどまりがちでした。そのため、ユーザーの声に丁寧に耳を傾け、当事者目線で課題を捉える共感的アプローチが不可欠です。
また、医療・企業・行政・市民といった多様な関係者と連携し、社会全体で支える共創型のビジネスモデルが信頼構築につながります。さらに、ジェンダーや年齢、ライフスタイルの違いを尊重し、多様なニーズに応える設計を心がけることで、誰もがアクセスしやすいフェムテックが実現します。
新規事業開発とフェムテックの相性
フェムテックは、未開拓のニーズが多く残されている領域。新規事業開発との親和性が高く、柔軟な発想と試行を重ねやすい分野です。近年では、社会的関心の高まりやテクノロジーの進展を背景に、新たなサービス創出への機運が高まっています。
特にフェムテックは、衣料、製薬、食品、保険、ITなど、既存事業と連携しやすく、異業種とのシナジー(相乗効果)も生み出しやすい特徴があります。従業員の声を起点とした社内実証から事業化へと進む事例も見られ、SDGsや健康経営といった社会的課題と接続することで、企業価値の向上にもつながります。
導入・協業の際に意識したい課題と配慮
フェムテックの導入や他社との協業にあたっては、女性の健康課題が個人差の大きいセンシティブなテーマであることを十分に理解し、丁寧な配慮が求められます。特に、製品やサービスの開発段階から当事者の声を積極的に取り入れ、ジェンダーバイアスや価値観の押し付けを避ける姿勢が重要です。
また、自治体や企業、医療機関と連携する際には、プライバシー保護や情報管理の徹底も欠かせません。フェムテックという概念がまだ明確に定義されていない中では、過剰な広告表現や信頼性に乏しい商品が混在する懸念もあるため、業界全体で品質基準や認証制度の整備が必要とされています。
フェムテックは社会課題解決とビジネス成長の両立へつながる
フェムテックは、女性の健康課題という社会的テーマにテクノロジーで向き合うことで、課題解決とビジネス成長を同時に実現できる注目分野です。月経・妊娠・更年期などのニーズに対応する製品やサービスが広がり、企業の健康経営や福利厚生への活用、スタートアップとの協業も進んでいます。今後は多様なライフスタイルやジェンダーに寄り添った設計、多様な産業との連携が求められるでしょう。
新規事業の開発やフェムテック領域への参入を検討されている企業の皆様には、大手企業とスタートアップの共創を支援する「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」の活用がおすすめです。最新のマッチング事例や提携成功のノウハウを知りたい方は、ぜひILSレポートのご請求や説明会への参加をご検討ください。
フェムテック分野への参入は専門スタートアップとの連携が成功の鍵!
本メディアではアジア最大級のオープンイノベーションマッチングイベント「ILS(イノベーションリーダーズサミット)レポート」を無料配布しています。大手企業とスタートアップが3,000件以上の商談を重ね、協業案件率30%超えのイベントです。
専門分野での具体的なパートナー探索方法や専門技術を持つスタートアップとの連携ポイントを豊富に扱っているので、ぜひ貴社の事業開発にご活用ください。